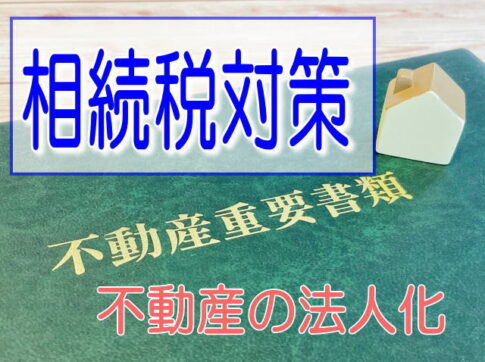親が所有する家に住んでいる方が、その家を相続することになった場合に気になるのは「相続税」です。
親の所有してる家なら、相続税が課税される可能性があります。しかし、一定の要件を満たせば、相続税を大幅に軽減できる控除や特例もあります。
そこで、本記事では、親名義の家に住んでいる方が相続する際の相続税のしくみと、知っておくべき重要な節税ポイントについて解説します。
安心して住み続けるための知識を身につけましょう。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
親名義の家には「相続税」が課税される可能性がある

住んでいた家を所有していた親が亡くなった場合、相続が発生するため「相続税」が課税される可能性があります。
親名義の家の相続における手続きは、遺言書の有無によって大きく異なるため、手続きの流れが異なります。詳しくは以下です。
遺言書がある場合
家を所有していた被相続人(親)が有効な遺言書を作成していた場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。手続きの流れは以下です。
- 遺言書の確認
遺言書が保管されていないか確認します。公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、公証役場に検索を依頼できます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。(※) - 遺言執行者の選任(必要な場合)
遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その方が遺産分割の手続きを進めます。指定がない場合は相続人全員で手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。 - 相続財産の評価
相続する家(土地・建物)を含む全ての相続財産の評価額を算出します。不動産の評価額は、路線価方式や固定資産税評価額を基に計算されます。 - 相続税の計算・申告・納税
算出した相続財産総額から基礎控除額などを差し引いた課税遺産総額に、相続税率を掛けて相続税額を計算し、申告・納税を行います。 - 不動産の名義変更
相続により取得した家の名義を、家を取得する人へと変更する相続登記手続きを行います。(※)自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認不要です。
遺言書がない場合
家を所有する親が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を、どのように相続するかを決定する必要があります。手続きの流れは以下です。
- 相続人の確定
誰が法定相続人となるかを戸籍謄本などを収集して確定します。 - 相続財産の調査・評価
相続する家(土地・建物)を含む全ての相続財産の調査を行い、評価額を算出します。 - 遺産分割協議
相続人全員で、どの財産を誰が相続するかについて話し合いを行います。相続人全員の合意が必要です。 - 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名・押印する必要があります。 - 相続税の計算・申告・納税
算出した相続財産総額から基礎控除額などを差し引いた課税遺産総額に、相続税率を掛けて相続税額を計算し、申告・納税を行います。 - 不動産の名義変更
作成した遺産分割協議書に基づき、相続により取得した人が家の名義を変更する相続登記手続きを行います
親名義の家を相続する際の注意点とは
 親が所有していた家を相続する際には、さまざまな注意点があります。
親が所有していた家を相続する際には、さまざまな注意点があります。
特に相続税は定められた期限内に納付する必要があるため、できれば相続発生前からしっかりと理解しておくことが重要です。
この章では、親名義の家を相続する際の注意点について解説します。
相続税は課税されない場合もある
親名義の家を相続した場合、必ず相続税が課税されるわけではありません。相続財産の総額が、以下の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が1人の場合は基礎控除額は3,600万円となります。
相続する家の評価額と、その他の相続財産(預貯金、有価証券など)の合計額が3,600万円以下であれば、相続税の申告・納税は不要です。
また、相続税には多くの特例や控除が用意されています。こうした制度を活用することで相続税額を大幅に減らす、あるいはゼロにできる場合もあります。
ただし、適用を受けるためには相続税申告が必要な控除などもあります。申告前には税理士に確認し、必要手続きを必ず確認しましょう。
自宅以外の相続財産も調査・計算が必要
相続税の課税対象となるのは自宅の土地・建物だけではありません。親が遺した現金や預貯金、有価証券などの財産も課税対象です。
したがって、自宅以外の相続財産も漏れなく調査し、正確に評価額を算出する必要があります。
また、相続税の計算には債務も含めます、親名義の家にローンがあったり、消費者金融などからの借入がある場合は相続財産の総額から控除できます。(債務控除)
相続時の不動産評価は複雑のため注意が必要
 相続する家の評価額は、土地と建物それぞれで計算方法が異なります。特に土地の評価は、路線価を基準にさまざまな補正が行われるため、複雑になることがあります。
相続する家の評価額は、土地と建物それぞれで計算方法が異なります。特に土地の評価は、路線価を基準にさまざまな補正が行われるため、複雑になることがあります。
形状が不整形であったり、道路との接道状況が特殊であったりする場合、専門家でなければ適正な評価額を算出することが難しいことも少なくありません。
過大に評価してしまうと相続税を払い過ぎてしまう可能性もあります。親名義の家を相続する際には早めに相続に強い税理士に相談し、不動産の適正な評価額を把握するとともに、適用できる特例や節税対策についてアドバイスを受けることが非常に重要です。
次に、家屋と土地の評価方法を説明します。
家屋の評価方法
相続税における家屋(建物)の評価額は、原則として固定資産税評価額に1.0を乗じた金額となります。
つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
土地の評価方法
相続税における土地の評価方法は、大きく分けて路線価方式と倍率方式の2つがあります。
- 路線価方式
市街地など、主要な道路に国税庁が定める「路線価」が付いている地域で用いられます。路線価は、その道路に面した1平方メートル当たりの土地の価格を示しており、実際の土地の評価額は、路線価 × 土地の面積で計算されます。
ただし、土地の形状(間口、奥行き、不整形地など)や利用状況(貸宅地、自用地など)に応じて、奥行価格補正や不整形地補正などの画地調整が行われ、評価額が複雑になることがあります。 - 倍率方式
路線価が定められていない郊外などの地域で用いられます。この場合、土地の評価額は、固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率で計算されます。倍率は、土地の地目(宅地、畑、山林など)や地域によって異なります。
親と子|一体誰が亡父の家を相続すべき?

家を所有していた父親が亡くなり、家族が相続する際には、誰がその家を相続することが相続税対策につながるのでしょうか。
相続は、単に財産を受け継ぐだけでなく、その後の生活や税金にも大きく影響を与えるため慎重な判断が必要です。
ここでは、配偶者である母が相続する場合と、子が相続する場合のメリット・デメリットを紹介します。誰が相続するか悩んだ際には、ぜひヒントにご活用ください。
母が相続するメリット・デメリット
亡父の配偶者である母が家を相続するメリットは以下です。
配偶者の税額軽減が使える
配偶者は相続税の計算の際に、「配偶者の税額軽減」という特例を利用できます。これにより、お母様が相続した財産のうち、一定額(1億6千万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額)までは相続税が課税されません。これは、特に相続財産に占める家の割合が大きい場合に、大きな節税効果を発揮します。
生活基盤を守れる
母が現在その家に住んでいる場合、相続によって引き続き住み慣れた生活を送ることが可能です。特に高齢者の場合、亡夫の住まいを守りたいという思いが強く、相続時には母に家を相続させるケースは多くなっています。
次に、デメリットは以下です。
二次相続が高くなる
家を取得した母が亡くなった際、子が再度その家を相続することになり、その際に相続税が発生する可能性があります。この時は配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続時よりも相続税が高くなります。
将来的な空き家のリスク
現在母が住んでいても、将来的に老人ホームへの入居など、住み替えの可能性がある場合、相続した家の活用や処分法を検討する必要があります。
子が相続するメリット・デメリット
子が相続するメリットは以下です。
将来的な空き家リスクの低下
お子様が直接相続することで、家の売却や資産運用を決めやすくなり将来的な空き家リスクを減らすことができます。
二次相続の負担を減らせる
子が一次相続の段階から家を相続しておくことで、二次相続で発生する相続財産を経R素効果があり、相続税対策の効果があります。
次にデメリットは以下です。
配偶者の税額軽減が利用できない
子が相続する場合、「配偶者の税額軽減」は利用できません。相続財産に占める家の評価額が大きい場合、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
小規模宅地等の特例が使えないおそれ
子が亡くなった父と同居していなかった場合、「小規模宅地等の特例」の適用を受けるための要件が厳しくなることがあります。同居していれば、自宅の土地の評価額を大幅に減額できる可能性があります。
家の維持管理の負担
子が現在その家に住んでいない場合でも、相続すると固定資産税などの維持費が発生します。
母と子のいずれの相続でもメリット・デメリットがある
亡父名義の家を相続する際には、母子のいずれでもメリット・デメリットがあります。また、ご家庭の納税資金計画などによっても、誰が相続するべきか慎重に検討する必要があります。
特に二次相続は一次相続よりも高い相続税が課税されやすいため、家の相続を一次相続の際にどうするか慎重に検討する必要があるでしょう。
親名義の家を相続する際の節税ポイント

親が所有していた家を相続する際、相続税は多くの方が気になるポイントでしょう。
しかし、重要な節税ポイントを押さえておくことで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。そこで、この章では親名義の家を相続する際に活用できる主な節税ポイントを解説します。
小規模宅地等の特例の活用
被相続人(亡くなった親)が居住していた宅地等(自宅の土地)を、一定の要件を満たす相続人が相続した場合、小規模宅地等の特例が適用できれば330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。なお、特例の適用で相続税が0円になった場合でも申告は必要です。
- 適用要件
同居していた親族が相続する場合は比較的要件が緩やかですが、別居していた親族が相続する場合は「家なき子」の要件など、厳しい条件を満たす必要があります。 - 遺産分割協議
特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに誰がどの土地を相続するかが確定している必要があります。遺産分割協議をスムーズに進めることが重要です。
配偶者の税額軽減
亡くなった親の家を配偶者が相続する場合、相続税の計算において「配偶者の税額軽減」という特例を利用できます。
これにより、配偶者が相続した財産のうち、1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までは相続税が課税されません。
なお、本特例の適用で相続税が0円になった場合でも申告は必要です。
債務控除の活用
親に借金(住宅ローンなど)や未払いの医療費、税金などがある場合、これらの債務は相続財産から債務控除できます。関連する書類をしっかりと保管し、漏れなく計上しましょう。
相続税評価額の適正化
不動産の評価額は先に触れたように土地の形状や立地条件によって評価額を減額できる場合があります。
税理士へ相談し、適正な評価額を算出してもらうことも検討しましょう。
相次相続控除の検討(二次相続の場合)
今回の相続が、過去10年以内に発生した親の相続(一次相続)によるものであれば、「相次相続控除」の適用によって一定額を控除できる利用可能性があります。
この控除は二次相続時に適用することも多いため、相続税申告時に覚えておくべき控除でしょう。なお、相次相続控除の適用で相続税が0円になった場合は申告不要です。
親名義の家が債務超過の場合はどうする?

もし、亡くなった親名義の家に住宅ローンなどの債務が残っており、その債務額が家の評価額を上回る「債務超過」の状態である場合はどうすればよいでしょうか。
あまりに高額の債務がある場合は「相続放棄」を検討する必要があります。相続放棄をすることで、家を含む一切の財産を相続しない代わりに、借金などの債務も引き継ぐ必要がなくなります。相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
限定承認を選ぶケースもある
親名義の家を引き続き住まいとして残したい場合は、「限定承認」という方法を選ぶケースも考えられます。
限定承認は手続きが相続放棄よりも複雑で、相続人全員の合意も必要です。相続放棄と同じく「相続の開始を知った日から3か月以内」申立てを家庭裁判所へ行う必要があります。
限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務(借金など)を引き継ぐ方法です。相続財産の中にどうしても残したい家などの財産がある場合に、その財産の価値と借金の額を比較しながら、相続するかどうかを判断することができます。
まとめ
この記事では、親名義の家を相続する際の節税ポイントについて、相続時の注意点なども交えながら詳しく解説しました。
親名義の家を誰が相続するべきかは、相続人のご状況(年齢、収入、同居の有無など)や将来のライフプラン、そして相続税の負担などを総合的に考慮して判断する必要があります。
また、不動産評価は複雑であり専門知識が不可欠です。ご自身だけで判断せずに、早めに相続に詳しい税理士へご相談ください。
横浜市の響き税理士法人では、相続税に関するご相談を広く受付しています。まずはお気軽にお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。