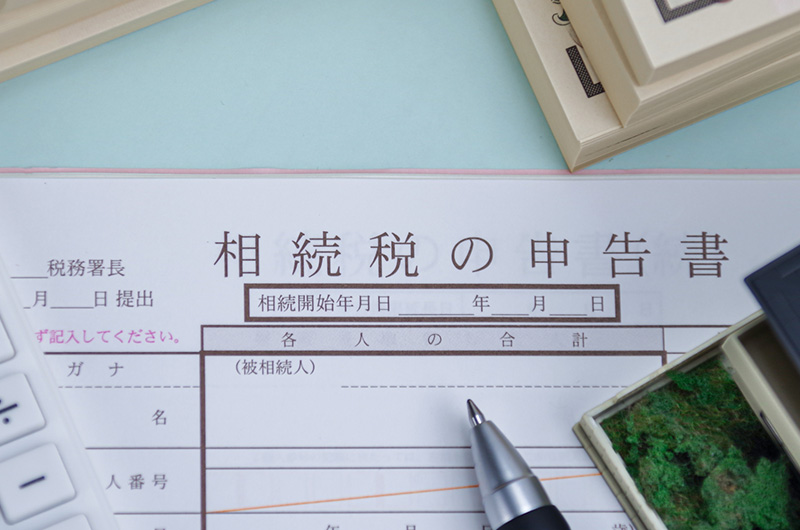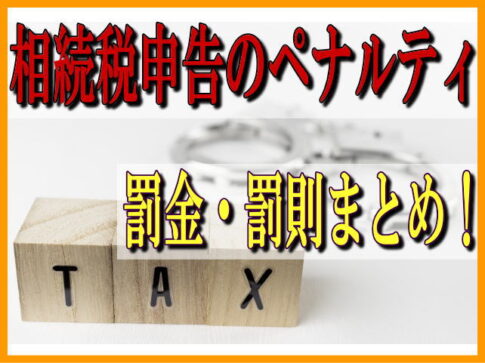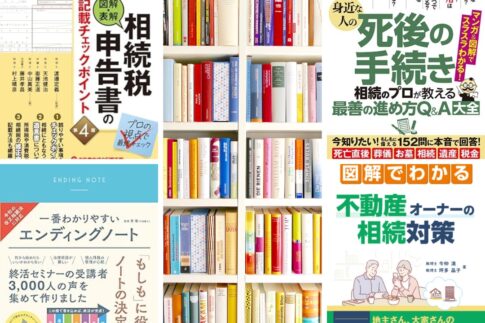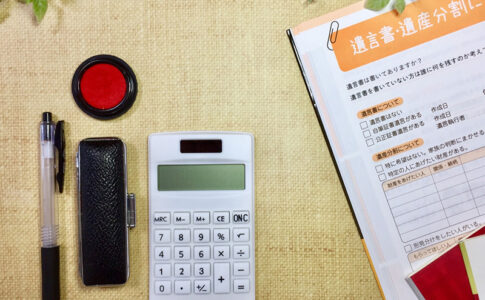相続税には納付期限が設けられており「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。相続税が発生している場合、ご家族が亡くなられてから10か月以内には納税を行う必要があるのです。
相続税には「時効」が設けられていますが、バレずに逃げ切ることはできるのでしょうか。相続税の期限には7年、5年という2つの時効があります。そこで、本記事では相続税の時効についてわかりやすく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税の時効は5年|除斥期間とは

日本国内には相続税をはじめ、さまざまな種類の国税があります。国税には一定期間を過ぎると、国側が納税者に課税する権利を失う「時効」が設けられています。一定期間については「除斥期間」と呼びます。では、相続税の時効と除斥期間とはどのように設定されているのでしょうか。
相続税の時効は「原則5年」
相続税の時効は、相続税申告・納付の期限である10か月(法定申告期限)から、除斥期間である「5年」を経過すると時効を迎えます。(国税通則法第70条1項)
被相続人の死亡日当日に、死亡の事実を知った場合は死亡日から「5年10か月」を過ぎると、相続税の時効が成立することになります。
では、5年間相続税の支払いをしなければ、相続税を支払わなくてもよいのでしょうか。
悪意がある場合の時効は「7年」
不正な行為など、悪意がある相続税逃れについては時効は除斥期間が「7年」とされています(国税通則法第70条5項)
このケースの場合、被相続人の死亡日当日に、死亡の事実を知った場合は死亡日から「7年10か月」を過ぎると相続税の時効が成立することになります。
たとえば、故意に被相続人の遺産を隠していたり、相続税申告書を改ざんして嘘の報告を行っていた場合などのケースでは、5年ではなく7年へ時効が延長されます。
時効を待てば相続税はバレずに逃げ切れる?

相続税の時効は5年、悪意がある場合は7年の時効が設定されています。相続税は必ずしも課税されるものではありませんが、対象となる方の中には高額の納税を行う必要があります。
相続税は原則として「現金」で納める必要があり、支払いに頭を抱える方も少なくありません。では時効を待っていれば、税務署にバレずに逃げ切れるのでしょうか
相続税を逃げ切ることは不可能
結論から言うと、相続税の支払いから逃げ切ることは不可能です。
相続税については税務署が厳しく調査を行っており、もしも申告が行われなかったり、申告の内容に疑問がある場合は「税務調査」を行うためです。最大7年間、知らないふりをしていれば時効を迎えられる、とは誤解しないように注意しましょう。
税務署が行う相続税の調査方法とは

税務署はさまざまな方法を駆使して、相続税調査を行っています。主な調査方法は以下です。
KSKシステムの利用
KSKシステムとは「国税総合管理システム」のことを意味します。本システムは全国の国税局・税務署をネットワークで結んでいるもので、税金の申告漏れ・滞納・脱税などを調査する目的で運用されています。システムの概要は以下です。
国税総合管理システム(以下「KSKシステム」という。)は、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステムである。
死亡届の提出を受けた市区町村役場は、死亡届を受理した日の翌月末までに税務署に対して死亡情報を提供する義務があります。つまり、相続の開始を税務署は必ず把握できるのです。
税務署は被相続人について収入や過去の資産状況などをKSKシステムを用いて徹底的に調査します。
相続税逃れは厳禁!バレた場合のペナルティとは

税務署は相続税の申告・納税について厳しく調査を行っています。では、相続税逃れを故意に行ったことが、税務署の調査の結果判明した場合には、どのようなペナルティが待っているのでしょうか。
延滞税
相続税が定められた期限までに納付されなかったら、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」が課せられます。つまり、納付遅れへのペナルティです。
| 延滞税が課される3つのケース ①申告等で確定した税額を法定納期限までに完納しない場合 ②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額がある場合 ③更正又は決定の処分を受け、納付しなければならない税額がある場合 |
延滞税の税率とは
延滞税には2つの種類の税率が用意されています。
①納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで…7.3%(または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合)
②納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後…14.6%(または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合)
なお、延滞税は変動しており最新の令和7年1月1日~同年12月31日の場合は、①について2.4%、②については8.7%と公表されています。
その他の期間については下記リンクをご参照ください。
参考URL 国税庁 延滞税の割合
無申告加算税
申告期限内に申告をしなかった場合は「無申告加算税」が本来納付すべき税額に対して課せられます。
| 無申告加算税が課される2つのケース ①期限後申告を行った場合 ②決定の処分を受け、納付しなければならない税額がある場合 |
無申告加算税は仮に期限後申告であっても、正当な理由があり、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告が行われている等のケースでは課税されません。ただし、遺産分割協議の遅れなどは対象になりませんのでご注意ください。
無申告加算税の税率
無申告加算税の税率は以下です。(令和6年1月1日以降対象分)
| 相続税額 | 税務調査の事前通知を受け取る前に、自主的に申告 | 税務調査の事前通知を受け取った後、税務調査前に申告 | 税務調査後に申告 |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円以上300万以下の部分 | 5% | 15% | 20% |
| 300万以上 | 5% | 25% | 30% |
重加算税
重加算税は、相続税のペナルティの中でもっとも重く、相続税逃れを目的に申告を行わなかった場合等に罰金として課せられる税金です。
| 重加算税が課せられる5つのケース ①相続人又は相続人から遺産の調査、申告等を任せられた人が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしている場合 ②相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮している場合 ③相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせている場合 ④相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得る場合 ⑤相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこともしくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告している場合 |
重加算税の税率
- 無申告による重加算税については、原則40%
- 過少申告による重加算税については原則35%
以上が重加算税の税率です。加えて、延滞税にも注意する必要があります。重加算税については延滞税が加算されます。
過少申告加算税
相続税申告を期限内に行っていても、過少に申告した場合には「過少申告加算税」が課せられます。
| 過少申告加算税が課せられる2つのケース ①税務署の調査を受けた後で修正申告を行う場合 ②税務署から申告税額の更正を受けた場合 |
過少申告加算税の税率
過少申告加算税の税率は以下です。
| 追加で納める税額 のうち | 税務調査の事前通知を受け取る前に、自主的に申告 | 税務調査の事前通知を受け取った後、税務調査前に修正申告 | 税務調査後に申告 |
|---|---|---|---|
| 当初の納税額 もしくは50万円のいずれか多い方で以下の部分 | なし | 5% | 10% |
| 当初の納税額 もしくは50万円のいずれか多い方を超える部分 | なし | 10% | 15% |
相続税逃れはバレる!期限内に確実な申告・納付を行おう

相続税については税務署が徹底的に調査を行っており、数年後に突然税務調査の事前通知を受けるケースも少なくありません。重加算税が課せられてしまうと非常に重い納税額となるだけではなく、悪質かつ高額の脱税には刑事罰が科せられる可能性もあります。
時効があるから…と相続税逃れをすることは大変危険です。
相続税は時に高額となる場合がありますが、控除や特例の利用で大きく節税できるケースも少なくありません。悪質な行為に手を染めるのではなく、まずは相続税の専門家である税理士へご相談の上で、期限内に確実な申告・納付を行いましょう。
まとめ
本記事では相続税の時効について、課せられるおそれがあるペナルティにも触れながら詳しく解説を行いました。相続税はバレずに逃げ切るのではなく、節税対策で臨むことが大切です。
横浜市の響き税理士法人では、相続税の専門家である税理士が適切なアドバイスを行い、申告・納税をサポートしています。いつでもお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。