
家族が亡くなり遺産分割協議を行ったら、協議で決めた内容について「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は預貯金口座の解約などの際に必要な書類ですが、作成時には「どこでもらえる」のでしょうか。
そこで本記事では遺産分割協議書について、もらえるのか詳しく解説します。作成方法や提出先についても解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
産分割協議書とは|どこでもらえる?
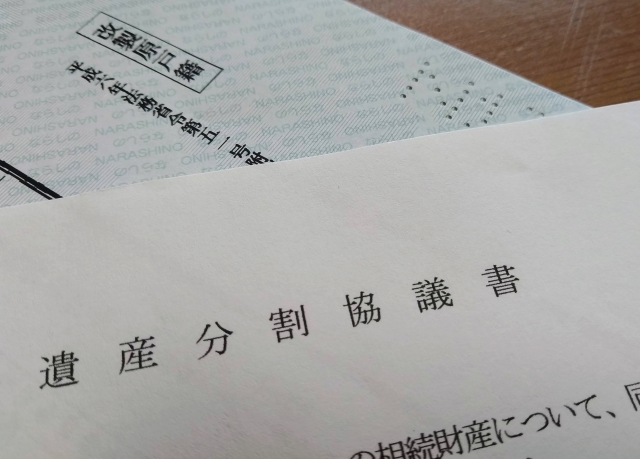
遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を記載した書面を意味します。
実は、遺産分割協議書には「法律で定められた書式」はありません。手書き、パソコンのどちらで作成しても問題はなく、作成期限も定められていません。
記載する内容は被相続人の情報、相続人に関する情報、具体的な遺産名などです。では、遺産分割協議書が欲しい場合にはどこでもらえるのでしょうか。
遺産分割協議書はテンプレートがもらえる
遺産分割協議書は、合意した内容を記載するため基本的には「自分で作成」します。
書式が欲しい場合には、ネット上で公開されているテンプレートをダウンロードして加工すれば、手軽にご自身に合った遺産分割協議書が作れます。
ただし、テンプレートにもさまざまな種類があります。たくさんネット上に公開されており、どれを使えばよいのかわからない場合は、国税庁や法務局が公開している遺産分割協議書例をお手本にすることもおすすめです。
国税庁 相続税の申告のしかた(令和6年分用)相続税の申告書の記載例 等P125(縦書き)
法務局 【相続登記ガイドブック】1-4-11 遺産分割協議書の例 (横書き)
遺産分割協議書作成に不安を感じたらどうする?
遺産分割協議書は被相続人の財産状況や、相続人名などを記載するため、公開されているテンプレートをそのまま活用するのではなく、ご自身に合わせて加工する必要があります。
作成に不安がある場合は、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することがおすすめです。税理士はもちろん、弁護士・司法書士・行政書士などにもご相談いただけます。
遺産分割協議書を作成したらどこに提出する?

遺産分割協議書は作成後、さまざまな相続手続きに活用します。では、具体的にはどのような場所へ提出するのでしょうか。この章ではよくある提出先を5つに分けて紹介します。
金融機関(銀行・信用金庫など)
被相続人に預貯金口座があった場合、解約や名義の引継ぎを行う必要があります。遺産分割協議時に誰が相続するのか決め、遺産分割協議書に記した上で、各金融機関に相続手続きを依頼します。
この時、金融機関側から遺産分割協議書を提出しています。その他、金融機関側が求める書類を添えて手続きを進めます。
証券会社や非上場株式の発行会社
被相続人が保有する上場株式がある場合は証券会社へ、非上場株式の保有がある場合は発行した会社へと相続手続きを依頼します。この時も、金融機関と同様に遺産分割協議書の提出が必要です。
相続登記(法務局)
被相続人に不動産(土地・建物)の保有があり、相続する場合には相続登記を行う必要があります。相続登記とは新しい所有者へ、被相続人の名義から名義変更を行う手続きです。法務局で手続きを進める際に、遺産分割協議書が必要です。
相続税申告(税務署)
被相続人の遺産に対して相続税が発生した場合は、税務署に相続税申告を行う必要があります。相続税申告時にも遺産分割協議書が欠かせません。
その他
この他に、被相続人の自動車の名義変更や著作権などの権利を引き継ぐ手続きの際にも、遺産分割協議書は必要です。
遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議は先に触れたように、法的な形式が提供されているものではないため、公開されている書式を使って自分で作成したり、専門家に作成してもらうことになります。では、遺産分割協議書を実際に作成する方法はどのようなものでしょうか。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成します。作成方法は以下の5つのステップを経て行います。
遺産分割協議書に参加してもらうために、まずは相続人が誰なのか詳しく調査を行います。被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を整え、相続人漏れがないように注意しましょう。
また、誰がどの財産を相続するのか決めるために、被相続人が遺した遺産を調査します。預貯金、不動産や株式はもちろん、債務も相続対象となるため漏れなく調査を行いましょう。
遺産分割協議を行い、相続人全員が合意できたら、最後に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書作成には知っておきたい注意点もあります。主に以下の4つです。
1.相続人全員の参加が必要
繰り返しですが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、遺産分割協議書に相続人の記載漏れがあると無効となってしまいます。
ただし、家庭裁判所で相続放棄をした相続人がいる場合は、記載は不要です。相続放棄申述受理証明書を提出する必要がある相続手続きもあるため、放棄をした方から受け取るようにしましょう。
2. 遺産分割協議に期限はないが、その他の手続きに期限がある
遺産分割協議書や、遺産分割協議書の作成に法的な期限はないものの、相続登記や相続税申告など、その他の手続きには期限が設けられています。
ゆっくり協議を進めていると、その他の手続きに影響を及ぼす可能性があるため、できる限り早く終えておくことが重要です。
期限に関しては以下記事をご参考ください。
3. 法定相続分どおりに相続する場合、遺産分割協議書は不要
相続人が1名であり、遺産をすべて相続する場合や、複数の相続人が居ても「法定相続分」どおりに相続する場合には、遺産分割協議書を作る必要はありません。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続の配分のことです。遺産分割協議では必ずしも法定相続分に沿って相続する必要はありません。
ただし、トラブルになりそうな場合や相続する遺産が少ない場合は、法定相続分どおりの相続でスムーズに協議を終えることも考えられます。
| 配偶者と子供が法定相続人である場合 | 配偶者1/2 |
| 子供の1/2(子供が複数いる場合、子供の数に応じて1/2を均等に分配) | |
| 配偶者と親(直系尊属)が法定相続人の場合(子がいない場合) | 配偶者2/3 |
| 父母(直系尊属)1/3(複数の場合は、相続人の数に応じて1/3を均等に分配する) | |
| 配偶者、兄弟姉妹が法定相続人の場合(直系卑属がいない場合) | 配偶者3/4 |
| 兄弟姉妹1/4(複数の場合は、相続人の数に応じて1/4を均等配分) |
詳しくは以下の記事をご一読ください。
4.相続人ごとに作成しておくと便利
遺産分割協議書については書式だけではなく、作成枚数にも法的な制限はありません。遺産分割の合意内容について、その後記載内容がわからなくなるなどのトラブルを避けるためにも、相続人分を作成しそれぞれが保管することがおすすめです。
また、提出先でご紹介のとおり、多くの相続の手続きで遺産分割協議書を提出するため、複数の原本があると迅速に手続きが進みます。
遺産分割協議書の原本は戻ってこない?

金融機関や法務局に遺産分割協議書を提出する際には、原則として「原本」を提出する必要があります。ただし、すべての相続手続きで遺産分割協議書の原本を提出してしまうと、お手元に大切な原本が残らなくなってしまいます。では、原本を返してもらう方法はあるのでしょうか。
遺産分割協議書提出後に原本は返してもらえる
遺産分割協議書を提出する場合、原本を返却してもらう方法があります。
上記の場合、原本とセットで提出すると、法務局側で原本とコピーを比較し、間違いなく提出されたコピーが原本と相違ないとわかったら、原本を返却してもらえます。金融機関などでも原本還付を認めていますので、提出時に確認することがおすすめです。
まとめ
本記事では遺産分割協議書がもらえるか否か、ダウンロード先や作成時の注意点にも触れながら詳しく解説しました。遺産分割協議書の作成には、法律で定められた書式はないため、自由に作成できます。ただし、記載しておかなければ無効となる事項も多く、法務局などが公開しているサンプルを活用して作成することもおすすめです。ダウンロードで記載例をもらえます。
もしも作成に困ったら、税理士をはじめとする専門家にも相談できます。
横浜市の響き税理士法人では、相続税にまつわるお悩みはもちろん、遺産分割協議書の作成やアドバイスも行っています。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

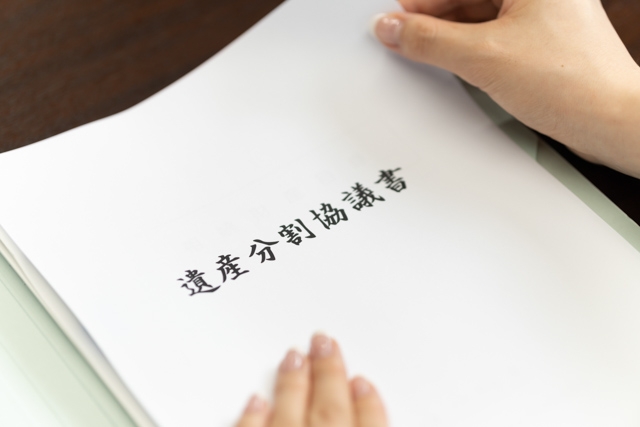

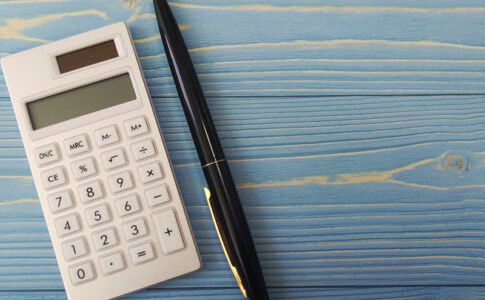
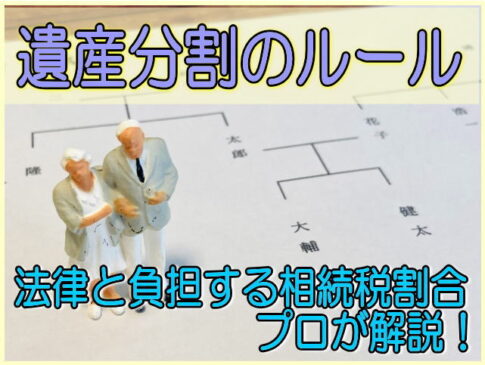







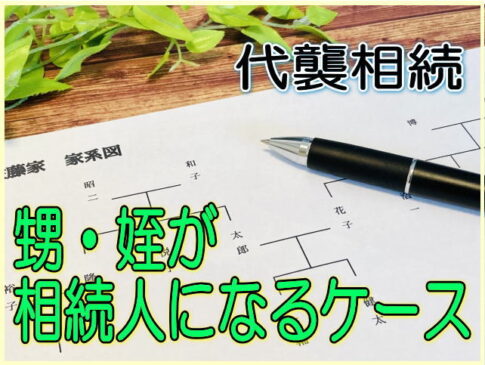
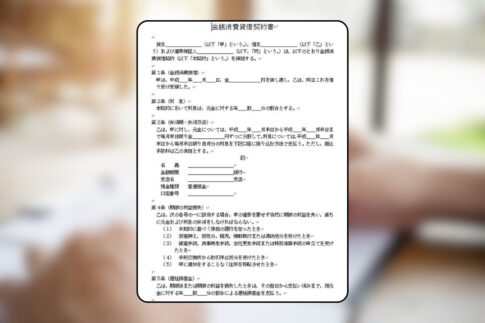









②遺産(相続財産)の調査と確定
③遺産分割協議の開始
④遺産分割協議への合意
⑤遺産分割協議書の作成