

父親が亡くなった後に、さらに母親も亡くなり相続が続いてしまうことを「二次相続」と言います。
高齢化が進んでいる日本では、両親が立て続けに亡くなるケースは決して少なくありません。このような相続は最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」と呼び、二次相続では重い相続税に直面する可能性があるため、注意が必要です。
そこで本記事では二次相続の視点から、一次相続時に対策が必要な理由や、二次相続における注意点をわかりやすく解説します。ぜひご一読ください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
二次相続とは|一次相続とはどう異なる?

二次相続とは、1回目の相続で相続人となった配偶者が亡くなることで発生する2回目の相続を意味します。
例として、両親と子1名のご家庭があるとします。1回目の一次相続で父親が亡くなった時、相続人は配偶者である母と子1名です。次に、2回目の二次相続で母が亡くなった時、相続人は子1名です。この章では一次相続との違いをわかりやすく解説します。
一次相続とはどう異なる?
①一次相続
一次相続では、両親のいずれかが存命です。たとえば、父が亡くなった母と子1名の家庭では2名が相続人となるため、基礎控除は以下となります。
- 基礎控除 3,000万円+(600万円×2)=4,600万円
また、相続税計算時には母が存命のため、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)も適用できます。
②二次相続
二次相続では上記を例にすると、母が亡くなり子1名が相続することになります。
両親が残した遺産をすべて子が相続する上、相続人が減るため基礎控除額も以下のとおり減少します。また、配偶者控除も使えません。
- 基礎控除 3,000万円+(600万円×1)=3,600万円
二次相続は「相続税」が増えてしまう
一次相続と異なり、二次相続では基礎控除額も減り、配偶者控除も使えないため「相続税」が増えてしまうおそれがあります。
特に配偶者控除は大きな控除枠のため、適用できない二次相続では納税額に頭を抱える人は多いのです。
■配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは、以下2点の条件でいずれかに該当すれば優遇措置が受けられる相続税の控除です。
①配偶者が法定相続割合で取得した相続財産か
②1億6千万円までで取得した相続財産か
一次相続時は配偶者が存命のため要件をクリアしていると適用でき、相続税は少なくなります。しかし、二次相続ではすでに両親が他界しているため適用できません。
小規模宅地等の特例も使えない場合がある
相続税に用意されている特例の1つに「小規模宅地等の特例」があります。この特例は一定の要件を満たすことで、相続財産に含まれる「土地」の相続税評価額について、最大80%減額できるものです。
一次相続時に本特例を適用できた人でも、二次相続時に同様に適用できるとは限りません。被相続人と生前に同居していた等、さまざまな要件をクリアする必要があります。
参考URL 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
一次相続時から二次相続を見据えた対策が必要

二次相続時は相続税が高くなりやすいため、子が重い相続税の支払いに悩まされるおそれがあります。
そこで、相続税の節税を目指すためにも一次相続時から、二次相続を見据えた対策が必要です。この章では考えられる対策方法について、わかりやすく解説します。
生前贈与を活用する
一次相続が起きた後に、親から子や孫へ「生前贈与」を進めていくことで、親が所有している財産を減らせるため、相続税対策につながります。
一般的に広く活用されている「暦年贈与」は、毎年110万円までなら贈与税が課税されません。暦年贈与は贈与される1人あたりにつき、110万円の限度額としてるため、子が2名いる場合は毎年それぞれに110万円(合計220万円)まで贈与できることになります。
ただし、2024年1月1日以降は民法改正により「死亡前7年以内の贈与額(110万円以下の贈与財産も含む)」を相続財産に加算しなければいけなくなりました。相続税における生前贈与の加算の対象が、従前の3年以内から7年以内へと段階的に延びていくため注意が必要です。
生前贈与は以前よりも二次相続対策には使いにくくなっています。そこで、次の対策方法も検討もおすすめです。
生命保険を活用する
生命保険も二次相続対策として有効です。以下2つのポイントで解説します。
まず、1つ目は相続時に生命保険から支払われる死亡保険人については、課税限度額がある点です。
一次相続で相続財産を取得した配偶者が、自分自身を「契約者」かつ「被保険者」に、子どもを「保険金受取人」に指定した生命保険に加入すると仮定します。
被相続人の死亡時、子どもが受け取った死亡保険金は相続税の対象ではありますが、死亡保険金の非課税限度額(500万円×相続人の数)が適用されるため、相続税を減額することができます。
たとえば、二次相続で子1名が死亡保険金を受け取った場合、500万の非課税限度枠を活用できます。
2つ目は死亡保険金は相続税などに利用できる点です。
被相続人の相続財産に不動産が多い場合、相続人は相続税の納付に苦戦することがあります。相続税の納付は原則として現金で納付するためです。
生命保険の死亡保険金は保険会社に所定の手続きを終えると、速やかに現金で支払われるため相続税の納税に使うこともできます。
また、不動産の売却などよりも早く手に入るため、葬祭費用や遺品整理の支払いに利用することも可能です。
配偶者居住権を利用する
「配偶者居住権」とは2020年4月から始まっている新しい制度です。被相続人が遺した自宅の「建物」に発生する権利を、「所有権」と「居住権」の2つへ分離させられるようになりました。配偶者が居住権のみ相続することで、自宅を丸ごと相続しなくても居住を続けられます。
配偶者居住権は配偶者が亡くなるまで権利を主張できます。(もしくは一定の期間も可能)
家族を含めた第三者に譲ったり、売ったりすることはできませんが、小規模宅地等の特例との併用もできます。また、2つに権利を分離することによって所有権を相続する側の相続税額も安くなります。
では、固定資産税はどうなるでしょうか。
「配偶者居住権」を配偶者が相続し、「所有権」を子が相続した場合は一般的に固定資産税の納税通知書は子へ通知されます。
一次相続時に税理士へ相談し、相続財産の割合額を調整する
一次相続では配偶者控除が使えるため、一般的には配偶者が多くの相続財産を相続します。しかし、二次相続も見据えると注意が必要です。特に高齢の配偶者が取得する場合は二次相続を見据えて対策を行う必要があります。
あえて一次相続時に子への分配を多くすることで、二次相続における相続税を節税することも検討できるでしょう。このようなケースでは、税理士に相談し二次相続もシミュレーションを行うことが大切です。
一次相続時から二次相続をシミュレーションしてみよう!

この章では、実際に一次相続の段階から二次相続をシミュレーションし相続税対策を行った事例を紹介します。
【事例】遺産総額1億円のケース
【一次相続】
妻:100% 子:0%
相続税…妻0円(配偶者の税額軽減の利用)子:0円
【二次相続】
子:100%
相続税…子:1220万円 ≪相続税額合計≫1220万円
【一次相続】
妻:50% 子:50%
相続税…385万円
【二次相続】
子:100%
相続税…子:160万円 ≪相続税額合計≫545万円
上記では、一次相続の段階から子へ相続財産を分配し、二次相続の対策を行ったことで、ご家族全体で支払う相続税の合計額が600万以上異なることがわかります。相続税のシミュレーションはとても大切なのです。
相次相続控除も知っておこう

相続税の計算では、様々な特例や控除を理解することが節税の鍵となります。
その中でも、短期間に相続が繰り返された場合に適用される「相次相続控除」は、知っておくと有利な制度です。これらの制度は、立て続けに相続が発生した場合の相続税負担を軽減するために設けられています。詳しくは以下のとおりです。
相次相続控除とは
相次相続とは、一次相続時に相続税を納付した後、二次相続が発生するまでの期間が10年以内に起きることを意味します。(遺贈等含む)
相次相続には次の要件を満たしていることで「相次相続控除」を受けられます。
- 二次相続の相続人であること
- 一次相続から二次相続発生まで10年以内であること
- 一次相続で発生した相続税をきちんと納税している
相次相続控除ができる額は、前回の相続において課税された相続税額の内、1年につき10%の割合で減額した後の金額を、二次相続の相続税額から控除します。
数次相続でも利用できる
数次相続とは、一次相続が発生して遺産分割協等が終了していないにもかかわらず、10年以内に新たな相続が発生することを指します。
数次相続時にも相次相続控除が適用できるため、漏れなく計算する必要があります。
まとめ
本記事では一次相続時にこそ、二次相続を見据えて対策を行う重要性について詳しく解説しました。高齢化が進んでいる日本では、一次相続時にしっかりと二次相続対策を行うことが大切です。将来のためにも、一次相続時から税理士へ相談しましょう。
横浜市を中心に多くの相続税申告に対応している響き税理士法人では、様々な相続税相談に対応してきた経験があります。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。













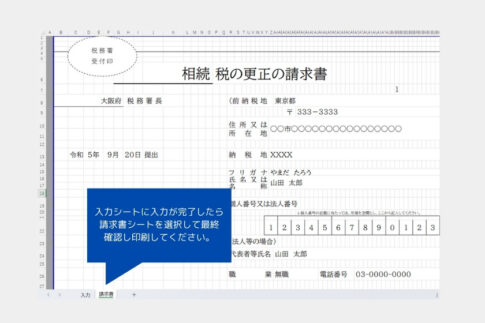








遺産の総額:1億円
一次相続の被相続人:夫、相続人:妻、子ども1人 合計2人
二次相続の被相続人:妻、相続人:子ども1人 合計1人