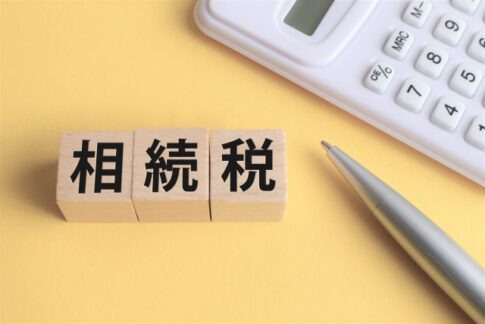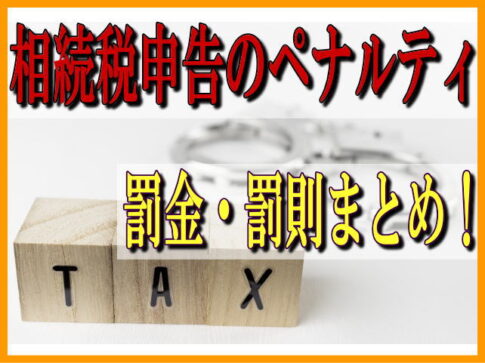小規模宅地の特例とは、被相続人(亡くなった人)が居住用や事業用として使っていた宅地を相続する場合に、一定の要件を満たせば、宅地の評価額を最大80%減額できるという特例です。
相続税は、被相続人の財産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に発生します。特に、自宅や事業用の土地は財産の中でも大きな割合を占めることが多く、土地の評価額が高額になることで、相続税が高額になるケースは少なくありません。
本特例は相続税を抑える効果がありますが、細かい要件があるだけでなく、平成30年(2018年」に法改正もあったため注意が必要です。そこで、本記事では小規模宅地の特例について、最新の「家なき子特例」の適用要件や悩みの種になりやすい改正後についての注意点を中心に詳しく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
小規模宅地の特例とは|平成30年の改正点や最新の適用要件とは

被相続人が自宅や事業用の宅地などを所有していた場合、相続税の対象となります。これらの不動産は残されたご家族にも欠かせない財産ですが、時に高額の相続税を招く可能性もあります。
そこで、ご家族が今後も安定して財産を所有できるように「小規模宅地の特例」が用意されています。本章ではこの特例の概要や平成30年に行われた改正のポイント、最新の適用要件を詳しく解説します。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、被相続人(亡くなった方)が居住用や事業用として使っていた宅地を相続した場合に、一定の要件を満たせば、宅地の相続税評価額を大幅に減額できるという制度です。
この特例の目的は、相続人が生活の基盤となる自宅や、生計を立てるための事業を継続できるように、相続税の負担を軽減することを目的としています。
減額される割合は土地の種類によって異なりますが、最大で80%も土地の評価額を減額できます。
参考URL 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
平成30年(2018年)の改正点
平成30年度の税制改正では、小規模宅地の特例について、適用要件が厳格化されましたが、特例自体が廃止されたわけではありません。特に大きな改正点は以下の2つです。
- 家なき子特例の見直し
「家なき子特例」とは、被相続人と同居していなかった親族(持ち家がないなどの要件を満たす者)が宅地を相続する場合に特例を適用できる制度でした。改正後は、特例の適用要件が厳格化され、適用できる人が限定されました。詳しくは後述します。
平成26年(2014年)の改正は相続人に有利な変更
平成26年にも小規模宅地等の特例の改正が適用されていますが、この時は二世帯住宅に関して適用の緩和が行われました。
区分所有登記がなされていない「完全分離型」の二世帯住宅であっても、特例が適用できるように変更されています。
つまり、建物内で家族が往来できないような二世帯住宅でも1つの所有権登記がなされていれば、同居とみなして本特例が適用できます。
小規模宅地等の最新適用要件とは

では、小規模宅地等の特例はの最新適用要件とはどのようなものでしょうか。
小規模宅地の特例は相続税法上の課税の特例で、その効果と適用要件は次のとおりです。
2025年現在の最新適用要件
| 効果 | 宅地(330平米まで)に対する相続税の課税対象額が80%削減される |
|---|---|
| 適用要件 |
|
「その他、ケースごとに必要な要件を満たすこと」とありますが、宅地を取得したのが被相続人の配偶者であれば無条件で小規模宅地の特例の適用を受けることが可能です。
しかし、宅地を取得したのが次のいずれかに該当する場合は注意が必要です。
- 被相続人が居住していた家屋の宅地を被相続人と同居していた親族が取得した場合の、その親族
- 被相続人と同一生計の親族が居住していた家屋の宅地を当該同一生計の親族が取得した場合の、その親族
上記の場合、①と②の両方を満たす必要があります。
①その宅地を取得した親族が相続開始の直前から相続税の申告期限まで継続してその家屋に居住したこと(継続居住要件)
②取得した親族が相続税の申告期限まで継続してその宅地を所有したこと(継続所有要件)の両方を満たす必要があります。
家なき子特例とは

平成30年改正後の小規模宅地等の特例では、いわゆる「家なき子特例」について厳格化されました。家なき子特例は、「被相続人と別居していた親族」が、小規模宅地等の特例を受ける際の要件を意味します。
先に触れたように、小規模宅地等の特例には「同居の要件」が設定されています。しかし、別居していたとしても、次の6要件をすべて満たすことで小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
① 取得した宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること
② 「居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者」に該当しないこと
③ 相続開始時に取得者が居住している家屋につき、これを相続開始前のいずれの時においても所有していないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者が主要な株主である一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
⑤ 被相続人に配偶者がいないこと
⑥ 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと
④の要件が、「相続の3年前から現在まで自己所有の家屋を持っていない」というものであり、この点をもって「家なき子特例」と呼ばれるようになりました。
④の要件が、「相続の3年前から現在まで自己所有の家屋を持っていない」というものであり、「家なき子特例」と呼ばれるようになりました。
家なき子特例はなぜ設けられている?

家なき子特例は、配偶者に先立たれた親が死亡した後、その親が居住していた空き家と宅地を相続人である子が取得して、住み続けることを想定しています。
相続発生時には別の場所に賃貸契約で暮らしおり、いずれ実家に帰ろうと考えている子が、高額の相続税を支払えずに実家を手放さざるを得ないケースがあります。
家なき子特例は実家を守るための効果があるのです。しかし、法の隙間を突いたグレーな適用事例も見受けられたため、法改正により厳格化されました。
平成30年度税制改正による厳格化
改正による変更点は、以下をご確認ください。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| ① | 取得した宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること | 同左 |
| ② | 「居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者」に該当しないこと | 同左 |
| ③ | - | 相続開始時に取得者が居住している家屋につき、これを相続開始前のいずれの時においても所有していないこと |
| ④ | 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと | 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者が主要な株主である一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと |
| ⑤ | 被相続人に配偶者がいないこと | 同左 |
| ⑥ | 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと | 同左 |
家なき子特例は確かに要件は厳しくなったものの、廃止ではないため適切に要件を確認すれば、十分に利用できる特例です。しかし、法改正後は適用できなくなったと思っている方も多く、適用漏れも見受けられます。
相続人の年齢問わず、別居の子でも適用できるケースは多いため諦めずに判定することが大切です。
改正後に小規模宅地等の特例を適用できなくなったケース
改正によって、次のようなケースで小規模宅地の特例の適用を受けることができなくなりました。
- 自宅購入し、即座に親族とセールアンドリースバック契約を締結したケース(新設された要件③に抵触するため適用対象外)
- 自身が100%株主である法人に家屋を購入させ、社宅として自身が居住したケース(改正された要件④に抵触するため適用対象外)
家なき子特例を受ける際の必要書類とは
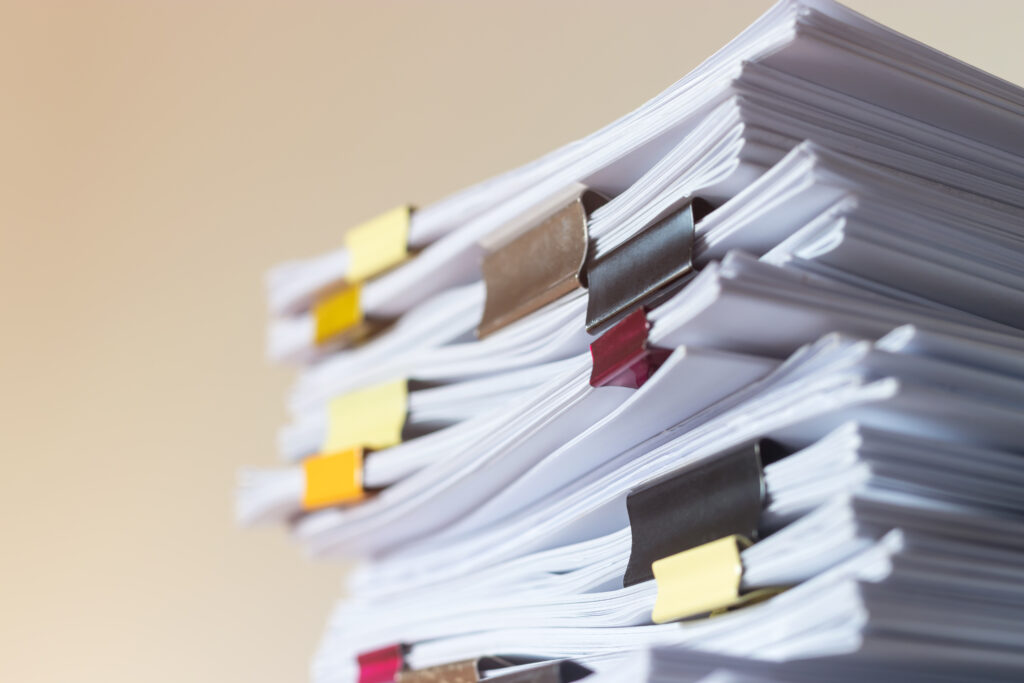
家なき子特例は、小規模宅地の特例の中でも特に要件が複雑なため、適用を受けるためには多くの書類を準備する必要があります。ここでは、特例を受ける際に共通して必要となる書類と、家なき子特例特有の必要書類にわけて解説します。
小規模宅地特例を受ける際に必要となる書類
家なき子特例も小規模宅地の特例の一種であるため、まずは共通して必要となる以下の書類を準備します。
・相続税申告書
小規模宅地等の特例を適用するためには、必ず相続税の申告書を提出する必要があります。申告書には、特例の適用を受ける旨を記載し、所定の計算を行います。
・遺産分割協議書
誰がどの財産を相続したかを明確にするため、相続人全員の合意内容を記した遺産分割協議書の写しが必要です。協議書には特例の対象となる宅地を取得する相続人を明記します。遺言書がある場合は遺言書の写しが必要です。
・戸籍謄本
被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍が必要です。法定相続人を確定するために使われます。相続人分も必要ですが、法定相続情報一覧図でも可能です。
・相続人全員の印鑑証明書
・住民票の写し(被相続人と相続人の関係によって細やかな変更あり)
・相続財産に関する残高証明書や、不動産の登記簿謄本など
・小規模宅地等の特例で、宅地の種類別にあわせた必要書類
この他にも書類が必要となるケースもあるため、事前に税理士に確認されることがおすすめです。特に生前、被相続人が老人ホーム等に入居されていた場合は、要介護の認定内容がわかる書類や被相続人の戸籍の附表などが必要となります。
次に、家なき子特例の場合は基本書類の他に、以下の書類が必要です。
家なき子特例で必要となる書類
・土地を相続する人の戸籍の附表
被相続人が亡くなる前3年以内に住んでいた場所を証明するために必要です。
・賃貸借契約書など
別居していた方が賃貸マンションなどに暮らしてた場合、持ち家に居住をしていないことを証明するために居住実態を証明する書類が必要です。
小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる非常に有利な制度ですが、適用を受けるためには多くの注意点があります。適用時のポイントを押さえていないと、特例が受けられず、高額な課税を受けるリスクがあるため、十分な理解が必要です。
相続税の申告は必須
この特例を適用すると相続財産が基礎控除以下になり、相続税計算の結果0円になるケースも少なくありません。
しかし、相続税が0円になる場合でも、必ず相続税の申告書を期限内に提出しなければなりません。申告が漏れると特例が適用されず、相続税が課税されてしまうため、注意が必要です。
遺産分割協議を期限までに完了させる
本特例を適用するには、誰がどの宅地を相続するかを明確にする必要があります。そのため、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了させなければなりません。
やむを得ず期限内に協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで一時的な猶予は可能ですが、手続きが複雑になります。
要件の自己判断は避ける
小規模宅地等の特例は、宅地の種類や相続人の状況、居住要件など、非常に細かく複雑な要件が定められています。少しでも要件に不備があると、特例の適用が否認される可能性があります。自己判断で手続きを進めることは非常に危険です。
特例の適用を検討する際は、相続税に詳しい税理士に相談することが不可欠です。専門家と連携することで適用要件を正確に判断し、適用不可のリスクも回避できます。
相続する土地を売却したら適用できない?

小規模宅地等の特例を適用するためには、原則として相続した土地を相続税の申告期限まで保有し続けなければなりません。 そのため、相続した土地を売却した時期によって、特例を適用できるかどうかが決まります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間内に売却してしまうと、保有継続要件を満たさないため、特例は適用できません。この章では知っておきたい小規模宅地等の特例の「保有継続要件」について解説します。
保有継続要件とは
保有継続要件とは、小規模宅地等の特例を適用するための重要な要件の一つです。相続人が特例の対象となる宅地を、相続開始から相続税の申告期限まで引き続き所有していることを指します。
この要件は、特例が「相続人の生活基盤や事業の継続を支援する」という制度趣旨に基づいているものです。もし申告期限前に売却してしまえば、制度本来の目的である「住まいや事業の継続」に反するとみなされます。
したがって、相続税の申告期限を過ぎてから売却するのであれば、保有継続要件は満たしていることになり、特例の適用は可能です。
保有継続要件が例外となるケース
保有継続要件には、以下のとおり例外的な扱いが認められる場合があります。
- 配偶者が相続する場合
被相続人の配偶者が居住用宅地を相続する場合は、保有継続要件や居住継続要件が免除されます。これは、配偶者が長年共に生活を築いてきた経緯から、相続人の中でも特に保護すべき対象とされているためです。
ただし、居住用宅地以外は対象外となるため注意が必要です。 - 相続税の申告期限後に引き渡す場合
相続税の申告期限内に売買契約を交わしたとしても、宅地の引き渡し日が申告期限後であれば、保有継続要件を満たすと判断されます。
ただし、譲渡所得税の確定申告において、契約日を基準として申告すると、保有継続要件を満たさないと判断される可能性もあるため、注意が必要です。
相続した土地の売却を検討している場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けるためにも、申告期限を考慮し、スケジュールを組むことが重要です。
小規模宅地等の特例が適用できなかったらどうする?

小規模宅地等の特例が適用できなかったとしても、相続税には他にもさまざまな特例や控除が設けられています。まずは、ご自身の状況で適用できる制度がないかを確認しましょう。
また、一次相続では小規模宅地等の特例が適用できても、次の二次相続では適用できなくなるケースもあります。相続時には次の二次相続にも備えて、対策を進めることが大切です。
その他に適用できる特例・控除
小規模宅地等の特例と基礎控除以外で、相続税額を軽減できる主な特例や控除は以下の通りです。
- 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税が課税されません。非常に非課税枠が大きい控除であるため、配偶者が相続人となる場合には、まずこの特例を検討します。
ただし、この特例は二次相続時の負担増につながるリスクがあるため、遺産を誰に・いくらわけるのか慎重にシミュレーションをしておくことがおすすめです。 - 未成年者控除
相続人が18歳未満の未成年者である場合、18歳になるまでの年数×10万円が相続税額から控除されます(令和4年3月31日以前の相続は20歳未満が対象)。 - 障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)が相続税額から控除されます。
この他に控除や特例がありますので、あきらめずに税理士へご相談ください。
二次相続時は適用できなくなるおそれがあるため注意
相続税の計算を進める際には、被相続人の配偶者が亡くなった際に発生する「二次相続」を考慮することが非常に重要です。一次相続(夫婦の一方が亡くなった時)で小規模宅地等の特例を適用できたとしても、二次相続では適用できず、税額が高くなるおそれがあります。
子どもが二次相続で親の自宅を相続する場合、親と同居していなければ、特例の適用要件は厳しくなります。特に別居して世帯を持っている子どもの場合、自身や配偶者の持ち家に暮らしていることは多く、家なき子特例の対象外です。
しかし、同居によって小規模宅地等の特例の要件はクリアしやすくなります。二次相続では両親をともに失い、子が相続するため一次相続で利用できた「配偶者の税額軽減」も適用できません。法定相続人が減り、基礎控除枠も減ってしまうため、小規模宅地等の特例も含めた相続税対策を検討しておくことがおすすめです。
まとめ
本記事では小規模宅地等の特例について、平成30年の改正や家なき子特例の変更点、適用を受ける際のポイントにも触れながら詳しく解説しました。
小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果がありますが、改正後には適用要件が厳しくなっているため慎重に確認する必要があります。
また、一次相続では適用できても、次の二次相続では適用できないおそれもあるため、あらかじめシミュレーションを行い相続税対策を進めることもおすすめです。
まずはお気軽に、横浜市の響き税理士法人へお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。