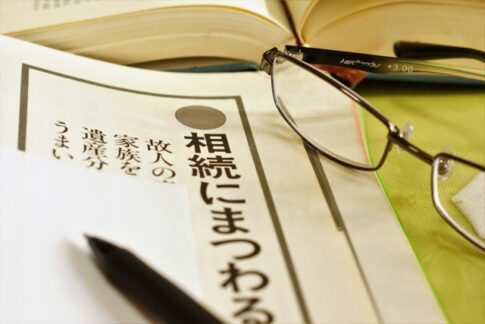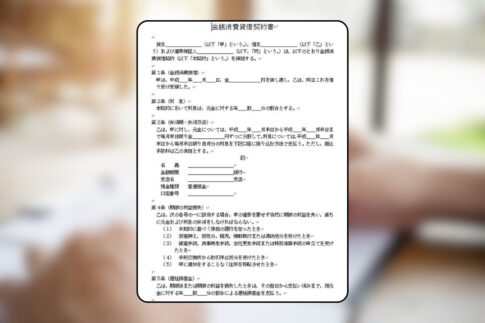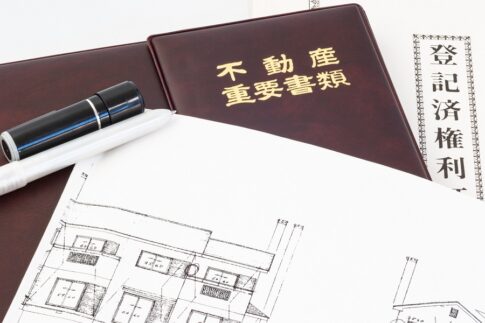生前に被相続人の介護に貢献したり、扶養にて生活を支えていた相続人は、被相続人の相続財産の取得時に「寄与分」を請求できます。しかし、寄与分請求や計算方法は難しく、請求時には貢献した内容がわかる資料も必要です。
そこで、本記事では相続時に知っておきたい「寄与分」について、制度の概要や請求・計算方法をわかりやすく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
知っておきたい相続時の「寄与分」とは

亡くなられた被相続人の生前に介護で尽くしたり、献身的に扶養を通して生活を支えていた、という相続人は多いでしょう。
このような行為は被相続人の財産の維持などに貢献しているため、遺産分割時に法定相続分を超える相続財産の取得を主張できます。この章では寄与分について、概要や請求方法をわかりやすく紹介します。
「寄与分」とは
「寄与分」とは生前に被相続人に「特別な貢献」をした相続人が、法定相続分以上に貢献した分、多くの遺産を取得することを意味します。
寄与とは貢献を意味する言葉で、その他の相続人より生前に被相続人へ尽くした分、自分より貢献していなかった相続人よりも多くの相続財産の取得を認めてもらうものです。寄与分は民法第904条第2項に規定されています。
引用:民法第904条第2項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条【法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定】までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
寄与分が認められる5つのケース
寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与だったと認めてもらう必要があります。寄与分が認められるケースは、以下5つの類型です。
| ・事業従事型 被相続人の事業を手伝っていた ・金銭出資型 被相続人の事業のために金銭を支出していた ・療養看護型 被相続人の介護に従事していた ・扶養型 被相続人の生活を扶養で支えた ・財産管理型 被相続人の財産を管理し、維持や増加させた |
寄与分を請求できる人とは
相続時に寄与分を請求できる人とは、どのような人でしょうか。詳しくは以下2つのパターンです。
①法定相続人
被相続人の法定相続人は寄与分を請求できます。
②特別な貢献をした特別寄与者
被相続人と同居していた相続人の妻が実際の介護に従事してた、というケースの場合、この相続人の妻は相続人ではないため、介護に貢献していても寄与分を請求できません。そこで、特別な貢献をした親族の場合は「特別寄与料」を請求できます。(民法1050条)
なお、内縁の配偶者やご友人など、親族以外の方は①、②のいずれにも含まれないため、寄与分も特別寄与料も請求できません。
寄与分と特別寄与料の違い
寄与分と特別寄与料の違いは次のとおりです。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
| 請求できる人 | 相続人のみ | 相続人以外の親族 (6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族) |
| 貢献の内容 | 事業従事、金銭出資、療養看護、扶養、財産管理など | 無償の療養看護その他の労務の提供 |
| 請求方法 | 遺産分割協議調停審判 | 相続人に対する金銭請求 |
| 請求期限 | 相続の開始から10年(2023年10月以降) | 相続開始および相続人を知った時から6か月以内(消滅時効) または相続開始時から1年以内(除斥期間) |
| 制度の目的 | 共同相続人間の公平を図る | 相続人ではない親族の貢献に報いる |
寄与分は、相続人による被相続人の財産に対する貢献を評価する制度です。
一方の特別寄与料は、相続人以外の親族による被相続人に対する貢献を評価する制度です。
特別寄与分の請求は消滅時効や除斥期間が短く、請求できる期限が非常に短いため注意が必要です。
寄与分はどのように計算する?

寄与分の主張を検討する場合、どのような計算で寄与分の金額を求めるのでしょうか。そこで、この章では寄与分の計算方法について、各類型別に詳しく解説します。
寄与分の類型別計算方法
寄与分は各類型別に計算します。計算方法は以下です。
| 類型名 | 計算式 |
| 事業従事型 | 基準賃金×従事した年数₋生活費控除額 |
| 金銭出資型 | 贈与した金額×貨幣価値変動率×裁量的割合 |
| 療養看護型 | 療養看護の報酬相当額(日当)×介護日数×裁量的割合 |
| 扶養型 | 負担した扶養料×扶養した期間×(1-寄与相続人の法定相続分の割合」 |
| 財産管理型 | 管理や売却を第三者に委任した際の報酬額×裁量的割合 |
次に、よくある事業従事型と療養介護型の2つについて、計算方法をご紹介します。
【計算例】事業従事型のケース
事業従事型における寄与分(特別寄与料も同様)は、次の式で計算します。
| 基準賃金 × 従事した年数 ー 生活費控除額 |
「基準賃金」とは、「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」から引用することが多いです。
「生活費控除額」とは、寄与分・特別寄与料を請求する人が被相続人と同居していた場合において、生活費を被相続人が負担していたときは、寄与分・特別寄与料を請求する人は被相続人から一定の利益を得ていたと考えるため、その利益相当額として生活費の金額の一部を控除するものです。
たとえば次の相続人A氏が寄与分を請求する場合の寄与分の額を計算してみます。
| ・相続人A氏は 男性 ・被相続人が営む小売業に30歳から現在(40歳)まで無給で従事 ・被相続人と同居、生活費として月1万円を家計に入れる ・被相続人は過去20年の間A氏との二人暮らしで、生活費は月10万円だった |
まず相続人A氏の「基準賃金」を求めます。令和5年度版賃金センサスの第5表によれば、小売業に従事する40~44歳男性の賃金は月額374.2千円とあります。これに12(1年間)を乗じた金額、すなわち449.04万円を今回の「基準賃金」とします。
次に「生活費控除額」を求めます。生活費控除額の計算にはいくつかの種類があります。
ここでは1人あたりの生活費(5万円)から相続人のA氏が支払っていた1万円を引いた月額4万円に12(1年間)を乗じた48万円に、同居している年数を乗じた金額を生活費控除額とします。つまり、48万円に10年を乗じた480万円が今回の「生活費控除額」となります。
以上より、A氏の寄与分は、449.04万円×10年-480万円=4,442.4万円となります。
参考URL:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況 産業別 第5-2表 産業、性、年齢階級別賃金及び対前年増減率
【計算例】療養介護型のケース
療養介護型における寄与分・特別寄与料は、次の式で計算します。
| 療養看護の報酬相当額(日当)×介護日数×裁量的割合 |
「療養介護の日当」は、国が定める介護報酬を基準に計算します。「裁量的割合」は、介護の実態などに応じた調整割合で、実務上は0.5~0.8が適用されます。
たとえば次のB氏が寄与分を請求する場合の寄与分の額を計算してみます。
| ・被相続人は要介護4だった ・相続人B氏は被相続人を3年間介護した ・Bの介護内容は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に該当すると認められる ・Bは被相続人を介護したことによる金銭、その他の利益を得ていない |
まず、「介護報酬基準額」を求めます。2024年度の厚生労働省 介護報酬基準を参考にすると要介護4の日当は6,630円です。「裁量的割合」ですが、この割合はさまざまな要因で変わるため、ここでは0.7として計算します。
以上より、C氏の寄与分は6,630円×1095日(365日×3年を意味する)×0.7=5,081,895円と計算できました。
参考 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定について
実際の寄与分・特別寄与料の計算時の注意点
実際に寄与分・特別寄与料の計算を行う場合、専門的な知識が必要です。
寄与分の計算には貢献度の評価が欠かせず、評価を算定は極めて複雑であるためです。
貢献度は、金銭的な価値に換算する必要があり、その算定基準は明確ではありません。たとえば療養介護の場合、介護期間や内容、被相続人の要介護度などを考慮する必要があります。
また、特別寄与料も含めて療養介護の計算では、親族間の扶養義務も考慮する必要があります。どこまでが扶養の範囲で、どこからが特別な貢献として評価されるのか、線引きは容易ではありません。弁護士などの専門家に相談した上で、請求に臨まれることがおすすめです。
寄与分・特別寄与料の請求方法とは

寄与分や特別寄与料を請求するにあたっては、どのように他の相続人へ請求するのでしょうか。この章で請求方法を紹介します。
相続人同士の話し合い
寄与分・特別寄与料は他の相続人へ請求します。
寄与料の場合は共同相続人へ、特別寄与料の場合は相続人以外の親族から相続人に対して請求します。
事業に貢献した、介護に従事したと口頭で述べても難しいため、請求の際には証拠を用意する必要があります。たとえば、扶養型の場合なら預貯金通帳やカードの利用明細などを通して、いかに扶養で貢献していたか客観的に証拠を使って主張します。
調停・審判
寄与分・特別寄与料の請求が他の相続人には認めてもらえない、あるいは話し合いに応じてもらえない場合、調停が可能です
- 遺産分割調停
- 寄与分を定める処分調停
- 特別の寄与に関する処分調停
遺産分割の話し合いの中で解決したい場合は、遺産分割調停を行います。寄与分のみを検討してほしい場合は寄与分を定める処分調停を行います。ただし、一般的にはこの2つの調停は併合して行われます。
調停が不成立の場合は審判へ移行し、裁判官の判断を仰ぎます。
注意!寄与分・特別寄与料がある場合の相続税申告

寄与分・特別寄与分が認められた場合、相続税申告にも影響する可能性があります。この章では押さえておきたい相続税申告時の注意点を紹介します。
寄与分の相続税申告
受領する寄与分を含めて相続税の申告を行います。遺産総額からいったん寄与分を差し引いて各人の相続分を計算したあと、寄与分が認められた相続人に対して寄与分を加算して計算します。
特別寄与者の相続税申告
特別寄与者は相続人ではないため、被相続人から遺贈があったものとして、相続税の申告を行います。特別寄与料の金額が決まってから10か月以内に相続税の申告書の提出と相続税額の納付が必要です。
なお、遺贈で財産を取得した人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額が2割加算されますが、特別寄与者もこの2割加算の対象となります。相続税の申告書を作成する際はご注意ください。
また、特別寄与料を支払った相続人は、その特別寄与料を相続税の債務控除できます。すでに相続税の申告納付が完了していた場合は、特別寄与料の支払いが確定してから4か月以内に更正の請求をすることで、払い過ぎた相続税額の還付を受けることができます。
まとめ
相続の話し合いの際に、しばしば複雑な問題となる「寄与分」について、計算方法なども交えながら詳しく解説しました。寄与分以外にも、相続人以外の親族は特別寄与料の請求も可能です。しかし、いずれの場合も計算方法は複雑であり、調停や審判を要するケースもあるためご注意ください。
横浜市の響き税理士法人では、寄与分や特別寄与料も含めた相続税申告のご相談にも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。