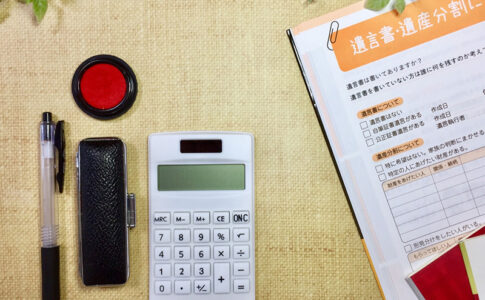マイホームの新築・購入を検討されている場合、どのぐらいの資金を用意すべきか悩む人は多いでしょう。マイホームは決して安いお買い物ではないため、ローンや頭金準備などに翻弄されてしまう人も決して少なくありません。
このような時に活用されているのが「住宅取得等資金の贈与」です。この贈与制度を上手に活用すると、マイホームの土地購入資金について非課税限度額までは贈与税がかかりません。お財布に嬉しい贈与です。
しかし、実際の適用時には要件もあるため注意が必要です。本記事では住宅取得などの資金贈与の注意点や、利用時のポイントを詳しく解説します。
「適用できなかった!」というトラブルを避けるためにも、ぜひご一読ください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
住宅取得等資金の贈与とは|制度利用のポイント

この贈与制度は、住宅の新築や増改築、建売住宅、中古住宅、マンションの購入など際に、必要な資金を購入する人の「直系尊属」が出してくれた場合、 一定の条件をクリアすれば非課税限度額まで贈与税が非課税 になる制度です。
この章では制度利用の概要を詳しく解説します。
制度を利用できる人
本贈与制度を利用できる贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)は限定されています。
①贈与者(贈与をする人)
贈与をする人は、直系尊属に限られます。つまり、マイホームを新築や増改築などを予定している人の「両親・祖父母など」が該当します。
②受贈者(贈与を受ける人)
贈与を受ける人は、①に挙げた両親や祖父母から見た「子・孫」(直系卑属)が該当します。
受贈者の要件
制度を利用できる受贈者は、おもに以下の要件をクリアする必要があります。
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて、住宅の新築や土地の取得などをすること
- 贈与をうけた年の翌年3月15日までに新しい住宅に住むこと、または3月15日以後住むことが確実であると見込まれること
この他に、所得税に関する要件なども設けられています。詳しくは以下の国税庁HPをご確認ください。
参考URL 国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
非課税限度額
本贈与制度で受けられる非課税限度額は以下です。なお、受贈者ごとに贈与制度を利用できるため、親や祖父母は複数の子や孫に、贈与できます。
①省エネなど住宅の場合は1,000万円まで
②一般住宅の場合は500万円まで
住宅取得等資金の贈与を利用できないケース

お金がかかるマイホームの新築や取得時には、家族から資金援助を受けられると物件や土地選びの選択肢も増えるため、積極的に活用していきたい制度です。しかし、要件もあるため贈与ができないケースもあります。
そこで、本章では確実に贈与を進めていくためにも利用できないケースについても詳しく解説します。
① 土地だけを購入した場合
土地の購入だけで住宅の新築、購入、増改築のいずれかを行わなければ、特例を利用できません。
「住宅取得等資金の贈与の特例」で認められる土地購入資金とは、次の三つと決められているからです。
(1)住宅用家屋の新築に先行してその敷地として使われる土地の取得のための資金
(2)土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地または土地の上に存する権利の取得のための資金
(3)増改築等とともにするその敷地として使われる土地の取得資金
住宅取得についても期限が設けられており、住宅の新築・取得・入居について当面見通しがつかない場合は本贈与制度が使えない可能性があります。
スケジュールをしっかりと把握し、慎重に進める必要があるのです。
②新しい住宅の名義が土地購入資金の贈与を受けた人でない場合
住宅取得資金贈与を土地の購入にも使いたい場合、新しい住宅の所有者が土地購入資金の贈与を受けた人でない場合は利用できません。
たとえば、夫婦2名でマイホームの土地と建物を取得するために協力して資金を出し合うと仮定します。
妻が妻側の父親から土地購入資金の贈与を受け、取得した土地の名義を妻、住宅の名義を夫にすると、夫婦のいずれも特例を利用できません。
特例を利用するためには、自分の直系尊属から贈与をうけなければならないからです。
今回の場合、土地購入資金を贈与した人は妻の父(直系尊属)です。夫の直系尊属ではありません。
また、特例を利用するためには、住宅の名義が住宅取得等資金の贈与を受けた人でなければならないというルールもあります。
土地購入資金の贈与を受けた人は妻ですが、この例では住宅の名義が夫であるため贈与の要件を満たせません。そのため、夫婦のいずれも贈与制度を利用できなくなってしまうのです。
この点を理解していないと、思わぬ贈与税の課税で驚くことになってしまうためご注意ください。
上手に住宅取得等資金の贈与を活用するポイント

要件をクリアしていない場合、せっかくの贈与制度も利用できなくなってしまいます。そこで、この章では住宅取得等資金の贈与を活用する際のポイントを詳しく解説します。ぜひご一読ください。
①土地だけを購入し、住宅建築や増改築などの予定がない場合
住宅取得等資金の贈与は、新築や増改築、既存住宅の取得を目的とした贈与に適用される制度です。そのため、前述のとおり贈与を受けた資金で土地のみを購入し、その年度内に住宅を新築する予定がない場合は、特例の対象になりません。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築、取得、増改築のいずれかを行えば、特例を利用できます。
②新しい住宅の名義が土地購入資金の贈与を受けた人になっていない場合
贈与を受けた資金を住宅の購入費用に充てたにもかかわらず、その住宅の登記簿上の名義人が、贈与を受けた人以外になっている場合も特例の対象外となります。
住宅の名義を土地購入資金の贈与を受けた人にすれば、特例を利用できます。
先ほどの述べた夫婦の例では、住宅の名義を夫婦共有の名義にすれば特例を利用できます。
③もしも頭金に贈与で得た資金を使わなかったらどうなる?
贈与された資金を住宅の頭金として利用しなかった場合でも、住宅の取得費用に充当したと認められれば特例の適用対象となります。
ただし、贈与を受けた資金を住宅の取得とは関連しない家具の購入、住宅ローンの返済に使用した場合は特例の対象外となるので注意が必要です。
④制度の対象年度に注意
現在の住宅取得等資金の贈与税の特例は「令和6年1月1日から令和8年12月31日」とされており、今後制度の内容や非課税限度額が変更される可能性もあります。
特例を利用する際は、必ず最新の情報を確認し、適用期間内に贈与を受けるようにしましょう。
住宅取得等資金の贈与の特例以外に利用できる贈与はある?

住宅取得等資金の贈与の利用はどうしても難しい場合には、その他に活用できる贈与制度はあるでしょうか。
一般的に広く利用されている暦年贈与にも非課税枠はありますが、年間110万円までと少額のため、住宅購入などにおける贈与には物足りなく感じるかもしれません。そこで、次にご紹介する贈与を検討しましょう。
相続時精算課税制度を活用しよう
相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる制度です。
2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、贈与した財産は、贈与者の死後に相続財産として精算されます。また、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例と併用することも可能です。詳しくは以下関連記事をお読みください。
まとめ
住宅取得等の資金の贈与は、住宅購入を検討している方にとって非常に有益な制度です。しかし、特例を適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、正しく理解していないと、かえって贈与税が課税されてしまう可能性もあります。
贈与を実際に利用する前に、マイホームの建築や取得のタイミングをしっかりと確認し、要件をクリアしているか確認しましょう。
また、高額の贈与を検討したい場合には「相続時精算課税制度」を併用することも可能です。上手に組み合わせることで、より効果的に資産を移転させることができます。
ただし、これらの制度は複雑であり、個別の状況によって最適な選択肢が異なります。まずはお気軽に、横浜市の「響き税理士法人」へご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。