
親子や夫婦など、家族間におけるごく少額のお金の貸し借りはどこの家庭でも普通にあることです。いちいち契約書を取り交わすことはまずないと思いますが、金額が大きくなると話が変わってきます。
お金を返してもらう約束を保全するという単純な目的以外に、税金面でのリスク回避のために契約書の作成が望まれるケースもあるのです。
本章ではお金の貸し借りに関する「金銭消費貸借契約書」の必要性について、税金面でのリスクと合わせて解説していきます。
目次
金銭消費貸借契約とは?
金銭消費貸借契約とは、平たく言えばお金を借りて返すことを約束するもので、要するに借金をする際の契約ということです。契約は基本的に口約束でも成立しますが、後で「言った・言わない」の争いになることを避けるために通常は約束事を書面に残すことになり、これが金銭消費貸借契約書という形でまとめられます。
一般的に金銭消費貸借契約書でどのような定めを記載するか見てみましょう。
安全のために家族間でも契約書の作成が勧められる

原則論で言えば、家族間でのお金の貸し借りでも基本的には契約書を作成した方が安全です。ごく少額であれば問題ないかもしれませんが、約束通り返済されなければ気持ちの良いものではありませんし、これが高額になれば家族間に不和をもたらす原因になるからです。
こうした取り引きの安全を図るという観点とは別に、税金面の不利益を避けるためにも金銭消費貸借契約書を作成することが勧められます。
実質的には返済されない金銭の交付は贈与であるとみなされ、これに贈与税を課税されることがあるので注意が必要なのです。1000万円につき、20歳以上(成人年齢の改正により令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)の者が、親や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合は税率30%、控除額90万円ですので、210万円の贈与税がかかる計算です。
税務署から実質的な贈与であると見られないためにも、お金の貸し借りをするのであれば家族間でも金銭消費貸借契約書を作成し、返済の約束があることの証明を残しておくことが勧められます。
贈与とみなされるリスクが高いケース

ここでは税務署に贈与とみなされるリスクが高いケースを見てみましょう。
返済期日を逸しているケース
金銭消費貸借契約書を作成したとしても、定められた返済期日を過ぎてなお返済できていない場合、最初から返済するつもりのない贈与であるとみなされる可能性があります。書面で約束したとしても、それは形だけだと判断されるわけですね。
収入に比して貸付金額が高額なケース
お金を借りる側の収入が少ないのに、高額のお金を貸すような行為は最初から返済を求める意志が無いと判断され、これも贈与とみなされることにつながります。
利息を取らないケース
金銭消費貸借契約において、利息を取るかどうかは契約当事者の判断に委ねられます。つまり利息の設定は必須ではないので、家族間の場合利息を取らないことも多いと思います。
ただしこの場合、税務署目線では本来かかるはずの利息利益を放棄した=借り手側に利益を供与したと捉え、利息分を贈与したとみなされる可能性があります。素人目線ではかなり意地悪に映りますが、税金を取りたい税務署目線ではこのような解釈をすることがあるので要注意です。
契約書が無いケース
そして最も注意が必要なのが契約書を作成しないケースです。口約束でも契約自体は成立しますが、契約書が無いと金銭消費貸借契約を結んだことを第三者に証明できません。
税金を取りたい税務署から見るとここが突っ込みどころとなり、贈与とみなす口実を与えてしまうことになります。税金を取りたいと考える税務署に対して抗弁するには、贈与ではなく借金であることを証明するために契約書を作成しておくのが有効ですので、まずは基本として覚えておいてください。
ただし、家族間での貸し借りであることを考えれば、できるだけ契約書の作成などの手間は避けたいところですよね。この点、一定金額までであればいちいち金銭消費貸借契約書を作成しなくても一応の安全を確保できるので、これに関して次項で見ていきます。
贈与税には基礎控除がある
贈与税には基礎控除というルールがあり、財産をもらい受ける側の人を基準に年間110万円までは贈与税がかからないことになっています。ということは、お金を借りる人を基準として年間110万円までの借金であれば、契約書を作成せず、仮に税務署に贈与とみなされても贈与税がかからないということです。
これを踏まえると、一般的な家庭において日常的に発生するごく少額の貸し借りにおいては、いちいち金銭消費貸借契約書を作成しなくても問題ないことが多いということになります。ただし、年間110万円以下であっても毎年定期的な金銭の交付があるようなケースでは、税務署に「定期贈与」という解釈を持ちだされる可能性があるので注意が必要です。
素人には考えづらいこのような解釈で課税される恐れもあるので、基礎控除の範囲内であっても数年かけてまとまったお金の貸し借りをするならば契約書を作成する方が安全と言えます。契約書を作成した方が良いかどうか判断が難しい場合はぜひ専門家である税理士にご相談ください。
契約書の作成方法と注意点

ここでは金銭消費貸借契約書を作成する際の注意点について解説します。契約書には最低でも貸し借りの対象となる金額と返済期日について必ず記載が必要です。
返済期日が無いことはつまり返さなくても良い=贈与と直に解釈される恐れがあります。そして家族間であっても利息や遅延損害金については一般的に妥当と考えられる範囲で設定した方が贈与とみなされるリスクは下がります。
家族間であることを考えると保証人や抵当の設定はなくても良いと思いますが、設定した方が「みなし贈与」とされるリスクはやはり下がります。そして大きなポイントとして、返済の方法は証拠が残る口座振り込みにするのがお勧めです。
手渡しと違い証拠が残る振り込みであれば、返済の事実を税務署に証明する手立てとして機能します。契約書の作成や契約条項の設定については安全を考慮して一度税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
本性では「金銭消費貸借契約書」がどのようなものか、契約としての性質や税金面のリスクを回避するための手段としてどのように機能するのかなど、基本的なところを見てきました。家族間でも年間110万円を超えるお金の貸し借りをする場合は、贈与税を課税されるリスクを避けるために金銭消費貸借契約書を作成しておくことが勧められます。
思わぬ課税を受けないためにも、不安な点は税理士に相談するなどして貸し借りの証拠を残しておくようにしましょう。

税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。

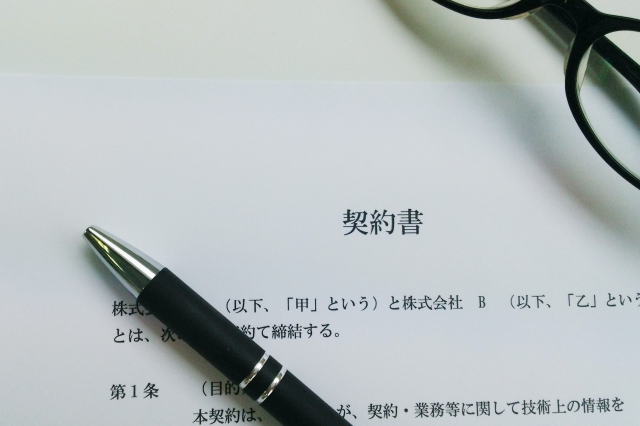




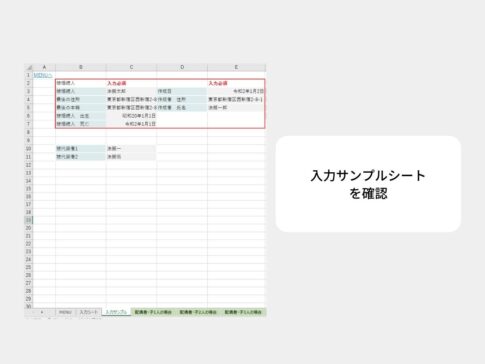












借り入れる金額を明記します。
返済の期日や分割払いで返済する場合はその回数を記載します。
銀行振り込みにするのか、持参して手渡しにするのかなど返済の方法を記載します。
元本にプラスして利息が付く場合は利率を記載します。
返済が遅れた場合のペナルティとして遅延損害金を設定する場合に記載します。
原則として分割返済とする場合でも、一定の返済期日を逸した場合は分割払いの権利が失われ、残金を一括で弁済する義務を生じさせる場合に記載します。
返済が滞った場合に代わりに弁済を求めることができる保証人を設定する場合はこれに関する事項、また抵当権を設定する場合はこれに関する事項を記載します。このように、金銭消費貸借契約書は単にお金を借りて返すという約束だけでなく、これに付随する様々な条件を取り決めるのが普通です。