
「外国人なら日本の相続税はかからない」という話を聞いたことはありませんか?
実は、これは半分正解で半分誤解です。
日本に住む外国人が亡くなった場合、原則として日本の相続税がかかります。ただし、ビザの種類や日本での居住期間によって、海外にある財産が非課税になる「10年ルール」という特例があるのも事実です。
さらに、外国人でも日本人と同じく基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)が適用されるため、この範囲内であれば国籍に関係なく相続税はかかりません。
ただし外国人の相続に関しては、在留資格や国内外財産の判定、複数国籍を持つ場合の扱いなど、複雑な要素がいくつも絡み合うため、「自分のケースでは相続税がかかるのか?」と悩む方も多いんです。
そこで今回は、外国人の相続税に関する基礎的な情報はもちろん、10年ルールの仕組みや相続税がかからない具体的な条件、相続税がかからなくても必要な相続登記の手続きなど、実務面においても重要な知識を分かりやすくお伝えします。
外国人の相続でお悩みの方、将来に備えたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
原則、相続は被相続人の国籍の法律を適用

外国人に日本の相続税がかかるかどうかを判断する前に、まず理解しておくべき大原則があります。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。つまり、亡くなった方(被相続人)の国籍によって、適用される法律が決まるということです。
被相続人が日本国籍の場合
被相続人が日本国籍であれば、相続人が外国籍であっても、また海外に居住していても、日本の相続法が適用され、日本の相続税の対象となります。
被相続人が外国籍の場合
被相続人が外国籍の場合は、その国の法律に従うことが原則です。ただし、日本に財産がある場合や、相続人が日本に居住している場合などは、日本の相続税が課税される可能性があります。
複数国籍を持つ場合は日本国籍優先
最近では、複数の国籍を持つ方も増えています。日本では原則として重国籍は認められていませんが、出生や親の国籍などの事情により、複数国籍を持つケースがあります。
法の適用に関する通則法第38条では、複数国籍を持つ場合でも、その中に日本国籍が含まれていれば、日本法が優先適用されると定められています。
たとえば、アメリカと日本の二重国籍を持つ方が亡くなった場合、アメリカの法律ではなく日本の法律が適用され、日本の相続税制度に従うことになります。
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
外国人に相続税がかかる4つのパターン
外国人の相続税を理解する上で最も重要なのが、納税義務者に関する4つの分類です。被相続人と相続人の国籍や居住状況などの組み合わせによって、課税される財産の範囲が大きく変わります。
納税義務者の4分類表
| 納税義務者の分類 | 相続人の状況 | 被相続人の状況 | 課税対象財産 |
|---|---|---|---|
| 居住無制限納税義務者 | 日本に居住 | 日本国籍または日本居住 | 国内外すべての財産 |
| 非居住無制限納税義務者 | 海外居住(10年超) | 日本国籍または過去10年内に日本居住 | 国内外すべての財産 |
| 居住制限納税義務者 | 日本に居住(外国籍・一時居住者) | 外国籍かつ一時居住者 | 日本国内の財産のみ |
| 非居住制限納税義務者 | 海外居住 | 外国籍かつ日本非居住 | 日本国内の財産のみ |
「無制限」は国内外すべての財産が対象、「制限」は日本国内の財産のみが対象と覚えると分かりやすいです。
1. 居住無制限納税義務者
日本に住んでいる相続人が該当します。国籍は問いません。この分類の方は最も課税範囲が広く、国内外すべての財産が相続税の対象となります。
たとえば、日本で働いている外国人の方が、同じく日本在住の親から相続を受ける場合などがこれにあたります。
2. 非居住無制限納税義務者
海外に10年を超えて居住している方が該当しますが、被相続人が日本国籍を持っていたり、過去10年以内に日本に住んでいた場合には、この分類となります。海外にいても全世界の財産が課税対象となるのが特徴です。
例としては、アメリカに10年以上住んでいる日本人が、日本にいる親から相続を受けるようなケースです。
3. 居住制限納税義務者
就労ビザや留学ビザなどで、日本に一時的に居住している外国人の方がこれに該当します。この分類の特徴としては、「10年ルール」が適用されることで、海外にある財産は非課税となる点です。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(いわゆる技人国ビザ)で5年間日本に住んでいる外国人の方が、母国の親から相続を受ける場合、海外にある財産は相続税がかかりません。
4. 非居住制限納税義務者
日本との関係が薄い外国居住者が該当します。被相続人も相続人も外国に住んでいて、日本には不動産などの財産だけがある場合などです。この分類では、日本国内の財産のみが課税対象となります。
例としては、一度も日本に住んだことのない外国人の方が、投資用に購入していた日本のマンションを相続するケースなどがあります。
「10年ルール」について|相続税がかからない外国人の条件

「外国人は相続税がかからない」という勘違いの根拠となっているのが、通称「10年ルール」です。正確には、一定の条件を満たす外国人の海外の財産が非課税になる制度のことです。
10年ルールが適用される3つの条件
相続税が軽減される10年ルールの適用を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります
この3つの条件をすべて満たす場合、海外にある財産については日本の相続税がかかりません。ただし、日本国内にある財産(不動産、預貯金など)は課税対象となります。
在留資格による10年ルールの適用可否
10年ルールの適用において重要なのが、在留資格(ビザ)の種類です。税法上では「表1」「表2」という区分があるのですが、簡単に言えば「一時的な滞在者」か「定住者」かという違いです。
10年ルールが適用される在留資格(一時的滞在者)
| ビザの種類 | 具体例 | 10年ルール |
|---|---|---|
| 就労系ビザ | 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、企業内転勤、特定技能など | ◯ |
| 留学・研修 | 留学、研修、技能実習 | ◯ |
| その他一時滞在 | 文化活動、短期滞在、家族滞在など | ◯ |
10年ルールが適用されない在留資格(定住的資格)
| ビザの種類 | 具体例 | 10年ルール |
|---|---|---|
| 永住系 | 永住者、特別永住者 | ✖ |
| 配偶者系 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 | ✖ |
| 定住者 | 定住者(日系人など) | ✖ |
配偶者ビザの方は、日本での居住期間が10年以下でも10年ルールは適用されず、全世界の財産が相続税の対象となります。
10年ルール判定フローチャート
10年ルールの適用可否について、わかりやすくフローチャートでまとめてみましたので、適用されるかどうかがわからない方はぜひ参考にしてみてください。
【ステップ1】被相続人は外国籍ですか?
YES → ステップ2へ
NO → 10年ルール適用なし(全世界財産が課税対象)
【ステップ2】被相続人のビザは一時滞在者用ですか?
YES → ステップ3へ
NO → 10年ルール適用なし(全世界財産が課税対象)
【ステップ3】過去15年間での日本居住期間は10年以下ですか?
YES → 10年ルールが適用(海外財産は非課税)
NO → 10年ルール適用なし(全世界財産が課税対象)
10年ルール適用時の計算例
ケース:中国籍のAさん(技術ビザで日本に来て8年)が亡くなった場合
日本の財産:5,000万円(不動産3,000万円、預金2,000万円)
中国の財産:3,000万円(中国の銀行預金)
相続人:配偶者と子供1人(いずれも中国籍)
10年ルール適用の判定:
- 外国籍:中国 → ◯
- 一時滞在者用ビザ(技術)→ ◯
- 日本居住年数8年(10年以下)→ ◯
【相続税額の計算】
課税対象:5,000万円(中国の財産:3,000万円は非課税)
基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税価格:5,000万円-4,200万円=800万円
相続税額:800万円×10%=80万円
もし10年ルールが適用されない場合、8,000万円全額が課税対象となるため、相続税額も大幅に増加してしまいます。
日本の相続税が課税される財産

外国人の相続において、どの財産が日本の相続税の対象となるのか、正確に把握することが重要です。特に、国内財産と国外財産の判定基準は複雑なため、注意が必要です。
国内財産・国外財産の判定表
日本国内にある財産については、日本の相続税が課税されます。財産の種類別における国内財産と国外財産の判定は以下の通りです。
| 財産の種類 | 所在の判定 |
|---|---|
| 動産・不動産 | 置かれている所在地 |
| 預貯金・積立金 | 受け入れをした営業所・事業所 |
| 合同運用信託・投資信託等 | |
| 営業上の権利(売掛金など) | |
| 貸付金 | 本店または主たる事務所 |
| 株式・社債など | |
| 生命保険契約・損害保険契約の保険金 | |
| 退職手当金 | |
| 国債・地方債 | 日本国内 |
| 外国の国債・地方債 | 発行した国 |
外資系企業でも、日本支店から受け取るものは「国内財産」となります。
不動産など所在地に合わせて判定できるものもありますが、中には株式や外国債など判定の難しい財産もあります。
国内財産・国外財産の扱いについては、基本的には税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
国外財産は邦貨に換算する
相続税で国外財産を計算する場合には、邦貨つまり日本円に換算する必要があります。国外財産は主に外貨預金や海外にある不動産などがあるでしょう。
換算する基準日と相場は原則以下の通りです。
換算日:被相続人の死亡日
換算レート:対顧客直物電信買相場(TTB)
例外:死亡日に相場がない場合は、最も近い日の相場を使用
ただし、先物外国為替契約の締結で設定した相場がある場合、上記の通りではなく契約締結時または締結時以後に設定したレートで決済されます。
外国人の相続時に見落としがちな財産
外国人の相続において、特に見落としがちな財産をいくつかまとめましたので、注意してください。
こういった財産も適切に評価して、申告する必要があります。
外国人が亡くなった場合の実務上のポイント

外国人の相続では、国際的な要素が絡むため、通常の相続よりも複雑な手続きが必要になることがあります。ここでは、実務で特に重要な2つのポイントを解説します。
遺産分割が間に合わないときは「未分割申告」を活用
外国人の相続では、様々な理由から申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合わないケースが多くあります。
- 海外在住の相続人との連絡・協議
- 国外財産の調査・評価
- 必要書類の取得に時間がかかる(翻訳・認証など)
このような場合、未分割申告を活用することで、延滞税などのペナルティを回避できます。
未分割申告の手順
- 申告期限内に仮申告を済ませる
仮に、法定相続分で計算して申告・納税を済ませる。
※「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付 - 遺産分割協議を進める
申告後も協議を継続しながら、3年以内の分割を目指す。 - 分割確定後に必要な手続きを取る
税額が確定した結果、税金が減る場合は「更正の請求」、税金が増える場合には「修正申告」という手続きをすることで、納税が完了します。
未分割申告のデメリットと対策
未分割申告は、期日を引き延ばせる反面、デメリットも存在するため、活用する際は慎重に進める必要があります。
| デメリット | 対策 |
|---|---|
| 配偶者控除が使えない | 3年以内に分割すれば遡及適用可 |
| 小規模宅地等の特例が使えない | 3年以内に分割すれば遡及適用可 |
| 物納ができない | 延納制度の検討 |
| 農地の納税猶予が受けられない | 事前の資金計画 |
3年以内に分割すれば、これらの特例を遡って適用することで、払いすぎた税金の還付を受けられます。
「未分割申告」を活用する場合、かなり専門的な内容になるため、基本的には税理士などの専門家を通して手続きすることをおすすめします。
課税がなくても不動産の相続登記が必要
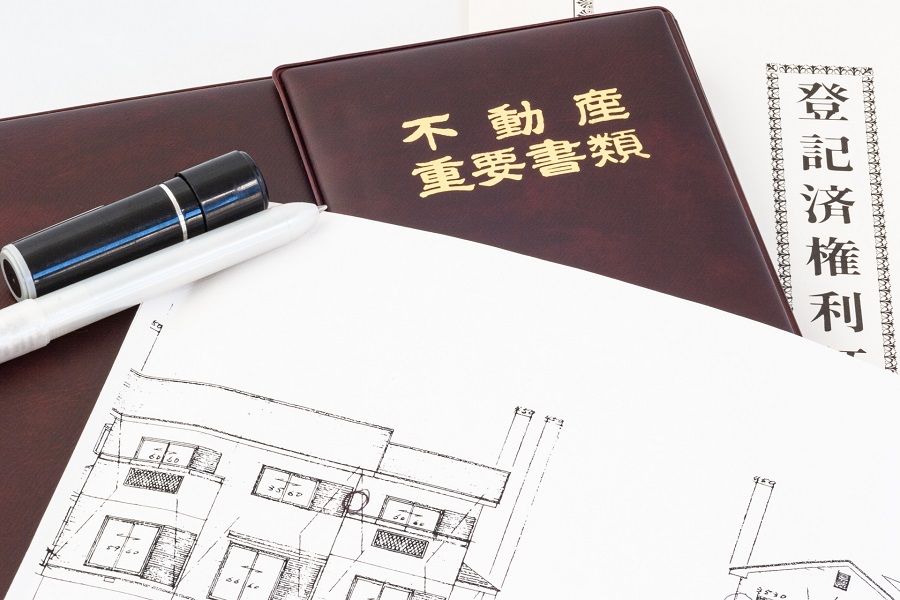
「相続税がかからないから手続きは不要」と考えてしまうのは危険です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続税の有無に関わらず、不動産の名義変更が必須となりました。
期限:相続を知った日から「3年以内」
罰則:正当な理由なく怠ると「10万円以下の過料」
対象:2024年4月以前の相続も対象(3年の猶予期間あり)
また外国人の相続登記では、出生証明書や本国で発行が必要な書類など、日本人とは異なる書類が必要になります。取得や翻訳などにどうしても時間がかかるため、早めの準備が重要となります。
相続登記を怠ると、不動産の売却や担保としての活用ができなくなるだけでなく、次回の相続時にさらに手続きが複雑化してしまうリスクもあります。相続税の申告が不要でも、必ず期限内に登記手続きは行いましょう。
まとめ:外国人の相続税は、税理士に相談を
今回の記事では、外国人の相続税について詳しく解説してきました。最後に重要なポイントについて振り返ってまとめておきたいと思います。
こうした複雑な要素を適切に判断し、最適な相続対策を行うためには、国際相続に詳しい税理士のサポートは不可欠でしょう。
相続税の申告期限は10ヶ月と決まっており、外国人の相続では準備に想定以上の時間がかかります。また生前対策を行うことで、10年ルールを活用した節税や、スムーズな相続手続きの準備も可能となりますので、お早めのご相談をおすすめいたします。
私たち「響き税理士法人」では、外国人の相続税についても一貫したサポートを提供しております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。





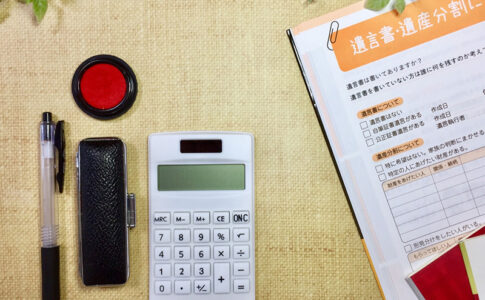



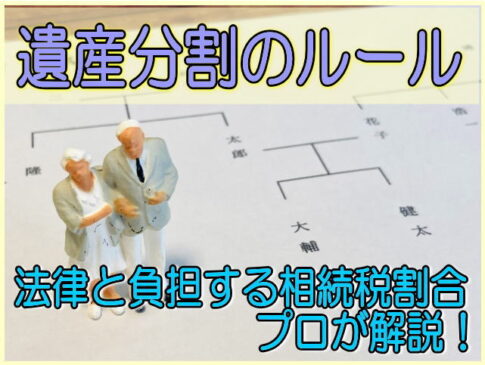









第六節 相続
(相続)第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。