
ご家族が亡くなり相続が開始されたら、遺産分割協議によって遺産の分配を行います。
遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があるため、相続開始後は速やかに相続人へ通知を行い、遺産分割協議に参加するように依頼します。
しかし、相続人の中にはほとんど面識がない方がいることも多く、どのように通知するべきか悩むケースも少なくありません。
そこで今回の記事では、遺産分割を行うにあたって最初に行うべき「相続人への通知」の方法や、手紙の文例について注意点も交えながら解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
なぜ相続人全員に通知が必要?

相続が開始され遺言書がない場合には、相続人全員に遺産分割協議を知らせる連絡を行います。では、なぜ相続人全員に対して通知を行う必要があるのでしょうか。この章では遺産分割協議のルールに触れながら、通知の必要性をわかりやすく解説します。
遺産分割協議は相続人全員参加が必要
被相続人が亡くなり、遺言書がない場合は被相続人が残した遺産を相続人間で分けるために遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、民法で決められた法定相続人全員が参加しなければ無効となるという決まりがあります。(民法907条)
没交流であったり、あまり面識のない相続人であっても全員に遺産分割協議を開始することについて通知する必要があるのです。
また、相続手続きにはさまざまな期限があります。遺産分割協議自体には法的な期限はありませんが、相続放棄や相続税の申告などには期限が設けられているため、相続開始後は早急に遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人とは
遺産分割協議で通知をする必要がある方は、「法定相続人」に該当する人です。法定相続人には順位があり、以下のように民法で定められています。
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 直系卑属(子や孫) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
たとえば、妻と子が相続人になるケースでは、亡くなられた被相続人に前妻との子がいる場合があります。前妻の子の連絡先がわからず、疎遠な間柄であっても相続人に該当するため遺産分割協議の開始を通知する必要があります。
よくある疎遠な相続人のケース
では、疎遠な相続人とはどのような方でしょうか。よくあるケースは以下のとおりです。
・被相続人の前妻・前夫との子
・被相続人が過去に認知した子
・被相続人の両親や祖父母、兄弟姉妹
・代襲相続人
代襲相続とは、本来相続するべき方が相続開始前に亡くなられている時、亡くなられた方の子が相続人となることを意味します。たとえば、配偶者と被相続人の兄が相続人となるケースでは、兄も亡くなっていることがあります。
兄に子がいる場合は代襲相続が発生し、兄の子と遺産分割協議をする必要があります。
相続開始から相続人に手紙を出すまでの流れ

実際に相続人に対して通知を出す際には、どのように進めればよいでしょうか。この章では文を送付するまでの流れを詳しく解説します。
戸籍謄本を集めて相続人を確定する
まずは相続人全員を確定をするために、被相続人の戸籍謄本を集めて、誰が相続人なのか確定します。通知を出す前に相続人を確定しておかないと、通知漏れが起きる可能性があるためです。
まずは以下の戸籍謄本を用意し、相続人を調べます。
・被相続人の出生から死亡にいたる、すべての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
次に、被相続人の子の有無や、両親・祖父母のご健在か否かにあわせて戸籍謄本を収集します。
①被相続人に子がおり、子がすでに死去している場合
亡子の出生から死亡までの戸籍謄本類
②被相続人に子や孫がいない場合
父母や祖父母の戸籍謄本類
③被相続人に、子がおらず両親・祖父母も死去している場合
亡くなられている父母・祖父母の戸籍謄本類および、兄弟姉妹の戸籍謄本類
④兄弟姉妹も亡くなっている場合
亡くなられた兄の子の戸籍謄本類
戸籍謄本の収集によって相続人が確定したら、「相続関係説明図」を作成し各相続人と被相続人の関係をまとめましょう。
被相続人の遺産を調査する
次に、被相続人が残した遺産を調査し財産目録を作成します。相続人への通知の際は、トラブルを避けるため、たとえ疎遠な親戚であったとしても、遺産については預貯金だけでなく不動産も含めて包み隠さず伝えましょう。
なお、遺産には債務も含みます。預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、ローン等の借入も相続するため、正確に伝えましょう。
面識のない相続人の住所を調査する
連絡先が分からない相続人に遺産分割協議の開始を知らせるためには、手紙を出す必要があります。
戸籍謄本取得の段階で疎遠な親戚がいると判明している場合、「戸籍の附票」を請求しておくことがおすすめです。
戸籍の附票を取得するためには、まず戸籍謄本でその相続人の本籍地を確認します。そして、相続人の本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求します。
関係性の遠いご家族の証明書を個人で取得するのは難しいため、司法書士や行政書士など法律の専門家に相談しましょう。
通知時に知っておきたい2つの注意点

普段から交流がなかった相続人へ遺産分割協議への参加をお願いするときは、威圧的にならないように手紙の文面など慎重に考えることが大切です。
手紙の印象が不誠実であったり一方的な内容であったりすると、相手方に不信感を抱かれて連絡がとれないまま相続手続きが進まないおそれがあります。この章では通知時の注意点を2つにわけて紹介します。
1.法定相続分を確定してから手紙を出す
相続人への通知の際は手紙を出す前に、すべての戸籍謄本を集めて相続人を確定させてから行います。相続人および各法定相続分が確定していないと、手紙を受け取った相手から相続分を質問されても答えることができず、不信感を持たれてやり取りが停滞するおそれがあります。
2.最初の手紙は専門家ではなく自分で書く
最初の手紙は、法律の専門家ではなく、ご自分で書くようにしましょう。
相続のために必要な手続きとはいえ、突然知らない司法書士や行政書士などの事務所から封筒が届くと驚いてしまいます。
特に弁護士からの通知はトラブルを予感させる可能性もあるため注意しましょう。
面識がない相続人宛に手紙を書く際のポイント

面識が全くない相続人宛に手紙を出す場合には、どのようなポイントを押さえておくと良いでしょうか。この章でわかりやすく解説します。
自分が何者なのかをはっきりと示す
手紙のはじめには今回亡くなった被相続人と、ご自身のお名前、被相続人との続柄を記載し、自分が何者なのかをはっきりと示します。
これらの記載は、手紙が詐欺やいたずらではないことを示すという目的もあります。「しばらく連絡は取りあっていないが、名前くらいは覚えているだろう」と思ったとしても、明確に記載しましょう。
被相続人が亡くなった経緯を示す
次に相続の開始について、被相続人が亡くなった経緯を書きましょう。差し障りのない範囲で、被相続人が亡くなった日時やご年齢、どのように亡くなったのかなどを記載します。
遺産分割協議に協力して欲しい旨を伝える
相続人に該当すると遺産分割協議に協力してもらう必要があるため、手紙にはその旨も記載します。もしも生前の被相続人とかかわりがなかった方であっても、一方的な遺産分割案を提示することは控えましょう。トラブルのもととなるおそれがあります。
また、相続財産の内容(不動産・預貯金など)や各相続人の法定相続分を記載する場合は、すべてて記載しましょう。
長年疎遠な親戚に対して財産の内容まで伝えたくないとしても、相続人は遺産分割協議に参加する権利があります。手紙を受け取る側としても、財産の内容や相続分の割合が分からなければ返答しかねます。
連絡の折り返しについて期日を設ける
面識のない親戚から手紙が届くと、面倒だからという理由で無視されてしまうことも少なくありません。連絡がつかない限り遺産分割協議を行えないため、連絡の折り返しについては期日を設けましょう。
また、相続税や相続放棄などの手続きには期限がある旨を伝えておくようにしましょう。
相続人への手紙の文面を紹介
税理 響き 様
拝啓
突然お手紙を差し上げる失礼をお許しください。
私の父、税理 一男(住所 神奈川県○○市2丁目12-3、生年月日 昭和21年○月○日)は、かねてより病気療養中のところ、令和○年○月○日に永眠致しました。
この度、父の相続手続きを行うにあたり、必要な書類を集めたりしていたところ、税理 響き様も相続人であることがわかりました。
相続手続きには、税理様を含め、相続人全員の合意が必要なため、相続人の一員でいらっしゃいます税理様のご協力を頂きたく、ご連絡を差し上げた次第でございます。
父の相続に際しましては、税理様のお気持ちをお伺いしたうえで、相続人全員が納得できる形で、手続きを進めてまいりたいと存じます。
つきましては、この度の経緯と今後必要な手続きにつきまして、一度ご説明させて頂くため、税理様のお時間をお借りしたく存じます。
突然のご連絡でこのようなお願いを致しまして大変申し訳ございませんが、一度私、税理 二男(電話番号090--)までご連絡を頂けないでしょうか。
または、同封の封筒にて税理様のご連絡先の電話番号をお知らせいただければ、私からご連絡差し上げたいと存じます。
いずれかの方法で、今月中にはご連絡いただけますと幸いです。
ご多忙の折お手数をお掛けいたしますが、何卒ご協力いただけますようお願い申し上げます。
敬具
令和 年 月 日
税理 二男(故 税理 一男 長男)
郵便番号 -
神奈川県○○市○○2丁目12-3
通知を出した後の流れ

通知の手紙を出した後、本人からの電話や手紙、あるいは代理人弁護士からの連絡があり、相続手続きに協力する旨の意思表示を確認できたら遺産分割協議に入ることができます。
遺産分割協議で相続財産を分配する
・遺産に不動産が含まれる場合
通知を受けた相続人から「不動産を売却して代金で分割してほしい」と希望されることがあります。
当該不動産に誰も住んでいない場合、希望通り売却して代金で分割することもできます。しかし、誰かが自宅として利用している場合、簡単に売却できません。
不動産の売却および代金分割を希望された場合は、預貯金の額を多めに渡すか、代償分割の方法を使うなどによる解決が考えられます。
・遺産に不動産が含まれない場合
遺産に不動産が含まれない場合、各相続人の法定相続分に応じて遺産の預貯金を分配するなどの方法で解決できるでしょう。解約した預貯金などを財産を分けて、遺産分割は完了です。
「相続放棄する」との返答があった場合
被相続人の財産を不要とする場合、相続放棄が可能です。通知を出した相続人から相続放棄をする旨の連絡があったら、その方自身で相続放棄手続きを家庭裁判所にて行ってもらうことになります。
相続放棄の意思表示をした場合には、その人は相続人の地位を有さなくなるため、遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。
ただし、預貯金の解約時などでは、相続人が相続放棄をした証拠を提出する必要があり、「相続放棄受理証明書」を提出する必要があります。
相続放棄後もさまざまな相続手続きにご協力いただくことがあるため、その旨も伝えましょう。
まとめ
この記事では、相続人への通知について文例も交えながら詳しく解説しました。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、面識のない方や没交流となっている方にも連絡をする必要があります。
本記事の文例を参考に、相続人と遺産の調査を行った上で連絡をしましょう。
相続手続きを円滑に進めるためには、相続手続きの期限も押さえながら進めていく必要があります。たとえば、相続税申告は被相続人が亡くなった日を知った日の翌日から10か月以内です。
ご逝去後はさまざまな整理に追われ、忙しいですが手続き期限を遵守するためにも、遺産分割協議は早めに始めましょう。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。





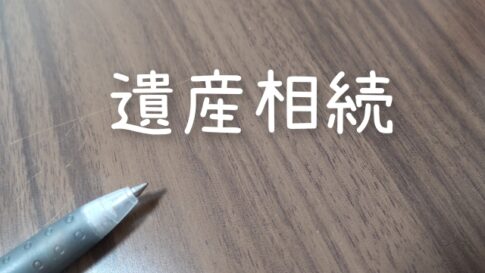
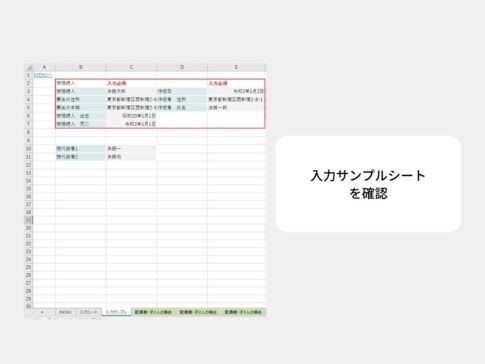




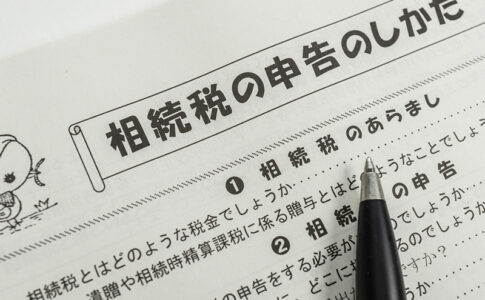







相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!