一人っ子の方がご両親を亡くされ相続を迎える際には、兄弟姉妹がいる場合とは異なる注意点があります。
特に、ご両親のうちお一方が亡くなられた後の「二次相続」では、相続税が高くなることがあるため注意が必要です。
そこで、この記事では一人っ子の方が二次相続に直面した際の注意点と、事前に知っておくべき対策方法を詳しく解説します。
スムーズな相続手続きと、将来の相続を見据えた準備のためにも、ぜひご一読ください。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
一人っ子の二次相続はどうして相続税が高くなる?

一人っ子の方の両親のどちらかが亡くなった時の相続を「一次相続」、遺されたもう一方の親が亡くなった時の相続を「二次相続」と言います。
一人っ子の二次相続では、相続税が高くなってしまうため、納税資金の用意などをしっかりと行っておく必要があります。では、どうして二次相続では相続税が高くなるのでしょうか。 その理由は主に2つ挙げられます。
1.一人っ子の二次相続は相続税率が高くなる
一人っ子の相続税率は兄弟姉妹がいる相続と比較すると高くなります。相続税率は累進課税であり、相続人1人が取得すると仮定した「法定相続分」が多ければ多いほど税率が高くなります。
つまり、相続人数が少ない相続では税率が高くなるのです。
特に二次相続では両親がご逝去されているため、相続人1名となり多くの相続財産を取得します。高額の相続財産があると、思わぬ金額の相続税が発生するおそれがあるのです。
2.二次相続では控除額が減り、使えない特例がある
相続税を納税する際には、さまざまな種類の控除や特例が用意されています。しかし、二次相続では控除額が少なくなったり、使えない特例が出てくるため相続税が高額になりやすいのです。
特に「基礎控除」や「生命保険金の非課税枠」などの控除は法定相続人の数が多いと受けられる控除額が増えます。しかし、二次相続で一人っ子の場合は受けられる控除額が小さいため、相続税が安く抑えられないのです。
二次相続時の基礎控除や特例の注意点とは

相続税が高額すぎると、生活基盤を揺るがすおそれがあるため、基礎控除をはじめとする多くの控除や特例が用意されています。
こうした控除類を使用すると、相続税が抑制できるしくみです。しかし、先に触れたように二次相続時には基礎控除や特例の使用に注意点があります。この章で詳しく解説します。
基礎控除額が一次相続時より減ってしまう
相続税の基礎控除枠は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算できます。一人っ子の場合、一次相続と二次相続では基礎控除枠に大きな違いがあります。
- 一次相続時 3,000万円+600万円×法定相続人数2名(親1名・子1名)=4,200万円
- 二次相続時 3,000万円+600万円×法定相続人数1名(子1名)=3,600万円
上記のように、二次相続では法定相続人の数は1人になってしまうため、受けられる基礎控除が減ってしまうのです。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠が少なくなる
被相続人の死亡保険金と死亡退職金にも、非課税枠が用意されており併用も可能です。
控除できる額はいずれも「500万円×法定相続人」です。
一人っ子相続の場合、法定相続人の数は1人となります。したがって、非課税限度額は以下のようになります。
- 生命保険金の非課税限度額:500万円 × 1人 = 500万円
- 死亡退職金の非課税限度額:500万円 × 1人 = 500万円
親1名が存命の一次相続と比べて、非課税枠が少なくなることを意味します。
例えば、法定相続人が親と子1名であれば、非課税限度額はそれぞれ500万円 × 2人 = 1,000万円です。
このように、一人っ子相続においては、生命保険金や死亡退職金を受け取る際にも、非課税となる金額が少なくなってしまい、相続税が高くなる可能性があります。
配偶者の税額軽減が利用できない
相続税には、配偶者が相続財産を取得した場合に相続税額を軽減できる「配偶者の税額軽減」という控除もあります。
これは、夫婦の協力によって築き上げた財産を考慮し、残された配偶者の生活を保障する目的があります。
配偶者が取得した遺産額が1億6千万円まで、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい金額までは、相続税が課税されないという非常に大きな控除枠です。
しかし、一人っ子相続の場合、子は配偶者ではないため配偶者の税額軽減は使えません。一次相続では相続税が0円だった方も、二次相続では大きな課税に直面するおそれがあるのです。
一人っ子におすすめ|相続税対策5選

一人っ子の方は、ここまでご説明のとおり受けられる相続税が高くなるおそれがあるため、できる限り早期に二次相続に向けた対策をすることが重要です。
そこで、この章では一人っ子の方向けにおすすめの相続税対策について、5つの方法をご説明します。
1.一次相続の遺産分割時に工夫をする
二次相続を見据えた対策は、一次相続の段階から始めましょう。
ご両親のどちらか一方が亡くなられた際の遺産分割協議において、将来の二次相続の負担を軽減する工夫を行うことで、二次相続の納税額を減らせます。
一次相続において、残された配偶者には「配偶者の税額軽減」が用意されているため、高額の相続財産の取得があっても、相続税を0円に抑えられる場合があります。
しかし、一次相続の段階で子にも相続財産を分けておくことで、二次相続で取得する財産を減らしておくこともおすすめです。
一次相続の際には、税理士に相談しどのように遺産分割すると二次相続時の負担が減るのか、シミュレーションをした上で遺産分割内容を決めましょう。
2.収益物件は贈与も検討する
収益を生む物件をご両親がお持ちの場合は、早めに一人っ子へ生前贈与することも対策方法の1つです。
生前贈与のメリットには以下が挙げられます。
- 早期の資産承継
まだご両親がご存命のうちに収益物件を贈与してもらうことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。 - 家賃収入の早期移転
収益物件を贈与することで、その後の家賃収入は一人っ子にできます。ご両親の相続財産が増えなくなるため相続税の節税につながります。
ただし、生前贈与には注意点もあります。不動産の贈与には贈与税が課税されるだけではなく不動産取得税や登録免許税などの費用がかかります。
さらに、暦年贈与の場合は相続開始7年以内(※)の贈与が相続税の課税対象となる財産に持ち戻して計算されるため、節税効果が薄れるおそれがあります。
収益物件の生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つですが、贈与税やその他の税金、将来的な影響などを総合的に分析した上で行いましょう。
3. 小規模宅地の特例の対象か確認しておく
相続財産の中でも大きな割合を占めることが多い土地については、「小規模宅地等の特例」で相続税を節税できる可能性があります。
本特例を適用できるかどうか、一人っ子相続においても必ず確認しておきましょう。特定居住用宅地等の特例におい被相続人と同居していたかどうかが重要なポイントとなります。
別居していた場合は、「家なき子」の要件を満たす必要があります。
家なき子の要件とは
①被相続人(親)の要件
・被相続人に配偶者がいないこと
・亡くなった時点で、被相続人に法律上の配偶者がいない(死別・離婚を含む)
被相続人と同居していた相続人がいないこと
・相続人の中に、相続開始時に被相続人と同居していた人がいないこと(相続放棄した人も含む)
②相続人の要件(一人っ子)
・相続開始前3年以内に、ご自身またはご自身の配偶者、三親等内の親族が所有する家屋に居住したことがないこと
・相続開始時にご自身が居住している家屋を過去に一度も所有していたことがないこと
・相続した宅地を、相続税の申告期限まで引き続き所有していること
4.相次相続控除を検討する
こちらは相続開始後の対策になりますが、二次相続がご両親のいずれかが亡くなられた一次相続から10年以内である場合、「相次相続控除」の適用が検討できます。
相次相続控除とは、被相続人が亡くなる前の10年以内にその被相続人が相続または遺贈によって財産を取得し、その際に相続税が課税されていた場合に、今回の相続(二次相続)で相続人が納める相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
短期間に相続が繰り返された場合の相続税負担を軽減できるしくみです。
5.納税資金対策をしっかり行う
相続税は、原則として現金一括納付が求められます。一人っ子相続の場合、兄弟姉妹がいる場合に比べて相続財産を分け合う必要がない一方で、多額の納税資金を一人で準備しなければならないという負担があります。
事前の納税資金対策を怠ると、相続税の納付期限までに資金が準備できず、滞納という事態を招きかねません。ご両親とともに、早めに相続税シミュレーションを行い、納税資金の準備を進めておきましょう。
一人っ子相続は、家族仲良く対策を始めよう
一人っ子の相続人は、将来的に相続手続きを一人で行う可能性が高く、相続税も高くなる傾向があるため注意が必要です。
早めに相続税の専門家である税理士のサポートを受け、万全の準備をしておくことが、スムーズな相続とご自身の将来の安心につながります。まずはお気軽に横浜市の響き税理士法人へご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。





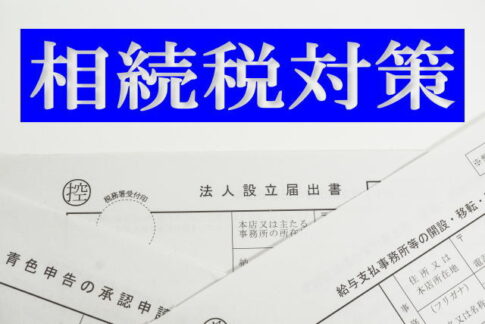
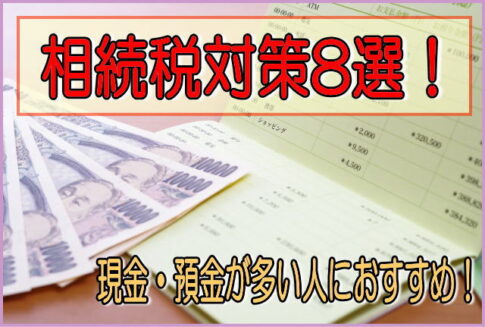

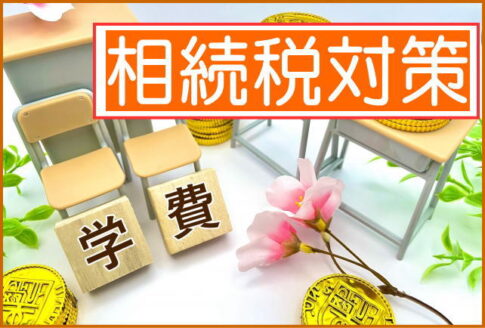


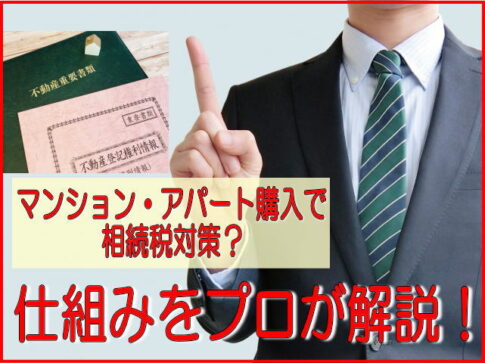
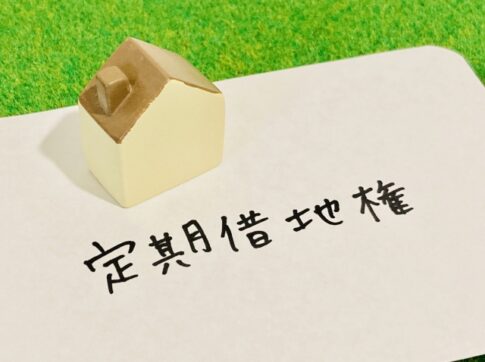






相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!