相続税の課税は不動産や有価証券などはもちろん、ご自宅に保管されている「現金」や金融機関に貯蓄している「預金」も対象になります。
被相続人が必ずしも生前に家族へ現金・預金の保管場所を告げているとは限らないため、相続開始後は相続人が適切に調査を行う必要があります。
漏れたまま相続税申告をしたり、相続税申告事態を行わなかった場合は税務調査を受け、ペナルティが課せられるリスクもあるため注意が必要です。
そこで、本記事では現金・預金がたくさんある人向けに、おすすめの相続税対策や注意点を解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
現金・預金の相続時に押さえておきたい注意点

現金や預金は多くの人がお持ちであるため、相続時に承継することが多い資産です。
では、これらの資産を承継する際に押さえておきたい注意点とはどのようなものでしょうか。この章では現金・預金の相続時の注意点を2つに分けて解説します。
1. 現金・預金の評価方法に注意
現金や預金を相続税申告時に評価する場合は「額面」どおりに評価を行います。わかりやすく言うと、1,000万円の現金があったらそのままの金額が課税対象となるのです。
不動産の場合は一般的に「時価」の評価よりも安くなることが多いですが、現金や預金はそのままであるため不動産と比較すると相続税評価時に高い課税が課される可能性があります。
なお、現金・預金の相続税評価額は以下のように評価が行われます。
| 財産の種類 | 評価方法 |
| 現金・普通預金 | 相続開始日の残高で評価する |
| 定期預金 | 相続開始日の残高および既経過利息(税引後の利息) |
| 外貨預金 | 相続開始日の残高および既経過利息に対して、相続開始日に公表される為替レートを使って換算する |
2.相続人が把握していない現金・預金に注意
被相続人が生前、家族に財産の全容を伝えていなかった場合、相続人は被相続人がいくら現金や預金を持っていたのか正確に把握することが困難です。
特に以下のようなケースでは、把握漏れが発生しやすくなります。
- 長年使用していない口座:被相続人が過去に開設し、その後ほとんど使用していなかった
- タンス預金::自宅のタンスなどに保管し、家族に知らせていない場所で現金を貯蓄していた
- 名義預金:実質的には被相続者の財産であるにもかかわらず、配偶者や子どもの名義で開設されている預金口座(名義預金)
- インターネットバンキング::オンライン上の口座の残高は、通帳が存在しないことがあり、把握が遅れやすい
- 貸金庫内の現金::家族に知らせていない金融機関の貸金庫に現金が保管されている場合、相続人の把握が遅れやすい
相続人が把握していない現金・預金が存在した場合、相続税の申告から漏れてしまう可能性があり、税務署からペナルティが課されることがあります。
また、相続人の遺産分割協議からも漏れてしまう可能性があり、誰が漏れた現金・預金を相続するのか揉めてしまうおそれもあります。
現金・預金の相続はしっかりと対策しよう!おすすめの8つの方法とは

現金や預金の相続を迎える前に、しっかりと家族が協力し合って相続税対策を進めておくことが大切です。
そこで、本章では現金・預金の相続税対策について「贈与」や「生命保険」に焦点を当てて詳しく解説します。8つの方法をご紹介しますのでぜひご一読ください。
1.暦年贈与
多くの人が利用している「暦年贈与」を使って、相続開始前に現金や預金を家族へ承継します。
この方法なら、年間110万円の基礎控除額内で贈与していけば贈与税も課税されません。相続時の現金や預金を減らす効果があり、相続税対策としても有効です。
110万円を超える贈与をしたとしても、110万円を超えた部分にのみ贈与税が課税されます。
ただし、注意すべき点もあります。贈与者(親など)が死亡した場合、死亡日以前7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります(2024年1月1日以降の贈与から段階的に加算期間が延長され、最終的には7年となります)。
2.住宅取得等資金の贈与の特例
親や祖父母など直系尊属から、子や孫への住宅の新築、取得、または増改築のための資金の贈与について、一定の要件を満たす場合に贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の贈与の特例」と呼ばれる制度があります。
この特例は、2026年12月31日までの贈与に適用されます。非課税限度額は、住宅の種類によって異なります。
省エネ等住宅等:1,000万円
上記以外の一般住宅:500万円
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
また、贈与を受けた資金は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得資金等に使う必要があるため注意が必要です。
お子様やお孫様が住宅の取得を検討されており、資金援助をお考えの場合、この特例を検討することで、贈与税の負担を軽減できる可能性があります。ただし、適用要件が細かく定められていますので、事前に税理士などの専門家にご相談されることが大切です。
参考URL 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
3.教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫に対しては「教育資金贈与の非課税制度」という制度があり、一定の要件を満たせば1,500万円まで(うち、学校等以外の教育資金に充てられるのは500万円まで)の贈与が非課税となります。
教育資金一括贈与の特例を利用する場合、金融機関に専用口座を開設し、教育資金であることを証明する領収書やレシートを金融機関に提出します。
なお、受贈者(子や孫)が30歳に達した時点で口座に残余資金がある場合、原則としてその残っている資金に対して贈与税が課税されます。
この制度の適用期限は、2026年3月31日までとなっており、今後の延長は未定です。
4.結婚・子育て資金の一括贈与
18歳以上50歳未満の子や孫(※贈与年の1月1日時点)に結婚・子育て資金を一括贈与する「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度もあります。
一定の要件のもと、1,000万円まで(結婚資金に充てられるのは300万円まで)の贈与が非課税となります。
教育資金と同様に贈与の使用目的は限定されており、金融機関に特別な口座を開設し、領収書や使用証明書を提出して、利用の都度、引き落としを行う必要があります。
贈与を受けた年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この非課税措置の適用を受けることができません。加えて、以下2点に注意が必要です。
- 贈与を受けた人が50歳に達すると、口座の残高に対して贈与税が課税される
- 贈与した人が亡くなると口座に残額がある場合は、その残額が相続財産に加算され、相続税の課税対象となる
この制度の適用期限は、2027年3月31日までとなっています。
参考URL 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
5.夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対し居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除することができます。
「夫婦間贈与の特例」という制度で、適用要件は以下のとおりです。
・贈与をした年の1月1日において婚姻期間が20年を経過している夫婦であること
・贈与された居住用不動産またはその取得資金が、受贈者(贈与を受けた配偶者)の居住の用に供されるものであること
・居住用不動産の贈与の場合、受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
・居住用不動産を取得するための金銭の贈与の場合、受贈者がその金銭により居住用不動産を取得し、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住する見込みであること
この控除は、同一の配偶者間では生涯に一度しか適用できず、相続時精算課税制度との併用もできません。
参考URL 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
6.日頃の生活費や教育費としての贈与
特別控除や各種非課税措置を利用する以外にも、扶養義務者から被扶養者への一定の贈与は、贈与税が課税されないという原則があります。日常生活に必要な費用や教育費として贈る場合は贈与税が課税されません。
子や孫を扶養する義務のある両親や祖父母などは、生活費や教育費などの費用を負担することが一般的であり、贈与対象にはなりません。ただし、多額の金銭を贈与した場合は、贈与税の対象となるので注意が必要です。
7.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)から、特定の受贈者(18歳以上の子・孫など)への贈与について、2,500万円の特別控除枠が設けられている贈与方法です。
相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算・納税するため、贈与時の負担を軽減できます。
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間の基礎控除110万円が創設されました。これにより、年間110万円までの贈与については贈与税がかからず、相続時の加算対象にもなりません。
特別控除枠については、基礎控除後の贈与額が、累計2,500万円に達するまでは贈与税はかかりません。基礎控除後の贈与額が累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度は、生前にまとまった財産を贈与したい場合に有効な選択肢となり得ますが、一度選択すると原則として暦年贈与に戻れないなどの注意点もあります。
8.生命保険への加入
生命保険金には相続時に非課税枠が設けられています。相続税を計算する際、被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金には、以下の非課税限度額まで控除できるしくみです。
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
の非課税限度額を超える部分の生命保険金は、相続税の課税対象となります。
相続人が相続放棄をしたとしても、生命保険金の非課税限度額の計算における法定相続人の数には含まれませんが、生命保険金の受取人となっている場合は、その保険金自体は相続放棄の影響を受けずに受け取ることができます。
生命保険は、相続対策として有効な手段の一つですが、加入する保険の種類や契約内容、受取人の指定などによって、相続税の取扱いが異なるため注意が必要です。
現金・預金の生前贈与時の注意点

生前贈与などの相続税対策は、大切な人への資産承継の有効な手段の一つです。しかし、適切な手続きを踏まずに行った生前贈与は、贈与税が課税されるだけでなく、相続税の計算に影響を与える可能性もあります。
本章では、現金・預金の生前贈与を行う際の重要な注意点を3つ解説します。
生前贈与には双方の合意が必要
生前贈与が法律上の「贈与」として認められるためには、以下の2つの基本的な要件を満たす必要があります。
①贈与者と受贈者の合意
財産を与える人(贈与者)と財産を受け取る人(受贈者)の双方が、贈与の意思を持ち、その内容について合意していることが必要です。
例えば、祖父母が幼い孫に財産を贈与したいと考えた場合、孫が贈与を認識し同意することは困難です。
この場合、親権者などの法定代理人が孫を代理して贈与を受ける意思表示を行うことで、贈与が成立します。単に祖父母が孫名義の口座に入金しただけでは、孫やその親が贈与と認識していないため、名義預金とみなされる可能性が高いでしょう。
②受贈者による自由な利用
贈与された財産は、受贈者が自身の判断で自由に管理・処分できる状態にあることが求められます。たとえ親が子どもの名義で預金口座を開設し入金していたとしても、通帳やキャッシュカードを親が管理し、子どもが自由に引き出すことができない状態であれば、贈与とは認められない場合があります。
贈与として成立するためには、受贈者が財産を支配・管理できる状態になっていることが重要です。要件を満たさない場合、税務上「贈与」として扱われず、贈与者の死亡後に相続財産として課税されたりするリスクがあります。贈与を行う際は、双方の明確な合意に基づき、受贈者が財産を自由に管理できる状態にすることが不可欠です。
生前贈与の証拠を残すこと
現金を直接手渡しで贈与した場合、その事実を客観的に証明する記録は残りません。
税務署の調査が入った際、基礎控除(年間110万円)以内の贈与であることを明確に証明できなければ、贈与税が課税される可能性があります。
このような事態を避けるためには、贈与の証拠を適切に保管・記録することが重要です。銀行振込の活用: 現金を手渡すのではなく、銀行振込を利用することで、誰が・いつ・いくら贈与したのかという客観的な記録が金融機関に残ります。
また、贈与契約書の作成・保管: 贈与者と受贈者の間で、贈与の合意内容(贈与者、受贈者、贈与財産、贈与日など)を明記した贈与契約書を作成することも確実な証拠となります。少額の贈与であっても、書面で残しておくことがおすすめです。
生前贈与は早期に始めること
贈与をした被相続人(親や祖父母など)が亡くなった場合、相続開始前7年以内に行われた生前贈与は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります(2024年1月1日以降の贈与から段階的に加算期間が延長されています)。
例として親から子へ毎年100万円の暦年贈与が行われていた場合、親が亡くなった際には、過去7年間の贈与額(段階的に加算期間が延長)が相続財産に加算されて相続税が計算されることになります。
したがって、相続税対策として生前贈与を検討する場合は、加算期間を考慮し、できるだけ早い段階から計画的に行うことが重要です。
まとめ
相続税対策としての生前贈与は有効な手段ですが、現金の手渡しなど贈与の事実が不明確な形で行うことは、税務上のリスクを高めます。
贈与を行う際は、銀行振込を利用したり、贈与契約書を作成・保管するなど、客観的な証拠を残すように心がけましょう。
また、生前贈与加算のルールを理解し、早期からの計画的な贈与を検討することが重要です。贈与税には、基礎控除に加えて、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与など、豊富な非課税措置や特例が存在します。これらの特例も活用できないか検討し、ご自身の状況に合わせた最適な贈与プランを立てましょう。
横浜市の響き税理士法人では、相続税対策のご相談も歓迎しています。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

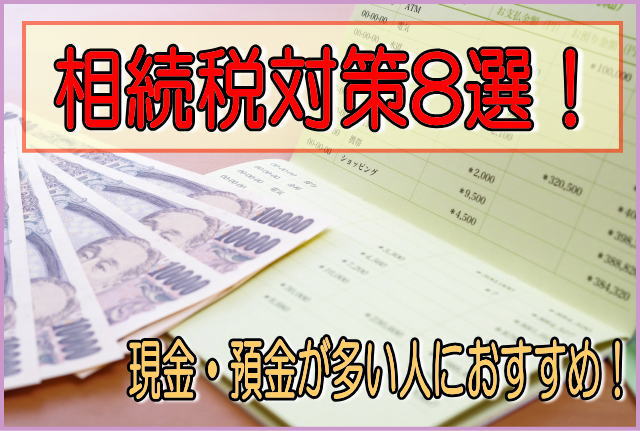

















相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!