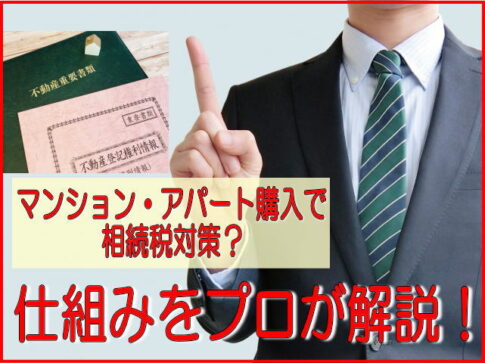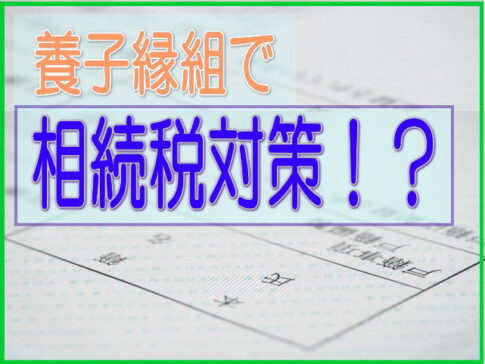ご自身が亡くなられた後に、特定の人に財産を遺す方法として「死因贈与」と呼ばれる方法があります。
死因贈与とは贈与者が亡くなったときに効力が生じる贈与契約のことです。たとえば「自分が死んだら、この家を長男に贈与する」というような約束を生前に交わすことを意味します。
遺言書に似ていますが、法的には「契約」であるため、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。では、死因贈与に「契約書」は必要なのでしょうか。
本記事では、契約書を作るメリットや記載すべき項目、不動産を含む死因贈与の記載方法などをわかりやすく解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
死因贈与に契約書は必要?

大切な方へ財産を遺したい、と死因贈与を検討される方は多いでしょう。では、実際に死因贈与を交わす場合には書面による契約書は必要なのでしょうか。本章で詳しく解説します。
必須ではないが作成がおすすめ
結論から言うと、死因贈与契約書は法律上は必ずしも作成しなくてもよいものです。
民法上、死因贈与は口頭でも成立するとされており、「亡くなったらこの家をあげる」と口約束で伝えた場合でも契約自体は有効です。
しかし、実際には「死因贈与契約書」を作成することがおすすめされています。口頭だけでは内容を忘れてしまったり、契約内容を誤るおそれもあるためです。
契約書はトラブルの回避にもつながる
死因贈与契約書を作っておくことは、ご逝去後の争いを防ぐ効果もあります。契約書を残しておくことが、死因贈与の証拠になるためです。
- 特に次のようなトラブルを回避できます。
- 他の相続人から「本当に合意していたのか」と疑われる
- どのような贈与内容だったか誤りなく手続きができる
- 不動産登記や相続税などの税務手続きでトラブルになりにくい
契約書の形で文書にしておけば、贈与者と受贈者の意思が明確になり、贈与内容・時期・条件などを具体的に残せます。相続税申告が必要となった場合に、資料に生かすことも可能です。
死因贈与の契約書の書式・様式は自由
死因贈与契約書には、法的に定められた書式や様式がありません。
契約書としての体裁(贈与の合意内容、日付、署名捺印など)が整っていれば、手書きでもパソコン作成でも問題がなく、遺言書よりも自由に作成できます。
ただし、重要なのは「贈与の合意があったことが客観的にわかる」ようにしておくことです。
後から「贈与者の同意なく勝手に作成された」と否定されないよう、文面には「死因贈与契約であること」を明記しておくと安心です。
死因贈与の契約書に記載すべき6つのポイント

死因贈与契約書を作る時は、一体どのような内容を記載するとよいでしょうか。これから作成される方向けに、死因贈与契約書に記載すべき5つのポイントをわかりやすく解説します。
1.公正証書での作成がおすすめ
死因贈与契約書は、公証役場で「公正証書」にしておくことがおすすめです。
公正証書とは、公証人(元裁判官や検察官など)が当事者の依頼を受けて作成する公文書です。死因贈与契約書を公正証書で作成しておくと次のようなメリットがあります。
- 偽造・改ざん、無効になる心配がない
- 契約の成立を公的に証明できる
- 紛失・破損しても公証役場で正本・謄本を再発行できる
- 不動産登記・税務申告時の証拠として有効
また、不動産を死因贈与する場合公正証書にしておけば、贈与者死亡後に受贈者が単独で名義変更の登記申請を進められるため、手続きがスムーズです。
2.死因贈与の合意を残す
死因贈与は贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)が生前に贈与契約を交わし、贈与者が亡くなった後に贈与の効力が発生する贈与契約です。
そのため、契約書を作る際には贈与者・受贈者双方の「合意」が交わされている必要があります。
「贈与者〇〇は、自己の死亡を原因として、次の財産を受贈者△△に贈与することを約する。」
といった一文を冒頭に記載しましょう。
2.贈与する財産を書く
不動産・預金・株式・車など、対象となる財産を特定して記載します。
特に不動産の場合は、登記簿上の「所在」・「地番」・「家屋番号」まで正確に記載してください。
例として、預貯金であれば「○○銀行○○支店、普通預金 口座番号×××××」といった形で明確にしておきます。
3.執行者の指定
死因贈与の実行をスムーズに進めたい場合、執行者(死後に手続きを行う人)を指定することもおすすめです。(※)
特に不動産を死因贈与する場合、執行者を指定しておくと不動産の名義変更登記時に執行者の印鑑証明書と実印で進められます。
指定していない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要のため注意が必要です。
弁護士や行政書士、信頼できる親族などを指名しておくと、死後の名義変更や税務手続きが円滑に行えます。
(※)執行者の指定は義務ではありません。
4.契約にかかわる当事者名を示す
死因贈与契約書には贈与者と受贈者の氏名・住所・生年月日を明記します。誰が贈与し、誰が受け取るのか漏れなく記載しましょう。
5.捺印・割印
契約書は贈与者と受贈者がそれぞれ1つずつを保管できるように2通作成します。
各ページに割印をしておくことで、改ざん防止にもなります。
また、贈与者・受贈者がそれぞれ捺印します。印鑑は認印でも問題はありませんが、実印の捺印と印鑑証明書の添付がおすすめです。
不動産の仮登記をする場合の記載方法とは

死因贈与では不動産を贈与することも可能です。死因贈与の場合、不動産を事前に「仮登記」できます。では、不動産の死因贈与時にはどのように契約書を作るのでしょうか。本章で詳しく解説します。
死因贈与なら不動産の仮登記が可能
不動産の死因贈与契約では、贈与者の生前に「仮登記」をしておくことが可能です。贈与者の死亡後に確実に所有権移転が行われるようにするための手続きで、受贈者の権利を保護する効果があります。
ただし、仮登記を行うためには、
- 死因贈与契約書
- 納税通知書もしくは評価証明書
- 登記原因証明情報
- 踏力免許税
- 印鑑証明書
などの提出が必要です。登記に関するお悩みがある場合は、司法書士への相談が望ましいでしょう。
不動産の死因贈与契約書の文面例
不動産を死因贈与する場合には、以下のような文面を記載します。(所有権移転登記手続の部分のみ記載)
| 第●条 (所有権移転登記手続) 甲および乙は、本件不動産について、乙のために始期付所有権移転仮登記をするものとする。甲は、乙が上記仮登記申請手続をすることを承諾した。 |
この他に、物件目録などへの記載によって登記簿上の表示に基づいて不動産に関する情報を正確に記載することが大切です。
負担付死因贈与の記載方法とは
死因贈与には、受贈者が一定の負担を果たすことを条件に、財産を贈与する「負担付死因贈与」と呼ばれる贈与方法もあります。本章では負担付死因贈与の記載方法について解説します。
負担付死因贈与とは
死因贈与には「負担付死因贈与」という形もあります。この方法は受贈者が一定の義務(負担)を果たすことを条件に、財産をあげるという契約です。たとえば次のようなケースです。
- 「生前の介護・看護を条件に、死後に自宅を贈与する」
- 「大切に飼育していたペットを引き続き飼育することを条件に、財産を譲る」
単なる贈与ではなく、受贈者に負担が生じるため双方がしっかりと話し合いを重ねた上で契約を交わすことがおすすめです。 このような条件付き契約の場合は、文面で明確に負担内容を示すことが重要です。
負担付死因贈与契約書の文面例
負担付死因贈与の契約書には、以下のような文面を記載します。(負担付の部分のみ記載)
| 第●条 乙は、本件贈与を受ける負担として、●●をしなければならない。 |
受贈者(契約書上は乙)の義務の範囲・期間・具体的な内容をできる限り明確に記載します。
知っておきたい死因贈与時の税金

贈与税ではなく相続税が発生する
死因贈与は通常の生前贈与と異なり、贈与の効力は贈与者の死亡時に発生します。そのため、税金の扱いは贈与税ではなく相続税の対象です。
死因贈与で財産を受け取る場合、他の相続財産と同様に相続税の申告が必要です。なお、基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)やその他の控除・特例などの相続税の優遇措置を適用できます。
不動産の登記時は贈与として扱う
死因贈与では不動産の名義変更(登記)を行う際の税金に注意が必要です。死因贈与契約によって不動産を受け取る場合、登記上は「贈与」に該当するため、登記原因は「死因贈与」として手続きを行います。
この時課税されるのは、相続税だけでなく登録免許税(相続よりも税率が高い)や不動産取得税が発生します。
登録免許税:相続は固定資産税評価額の0.4%、死因贈与は固定資産税評価額の2.0%
不動産取得税:相続では非課税だが、死因贈与は課税対象
そのため、税負担を軽くしたい場合は、遺言による相続のほうが有利なケースもあります。
まとめ
死因贈与は「確実に財産を渡したい」という思いを形にできる便利な制度ですが、契約の性質が「贈与」である点を理解しておくことが重要です。
契約書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブル防止や登記・税務手続きを円滑に行うためにも、書面で残すことがおすすめです。特に不動産を含む場合は、公正証書で作成しておくことで法的な証明力が高まり、相続人間の争いを防ぐ効果があります。
死因贈与は、遺言書よりも自由度が高く、確実に意思を反映できる契約ですが、正しい知識と準備がなければ思わぬトラブルや税負担が生じる可能性もあるため注意が必要です。まずはお気軽に響き税理士法人へご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。