
相続税対策につながる生前贈与に関心を持つ方が増えています。しかし、気になるのはやはり「贈与税」でしょう。
では、贈与税とは誰が、どんな時に支払うものなのでしょうか?
そして、贈与した側である「贈与者」は、贈与の事実を税務署へ確定申告を通して報告する必要はあるでしょうか。
贈与方法について正しく知っておかないと、思わぬ落とし穴に直面してしまうことがあります。
そこで、本記事では贈与について「贈与した側」の方向けに注意点を解説します。確定申告の有無についても触れますので、ぜひご一読ください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
贈与税とは?必ず課税される?

個人から個人へ、財産を贈与する場合には税金が課税されることがあります。この時に発生する税金を「贈与税」と言います。では、贈与税はどのような贈与に対して行われるのでしょうか。
年間110万円の贈与を超えると課税される
贈与税は贈与したら必ず課税されるものではありません。贈与者(贈与する人)から受け取る人(受贈者)へ、年間110万円を超える財産が贈与された時に、贈与税が課税されます。この110万円とは「暦年贈与」の基礎控除枠のことであり、110万円を超えた時に課税される贈与税は受贈者が支払います。
相続時精算課税制度を利用すると贈与税はどうなる?
贈与の方法には、上記の暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」と呼ばれる方法もあります。この方法は60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する方法で、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。
制度利用に関しては以下の記事もご一読ください。
贈与後は贈与した側に確定申告は必要?

財産を贈与した際の贈与税は、財産を贈与した側ではなく、受け取った受贈者に対して課税が行われています。
では、贈与税の課税時に贈与した側は確定申告等の方法で税務署に申告する必要はあるのでしょうか。この章で解説します。
贈与した側の確定申告は「不要」
贈与した側は、ご自身の財産を渡す側に過ぎません。そのため、贈与税が課税されることはありませんので、確定申告等の報告は不要です。
しかし、贈与を受け取る方は贈与が行われた際に注意が必要です。
贈与を受けた側は「贈与税」の申告を行うケースがある
贈与によって財産を受け取った受贈者は、贈与の実態によっては「贈与税の申告」が必要なケースがあります。ただし、贈与税の申告は「確定申告」ではありません。ここで整理しましょう。
贈与を受け取っても、所得税の確定申告は不要
贈与で財産を受け取ると、所得が増えると感じるかもしれません。しかし、贈与は確定申告ではなく、贈与税の申告によって税務署へ報告を行います。
ただし、法人から財産を受けた場合は、贈与税ではなく「所得税」がかかるので注意しましょう。
贈与を受けた側が贈与税の申告をするケース

贈与を受けたとしても、必ずしも「贈与税の申告」が必須なわけではありません。贈与税の申告が必要となるのは、以下の3ケースです。
- 暦年贈与で年間110万円を超える生前贈与を受けた
- 相続時精算課税制度をの初年度 および、相続時精算課税制度を利用し年間110万円を超える贈与を受け取った
- 贈与税の特例を使って生前贈与を受けた
贈与税の申告が必要となった場合「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」に受贈者が住む地域を管轄する税務署へ申告を行います。この日程は確定申告の日程と同じですが、手続きを混同しないように注意しましょう。
③については注意点がありますので、後述いたします。
押さえておきたい贈与税がかからない財産
贈与税は現金や預貯金だけに課税されるものではなく、原則として個人からもらったすべての財産に課税されます。たとえば、不動産も課税対象です。しかし、例外として下記の9種類の財産については贈与税がかかりません。
日常生活に必要な生活費や社会通念上相当と認められる香典など、意外と多くの財産に贈与税がかかりません。ただし、不安がある場合はあらかじめ贈与の専門家である税理士に相談することがおすすめです。
贈与税の税率はいくら?

贈与税が発生した場合、どのように計算し、納付に臨む必要があるでしょうか。この章では暦年贈与と相続時時精算課税制度の2つの課税方法について、税率を詳しく解説します。
暦年贈与の税率
暦年贈与は毎年110万円の基礎控除額があり、110万円を超えた部分に税率をかけて納税額を算出します。
贈与した財産が大きいと、税率も連動して増える「累進課税」方式が採用されているため注意が必要です。
①一般贈与財産用
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例として、兄弟間・夫婦間・親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| <一般贈与財産用>(一般税率) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除後の
課税価格 |
200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm】
1年間のうち、贈与された財産が110万円以内であれば、贈与税はかからないため贈与税の申告は不要になります。また、この110万円は「財産を受け取る側」につき控除される金額です。財産を渡す人(贈与者)ごとに110万円の控除が認められているものではなく、複数の贈与者から贈与を受ける場合は110万を超えたら申告が必要です。
②特例贈与財産用
贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算は「特例贈与財産用」を採用します。
なお、2022年の民法改正により、対象となる受贈者の年齢が20歳から18歳へ変更されています。
直系尊属から財産を受け取るほうが、受けられる控除額は大きくなります
|
<特例贈与財産用>(特例税率) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除後の
課税価格 |
200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
【出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm】
相続時精算課税制度の税率
相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があるため、暦年贈与よりも大きな控除額がある点が特徴の1つです。また、2024年の法改正により、年間110万円までの基礎控除枠も増えました。
贈与額が2,500万円を超えると、超えた部分に対して一律で税率20%で贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度は贈与税の非課税枠が大きいものの、相続が発生した時に「相続税」として相続財産に加算されます。したがって、納税の先送りの側面があるのです。
また、相続時精算課税を選択した贈与者が「やっぱり暦年課税に戻したい」と思っても、変更できません。
相続時精算課税制度は利用を決めた初年度に税務署の申告も必要です。申告漏れが起きると特別控除ができなくなり、一律20%の贈与税が課税されます。
延滞税などもさらに課税されてしまうため、慎重に手続きを進めましょう。
贈与税がかからなくても申告が必要なケース

贈与方法は主に先に触れた「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの方法がありますが、贈与税がかからなくても、申告が必要なケースがあります。ご説明の前に、まずは贈与税の非課税枠がある「贈与税の特例」をご紹介します。
贈与税の特例一覧
| 贈与方法 | 非課税枠 | 主な条件 | 主な契約終了時の注意点 |
| ①住宅取得資金の贈与 | 1000万円もしくは500万円まで非課税 | 受贈者の年齢は18歳以上、年収は2,000万以下 | なし |
| ②教育資金の一括贈与 | 1500万円もしくは500万円まで非課税 | 受贈者は30歳未満、年間所得1,000万円以下 | 受贈者が30歳の時点で贈与された財産が残っていたら贈与税対象。贈与者が死亡した時点で相続税が課税される可能性がある(対象外の方あり) |
| ③結婚・子育て資金の一括贈与 | 子育て資金1000万円、結婚資金300 | 受贈者は18歳以上50歳未満。年間所得1,000万以下 | 受贈者が50歳の時点で贈与残額があったら贈与税対象。贈与者が亡くなったら相続税が課税。 |
| ④贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 2000万円まで非課税 | 婚姻期間20年以上 | なし |
「贈与税の特例」の注意点
上記の贈与については非課税枠がありますが、たとえ贈与税が0円であっても申告が必要です。
例として、教育資金の一括贈与を利用する場合は受贈者が金融機関で「教育資金口座」を開設した上で、金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を提出しなければなりません。また、贈与税の特例の中には非課税対象期間の終了時に使い残された贈与財産があれば、贈与税の課税対象となり贈与税申告が必要なものもあります。
贈与税の特例は手続きや、利用終了時が複雑であるため利用率が低いとされます。しかし、暦年贈与や相続時精算課税制度との併用ができるため、十分に検討の上で利用することもおすすめです。
まとめ
本記事では贈与した側の確定申告の有無についてを中心に、詳しく解説を行いました。贈与者側には確定申告の義務はないものの、受贈者側には必要に応じて贈与税の申告が必要です。
また、贈与税の特例については手続きそのものが複雑なため、利用時には慎重に要件や書類を確認するようにしましょう。
横浜市を中心に相続・贈与の専門家として多くのご相談に対応している響き税理士法人では、相続税対策を見据えた贈与のご相談にも対応しています。いつでもお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。



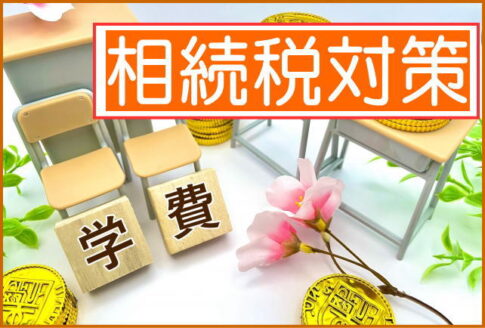



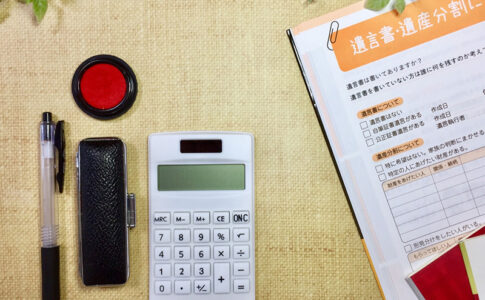












贈与税がかからない9つの財産
①法人からの贈与により取得した財産
②扶養義務の家族間で、生活費や教育費として贈与により取得した財産
③公益事業用の財産
④特定公益信託から交付される学術奨励金または学資金
⑤心身障害者扶養共済制度にもとづいて支給される給付金の受給権
⑥選挙の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭など
⑦特定障害者への特定障害者扶養信託契約にもとづく信託受益権
⑧相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産
⑨社交上必要と認められる香典、祝物、見舞金など
参考URL 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合