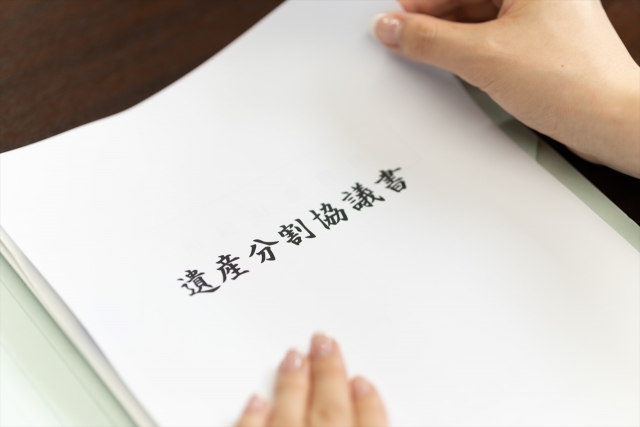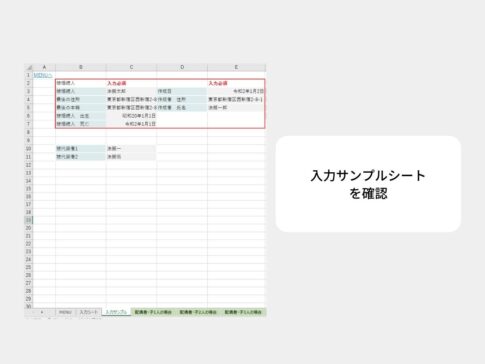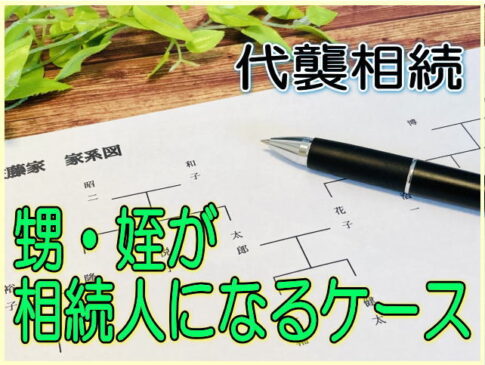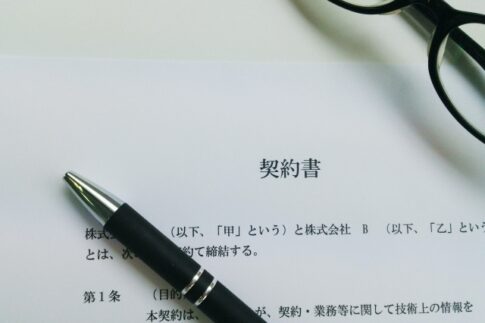公正証書遺言は、いくつか種類がある遺言の中でも証明力や執行力が強い遺言です。故人の遺志がしっかりと示されているため、遺言の内容通りに遺産の分割をする事も多いでしょう。実は、公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書は必要ないというパターンが多くあります。
では、何故、公正証書遺言があると遺産分割協議は必要ないのでしょうか?
そこで今回は、公正証書遺言がある場合に遺産分割協議書が必要ない理由について、公正証書遺言の持つ役割や、遺産分割協議の意義も交えて、解説していきます。遺産分割協議が必要なくなる事は、相続人間のトラブルを防ぐというメリットにも繋がります。
後半には、よりスムーズに相続手続きを行うために、注意するべき点もお伝えしていくので、相続に不安を感じる方はぜひ、最後まで読んでくださいね。
目次
公正証書遺言があれば、相続トラブルを抑制できる可能性が高い
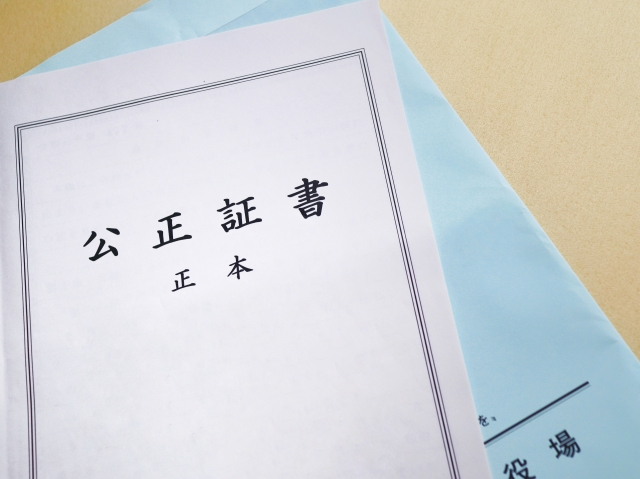
先述の通り、公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議書は必要がない事例が多いです。相続でトラブルになる原因は、相続人同士での財産分与が上手くいかないというものが多くあります。
もちろん、遺言により被相続人が一方的に財産分与を決めてしまう事も、相続争いの火種になる可能性も否定できないところではありますが、遺産分割協議がなくなる事で、相続トラブルの発生を抑制できる可能性がある事は確かでしょう。
つまり、公正証書遺言は相続トラブルを防ぐのに、とても重要なカギになるのです。
遺産分割協議書が必要ない理由は?

公正証書遺言がある時に遺産分割協議書が必要ない理由は「遺産の分け方がすでに決められている」からです。
遺言と遺産分割協議書はどちらも、遺産の割合や分け方について記しています。公正証書遺言により、遺産の分け方が決まっているので、遺産分割協議は行う必要がなく、当然、遺産分割協議書も不要になるという事です。とはいえ、公正証書遺言や遺産分割協議書について、漠然と認識できていても、しっかりと理解できているという方は少ないのではないでしょうか?
では、「公正証書遺言」と「遺産分割協議書」について、それぞれ見ていきましょう。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人の立ち会いのもと作成する遺言の事をいいます。公証人とは、法務大臣に任命された準国家公務員で、裁判官や検察官などを経験した事のある法律の専門家が務めます。
法律のプロを交えて作成する事ができるため、法律的に見て問題のない遺言内容になる事はもちろん、自分で作成した遺言では要件を満たせず遺言が無効になる可能性がありますが、公正証書遺言であればその心配がありません。
作成後の遺言は公証役場で保管されるため、誰かに書き換えられたり、破棄されたりという恐れもあり得ません。遺言の中で、もっとも安心して作成、保管ができるのが公正証書遺言と言えるでしょう。
遺産分割協議書とは?
「遺産分割協議」とは相続人全員で遺産をどのように分けるかを決める事で、それを記載した書面の事を「遺産分割協議書」と言います。
遺産の割合や分け方について、遺言では故人が決める一方で、遺産分割協議書は相続人たちが取り決めるものです。書面に残す事で、遺産の割合や分け方について、相続人全員が同意したという証明にもなります。
公正証書遺言がある場合の相続手続きの流れ
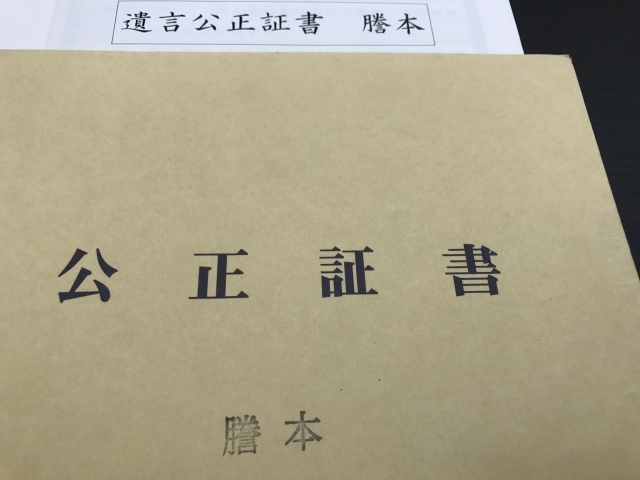
続いて、公正証書遺言が残されている場合の相続手続きの流れをご紹介します。大きく分けて3つのプロセスがあります。
①公正証書遺言を探し、内容を確認
まずは、故人の遺品の中から公正証書遺言を探し、遺言内容を確認します。
公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり開封時に検認の手続きが必要ないため、見つけた時点で開封が可能です。もし、遺言が見つからなければ、最寄りの公証役場に行くと、遺言を探してもらえ、謄本を受け取れます。
②遺言の内容を相続人全員で確認し、財産分与を決定
遺言に記載された財産分与の方法で問題がないか、相続人全員で確認します。
相続人が遺言に記載された通りの内容で財産を分ける事に納得すれば、そのまま次の手続きに進みます。相続人の全員が遺言での財産分与に同意できず、遺産分割協議をもって変更したい場合には、後程紹介する流れで手続きを進めていく事になります。
③遺産の名義変更を行う
公正証書遺言もしくは遺産分割協議によって、財産分与の方法が決まったら遺された財産の名義変更を行います。
預貯金を相続した場合は、各金融機関により名義変更の手続き方法や必要書類が異なるので、それぞれの金融機関に問い合わせましょう。
不動産は法務局で所有権移転の登記を行います。手続きには本人確認や戸籍謄本などの書類が必要となりますが、公正証書遺言に従う場合は公正証書遺言、遺産分割協議で取り決めたなら遺産分割協議書が必要です。
相続税の納付が必要になる場合は、相続税納付の手続きを行います。
公正証書遺言での分け方に納得できなければどうすればいい?

公正証書遺言に記載されている分け方での財産分与では、相続人同士の折り合いがつかず、上手くいかない事もあるでしょう。
このようなパターンでは、実際に遺言に記載されている内容での財産分与が不適当だと相続人全員が判断すれば、遺産の相続内容を変更する事ができます。遺言はあくまで、故人の遺志を示すものであるため、記載された内容に強制力はありません。相続人全員が遺産分割協議を行い、その内容に同意すれば、遺産分割協議書での相続手続きを進めていくことになります。
公正証書遺言があると、遺産分割協議が行えないこともある

基本的に、相続人全員が遺産分割協議が必要と結論付けた場合、遺産分割協議を行う事は可能です。しかし、遺産分割協議が行えない場合もあります。
次のようなパターンでは遺産分割協議を行う事ができません。
- 遺言により遺産分割協議が禁止されている
- 相続人・受遺者の全員の同意がない
- 遺言執行者が同意していない
遺言により遺産分割協議が禁止されている
被相続人により、遺言で遺産分割協議が禁止されている場合には、遺産分割協議は行えません。民法では、遺産分割協議について以下のように定めています。
上記の通り、「被相続人が遺言で禁じた場合を除き」とされています。遺産分割協議での財産分与を行う場合、被相続人が遺言によりそれを禁止していたら遺産分割協議は行う事ができません。
相続人・受遺者の全員の同意がない
相続人全員の同意があって、遺産分割協議が行える事はすでにお伝えしました。注意すべきは、遺言に法定相続人以外の「受遺者」の存在があった場合です。
遺言に受遺者への財産の遺贈が記載されている場合、その受遺者の同意が得られなければ、遺産分割協議を行う事はできません。
遺言執行者が同意していない
遺言に記載されている内容通りに相続を遂行するため、手続きなどを行う人を「遺言執行者」と言います。
遺言執行者は遺言者が任意に選ぶ事ができるため、相続人以外が指定されている場合があり、遺言執行人は遺言を実現するために強力な権限を保持しています。相続人以外が遺言執行者として指名されている場合、遺言執行者の同意が得られない限りは遺産分割協議を行う事はできません。
遺産分割協議をした後に、公正証書遺言が発見されたら?
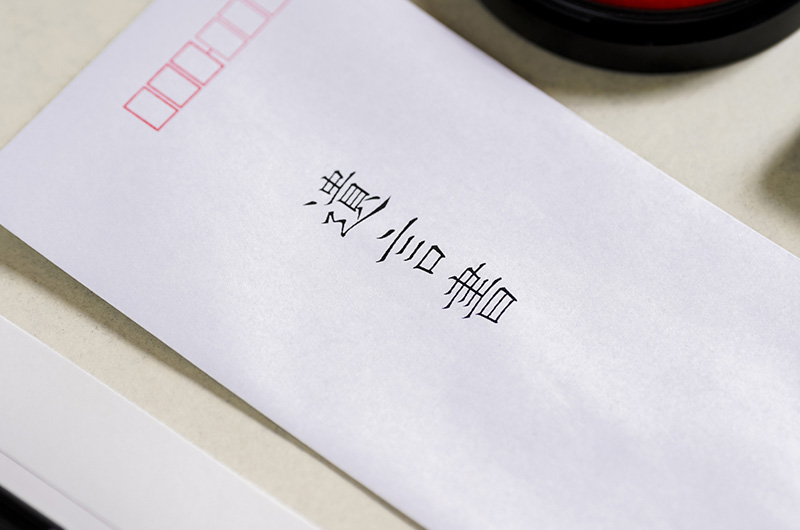
相続人同士で遺産分割協議を行った後に、公正証書遺言が出てくる可能性もあります。
公正証書遺言は公証役場に保管されますが、公証役場には故人が亡くなった事は知らされません。そのため、公正証書遺言の存在を相続人が知らなかった場合は、いつまでも気付かれない可能性があります。
このような時に、遺産分割協議書と後から見つかった公正証書遺言のどちらを採用するかはケースバイケースです。相続人全員が遺産分割協議での財産分与に納得すれば、そのまま遺産分割協議で取り決めた内容で相続手続きをすすめます。
公正証書遺言の発見によって、遺産分割協議が無効になる場合は?
遺産分割協議は、基本的に相続人全員が話し合い同意したものとして、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。このため、遺産分割協議は基本的に一度行ったら無効になる可能性はほとんどありません。
しかし、必ずしも遺産分割協議が無効にならないわけではなく、いくつかの要件が重なる事で無効となるパターンもあります。公正証書遺言の発見によって、遺産分割協議が無効となるのは以下のような場合です。
- 遺産分割協議終了後に、遺言が発見され、
- 遺言の存在を一部の相続人が知らず、
- 相続人のうち、一人でも遺産分割協議の内容に反対した場合
ただし、先に伝えたとおり、発見された遺言で遺産分割協議が禁止されている、遺言執行人が選任されているなどの時には、一度成立した遺産分割協議を相続人全員の同意のもと、解除し、再度遺産分割協議をする「再分割の協議」を行います。
遺産分割協議が無効になれば、公正証書遺言の内容が優先される事になります。ただ、遺産分割協議が無効になるか否かはその時々によるため、専門性の高い判断が必要となるため、プロに相談するのが良いでしょう。
公正証書遺言を残せば、万が一の時もしっかり遺志を示せる
公正証書遺言は、遺言の中でももっとも無効になりにくく、法律の専門家の立ち合いの下に作成するため内容にも確実性があります。遺言で自らの遺志を伝える事は、残された相続人たちにとっても大きな意味があるでしょう。
しかし、記載されていない財産が見つかった場合や遺言の有効性が認められる要件を満たしていない場合、かえって遺言の存在が相続手続きをややこしくしてしまう可能性もあります。しっかりとした遺言を作成する事は、不動産などの財産内容をきちんと調査するのはもちろん、有効性の認められる内容にまとめ上げる必要があり、個人で行うのはかなり難しいというのが、実際のところでしょう。
税理士などの専門家であれば、遺言の記載方法や財産の洗い出し、遺言の作成もしっかりサポートしてくれます。実際に相続が発生した時も、残されたご家族が不安になる事なく相続手続きを進めるお手伝いができます。
遺言、相続で心配な事がある方は、ぜひ税理士に一度相談してみましょう。

税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。