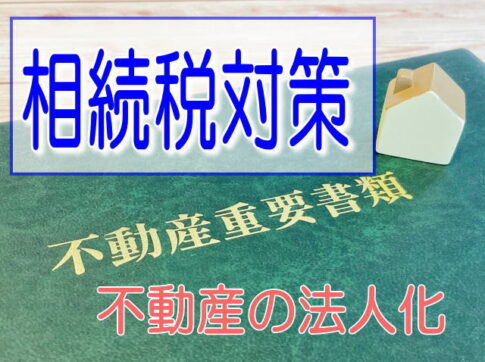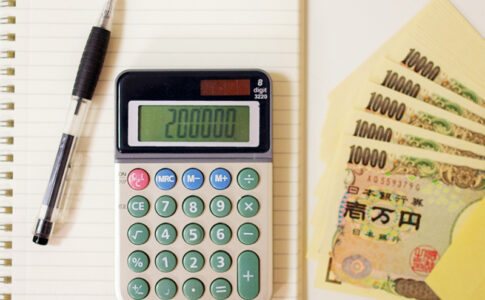「法人に遺贈したら、相続税は節税になる?」
「法人への遺贈と相続税を払うのは、どっちがいいのか知りたい」
法人に遺贈すると、相続税の節税対策になると聞いたことがある人もいるでしょう。
相続税は個人に課せられるものであるため、法人への遺贈した場合に相続税はかかりません。
ただし、相続税は抑えられますが、相続税以外の税金が発生してしまいます。
結果として、相続税を納める場合よりも高額な納税が必要になることもあるでしょう。
そこで今回は、法人への遺贈と相続税の関係、仕組みについてお話します。
法人への遺贈と相続税のどちらがより節税になる可能性が高いかについてもまとめていますよ。
この記事を読むことで、法人への遺贈と相続税を選んだ時の差が分かるので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
法人への遺贈でかかる税金

個人が法人に遺贈したときにかかる税金には、以下のようなものがあります。
- 法人税
- みなし譲渡課税
- 不動産取得税
- 登録免許税
法人に遺贈したとき、どの財産を遺贈されても基本的に発生するのが法人税です。
また、不動産を遺贈したら、不動産取得税や登録免許税がかかります。
さらに、遺贈財産に含み益がある場合には、みなし譲渡課税が発生します。
個人から法人への遺贈では贈られる財産によって、発生する税金が変わることを理解しておきましょう。
法人税
一般的に、個人から法人に遺贈を行った場合は、譲渡所得として法人税が課税されます。
ただし、遺贈先の法人が非営利法人や公益を目的とする事業を行う法人などの場合は、法人税が非課税になるケースも。
遺贈先の法人の法人税が、非課税の対象になるかわからない場合には、税理士に相談してみましょう。
法人税は会社の規模やそのほかの収益、損失を総合的に考慮して課されます。
参考として、以下に中小企業の法人税率を示します。
【中小企業の法人税率(軽減税率)】
| 区分 | 所得 | 税率 | |
| 普通法人 | 中小法人 | 年800万円以下の部分※1 | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | ||
| 中小法人以外の法人 | 全額 | 23.2% | |
| 一般社団法人等 ※2 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | ||
| 公益法人等 ※3 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
| 年800万円超の部分 | 19% | ||
| 協同組合等 ※4 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
| 年800万円超の部分 | 19% | ||
2025年3月31日まで適用される中小企業の税率軽減は、2026年度末(2027年3月31日)まで2年間延長する方針となっています。
上記に当てはめると、中小企業で800万円以下の税率は15%、800万円を超える部分は23.2%の税率です。
相続税の税率は10~55%なので、税率だけで考えると税額を抑えられる可能性が高いでしょう。
みなし譲渡課税
個人から法人に不動産などを遺贈した場合、課税されるのがみなし譲渡課税です。
みなし譲渡課税は遺贈された不動産や株式に含み益がある場合に、相続人にかかります。
【含み益とは】
資産の時価が取得価格(簿価)を上回った場合の差額をいう
たとえば、不動産や株式の譲渡価格(通常、時価で評価)が、取得したときの価格を上回る場合の差額を示す
実は、みなし譲渡課税はトラブルのもとになりやすいため、注意してください。
理由は、財産を受け取るのは法人なのに、税金を支払うのが相続人であるためです。
細かくいうと、相続人が被相続人(遺贈した人)の準確定申告で納付することになります。
準確定申告は相続人が行うため、結果として相続人が支払うといってよいでしょう。
妻(夫)や子からすると、自分が受け取っていない財産の税金を支払わなければならないため、理不尽に感じますね。
納得のいかないことではありますが、現行の法令が上記のように定められているため、従うよりほかはありません。
実務的には、みなし譲渡課税を負担する相続人に、納税資金のための資産を相続させるなどの手立てをすることなどで対処します。
負担をかける相続人には被相続人本人の口からしっかり説明し、了解を得ておくと、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
遺言にのこすだけでなく、きちんと相続人に理解してもらうことが重要です。
不動産を遺贈する場合は不動産取得税・登録免許税も
不動産を遺贈する場合には、不動産取得税や登録免許税が課税されることがあります。
不動産取得税について解説する前に、遺贈の2つの方法についてお話しします。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があり、それぞれ遺贈される財産によって異なります。
【特定遺贈と包括遺贈】
| 特定遺贈 | ・特定の遺産を遺贈すること(例:地番〇〇の不動産、など) |
| 包括遺贈 | ・遺産の割合を指定して遺贈すること(例:全財産の4分の3、など) |
法人に特定遺贈で不動産を贈る場合には、法人に不動産取得税が課されます。
特定遺贈で相続人以外(法人や第三者)が不動産を取得する場合は、相続ではなく譲渡に近いものである、と解釈されるためです。
一方で、相続人が遺贈により不動産を取得した場合は、どちらの方法でも不動産取得税はかかりません。
相続による不動産の取得は、譲渡ではなく形式的な所有権の移転とみなされるためです。
また、遺贈された不動産に登記が必要になるなら、登録免許税が必要です。
登録免許税は土地と建物、両方を取得して登記が必要な場合、どちらも納付します。
支払い時期は明確に定められていませんが、手続き上、登記完了までに納付が必要です。
不動産取得税は、受け取った不動産を登記した後、半年後以内に納税通知書が届きます。
納税通知書に記載された期日(通知の到着後1ヶ月ほど)までに支払います。
期日や納税通知書が届く時期は、各都道府県によるため確認してくださいね。
不動産取得税と登録免許税の概要や計算方法は以下の通りです。
参考にしてみてください。
| 税金 | 概要 | 納税額の計算方法 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を取得した時に課される地方税 | 不動産の評価額×3% ※軽減税率 |
| 登録免許税 | 所有権を登記するときに課される国税 | 土地:評価額×1.5% 新築建物:評価額×0.15% 中古建物:評価額×0.3% ※軽減税率 |
相続税はかからない
個人から法人への遺贈では、相続税は発生しません。
相続税は財産を相続した個人を対象にした税金であるため、法人に相続税は課されません。
相続税という観点だけでみると、節税効果があるように感じますね。
ただし、重要なのは相続税だけに着目せず、法人税や所得税など、ほかの税がどう変わるのかを総合的に考えることです。
先述の通り、法人への遺贈は、法人税やみなし譲渡所得課税が課されます。
法人に遺贈する場合には、どんな税がどの程度課されるのかを把握しておく必要があります。
また、相続税は税率こそ高いものの、1件につき3,600万円以上の大きな基礎控除額が設けられています。
【相続税の基礎控除額】
3,000万+法定相続人数×600万円
【相続税の税率】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:相続税の税率|国税庁
法人への遺贈により相続税は抑えられますが、法人税や所得税などほかの負担が増える可能性があることを考慮しましょう。
法人税や所得税、そして相続税まで絡めて考えるのは非常に煩雑です。
ぜひ、自分だけで抱え込まずに税理士に相談してください。
法人への遺贈で節税になるパターン

法人への遺贈が節税につながりやすいケースを紹介します。
法人が赤字の場合
法人への遺贈で節税になりやすいケースとして、赤字の法人への遺贈が挙げられます。
法人税は収益と損失を相殺し、利益が出た場合に課税されるものです。
つまり、遺贈する財産が法人の赤字を越えなければ、法人税はかからないことになります。
また、法人には繰越欠損金制度があり、10年間の赤字を繰り越せるのもポイントです。
遺贈があった年は黒字になったとしても、過去10年分の赤字と相殺することで、法人税を抑えられます。
結果として、赤字の法人への遺贈は相続税が抑えられるだけでなく、法人税も抑えられることになります。
法定相続人が少ない場合
法定相続人が少ない場合も、法人への遺贈が節税に繋がりやすいケースです。
例えば、現預金1億6千万円、不動産4千万円(時価)、合計2億円の遺産を子1人で相続する例で考えてみましょう。
すべて相続する場合
2億円-基礎控除額3600万円=1億6400万円が課税対象。
子の相続税=1億6400万円×税率40%-控除額1700万円=4860万円
相続税:48,600,000円
不動産を法人に包括遺贈
①相続税
現預金1億6000万円-基礎控除額3600万円=1億2400万円が課税対象
子の相続税=1億2400万円×40%-1700万円=3260万円
相続税:3260万円
②法人にかかる税
法人の概要:収益700万円/損失600万円/利益100万円
法人税:100万円+4000万円=4100万円が課税対象
800万円以下の部分:800万円×15%=1,200,000円
800万円超の部分:3300万円×23.2%=7,656,000円
法人税=1,200,000+7,656,000円=8,856,000円
不動産取得税=0 ※包括遺贈のため、不動産取得税なし
①+②合計=41,456,000円
相続税のみ48,600,000円>法人への遺贈+相続税41,456,000円となり、
一部の財産を法人に遺贈することで、相続のみにするよりも700万円以上、全体的な納税額が少なくなります。
法人へ遺贈する注意点

最後に、法人に遺贈する際の注意点をまとめました。
事前に注意点を理解しておくことで、失敗するリスクを減らせます。
ぜひ、アクションを起こす前に一読してくださいね。
手続きが煩雑
法人への遺贈は、手続きが煩雑になることが挙げられます。
相続税だけであれば、財産評価以外の作業はそれほど煩雑ではなく、規模によっては相続人本人での納税も可能です。
しかし、法人への遺贈を行う場合には、一筋縄ではいきません。
先述の通り、法人税、不動産取得税やみなし譲渡課税など、相続税と絡めてほかの税が発生します。
いくつもの種類の申告や納税が必要となるため、個人での作業は困難でしょう。
相続人がもめるリスクがある
相続人がもめるリスクがあることも、法人への遺贈の注意点です。
財産の一部を法人に遺贈することに、異議を唱える相続人が出てくる可能性があるためです。
同様に多額の財産を法人に遺贈する場合には、遺留分を主張する相続人がいることも懸念されます。
遺贈される法人に、相続人の一部がいるときには、法人に属さない相続人が不公平を訴えることもあるでしょう。
上記のようなトラブルを避けるためには、遺言書の準備と、被相続人の口から相続人全員に、考えや事情を説明することが重要です。
可能であれば、相続人全員が揃うところで話をすることで、齟齬や思い違いを減らせます。
良かれと思った法人への遺贈が、思わぬトラブルを招かないよう事前の準備や対策をしっかりおこない、有効な財産分与を行いましょう。
準確定申告が必要になる可能性
法人への遺贈の注意点のひとつには、被相続人の準確定申告が必要になることも挙げられます。
不動産を法人に特定遺贈する場合には、相続人が亡くなった方の譲渡取得税の準確定申告・納税を行います。
一方で、法人には譲渡所得税はかかりません。
法人の代表者が相続人の中に含まれていない場合などは、特に相続人は納得がいかず、もめる可能性が高いです。
準確定申告を請け負う相続人に譲渡所得税を支払う分の資金を渡すなど、相続人のフォローをするようにしましょう。
まとめ|法人への遺贈は一人で悩まず税理士に相談を

今回は、法人への遺贈と相続税の仕組みについてお伝えしました。
法人への遺贈は、相続税の節税につながる一方、法人税や所得税などほかの税が課税されます。
相続税の税率は高いですが基礎控除額が大きいため、税負担は比較的抑えられることが多いです。
一方で、法人に赤字決算が続いている場合では、法人の赤字と遺贈された財産を相殺できるため、法人税を抑えられます。法人税がかからないケースもあるでしょう。
法人への遺贈は、相続税、所得税、法人税など複数の税が絡むため、非常に煩雑です。
ぜひ、ひとりで悩まず、相続税や所得税に強い税理士に相談してみてください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。