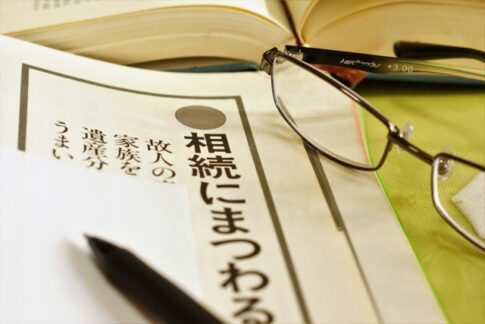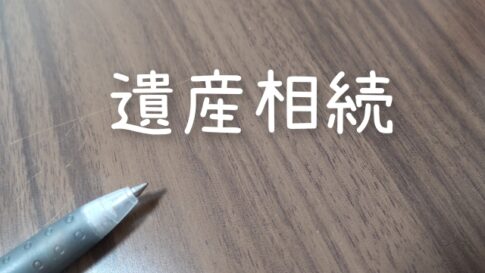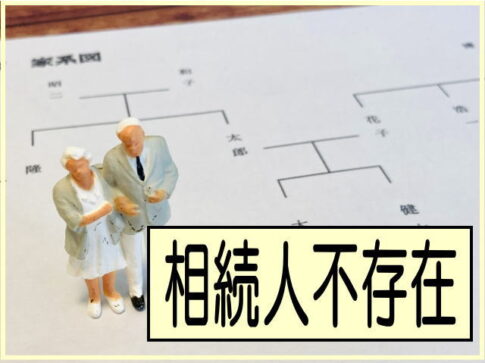ご自身の大切な財産を次世代へつなぐ方法には、いろんな方法が考えられます。なかでも、死因贈与は生前に贈与の契約を交わすことで、安全に指定の財産を渡せるためご検討されている方も多いでしょう。
では、死因贈与とは別の方法である「遺贈」とはどのように異なり、実際に選択するにあたってはどのように判断すればよいでしょうか。
2つの方法には法律上の仕組みや手続きには大きな違いがあるため、じっくり比較することが大切です。本記事では、両者の違いをわかりやすく整理し、メリット・デメリットや税金面の注意点まで詳しく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
死因贈与と遺贈の違いとは

財産を承継させる方法には遺言書が広く知られていますが、「死因贈与」と「遺贈」の2つの方法もあります。
どちらも「財産をあげる人が死亡した時」に効力が発生するという点では共通していますが、手続きには決定的な違いがあるため注意が必要です。この章では死因贈与と遺贈の違いを、わかりやすく比較します。
死因贈与とは
死因贈与は贈与者が亡くなったときに効力が生じる贈与契約です。
贈与契約のため贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)が双方同意の上で契約します。受遺者は法定相続人以外の第三者でも可能です。
口頭でも契約は成立するものの、死後に効力が発生するため契約書形式の書面を残すこと(特に公正証書)がおすすめです。負担付死因贈与という方法もあり、受贈者に一定の義務を負わせることで財産を遺すことも可能です。
遺贈とは
遺贈とは遺言書という形式によって、遺言者(財産をあげる人)が受遺者(財産をもらう人)に対して、一方的に財産を無償で譲る方法です。
遺言者が遺言書を作成するだけで成立するため、贈与契約とは異なります。受遺者の同意は不要です。
また、遺贈であっても法定相続人以外の方に財産を遺すことが可能です。お世話になった友人、内縁の配偶者や法定相続人にはなれない親族などに財産を譲ることが可能です。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの方法があり、いずれも法的な効力は遺言者が死亡した時に初めて発生します。詳しくは以下の記事をご一読ください。
関連記事:遺言書で他人に遺産相続させたい|法定相続人以外への遺贈の注意点
2つの手続きの違い一覧表
死因贈与と遺贈の違いを一覧表にて解説します。
| 死因贈与 | 遺贈 | |
| 契約の有無 | 契約が必要 | 契約は不要(遺言者の一方的な意思表示のみ) |
| 成立の要件 | 贈与者・受贈者双方の意思の合致 | 遺言書の作成が必須(民法で定められた厳格な方式) |
| 撤回の有無 | 可能(最高裁 昭47.5.25)ただし、不動産の場合仮登記が可能 | 遺言者が一方的にいつでも撤回・変更可能 |
| 受贈者(受遺者)の権利 | 契約締結後、贈与者の死亡によって効力が発生 | 遺言者の死後に効力が発生するが、遺贈を放棄することが可能。 |
| 不動産名義の変更 | 生前に仮登記が可能(第三者への対抗力確保) | 生前の登記は不可 |
死因贈与と遺贈のメリット・デメリットとは

大切な財産の渡し方を選択する上で、それぞれの制度が持つメリットと欠点を深く理解しておくことが重要です。そこで、本章では死因贈与と遺贈のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
死因贈与のメリット・デメリット
■死因贈与のメリット
死因贈与は贈与者・受贈者が双方同意をして生前に契約を結ぶため、遺贈のように贈与者の死後に受贈者側から「この財産ならいらなかった」と放棄されるリスクが非常に低いというメリットがあります。
また、負担付死因贈与なら「私の介護を最後まで行うことを条件に、この自宅を贈与する」といった契約も可能です。ペットの飼育などもお願いできるため、何かをしてもらう見返りとして財産を託したい場合にも有効です。
不動産を贈与する場合、契約締結後に仮登記をしておくことで、贈与者の死亡前に不動産が第三者に売却されたり、差し押さえられたりするのを防ぐ「対抗力」が得られます。
■死因贈与のデメリット
贈与という契約の性質上、贈与者の一方的な意思だけでは撤回できない可能性があります。「やっぱり死因贈与はやめよう」と心変わりした際に受贈者の協力を得られずトラブルになる可能性があります。
また、死因贈与は不動産に注意が必要です。法定相続人が取得する場合であっても、不動産の所有権移転登記時にかかる登録免許税(原則2%)や不動産取得税が、遺贈と比べて高額です。
遺贈のメリット・デメリット
■遺贈のメリット
遺言書を使った財産の遺し方のため、受遺者の同意を得る必要がありません。また、遺言者はいつでも内容を一方的に変更・撤回できます。
法定相続人に不動産を遺贈する場合、死因贈与よりも登録免許税(0.4%)や不動産取得税(非課税)の面で大幅に優遇されます。
さらに、遺言書内で遺言執行者を指定しておけば、その後の名義変更などの手続きもスムーズかつ確実に行うことができます。
■遺贈のデメリット
遺贈をする場合、民法で定められた厳格な方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)に従って作成しなければ、遺贈自体が無効になってしまうリスクがあります。
また、形式に問題はなくても遺言者の死後、受遺者は自由に遺贈を放棄することができます。思うように財産を受け取ってもらえないリスクがあるのです。
さらに遺贈は一方的な行為であるため、生前に「世話をしてくれたら遺贈する」といった条件(負担)を法的に拘束力を持って課すことは困難です。
どちらの方法を選択する?選び方を解説

死因贈与と遺贈のどちらを選ぶべきかは、財産を託したい相手や、遺す目的に応じて判断が異なります。そこで、本章では死因贈与と遺贈について、悩んだ際のヒントとなる「選び方」を紹介します。
死因贈与が適している人
死因贈与は贈与契約というメリットがあるため、「 確実に財産を渡し受け継いでほしい」と思っている人におすすめです。
また、受贈者に対して、自身の生前の介護や、住まいの管理など特定の義務を負わせることをお願いしたい人にもおすすめの方法でしょう。
死因贈与には生前に仮登記できるため、受贈者側も「確実に不動産を受け継げる」というメリットもあります。
遺贈が適している人
遺言書は遺言者の死後に開封されるため、生前に内容を知られることがありません。誰にも知られないように財産を遺したい方におすすめです。
また、健康状態や人間関係の変化に応じて、いつでも内容を書き換えたい場合も、死因贈与より遺贈の方が適しているでしょう。
また、死因贈与よりも不動産の税制上の優遇措置が受けられるため、税負担を軽減したい場合にもおすすめです。
死因贈与と贈与|手続きの流れの違い
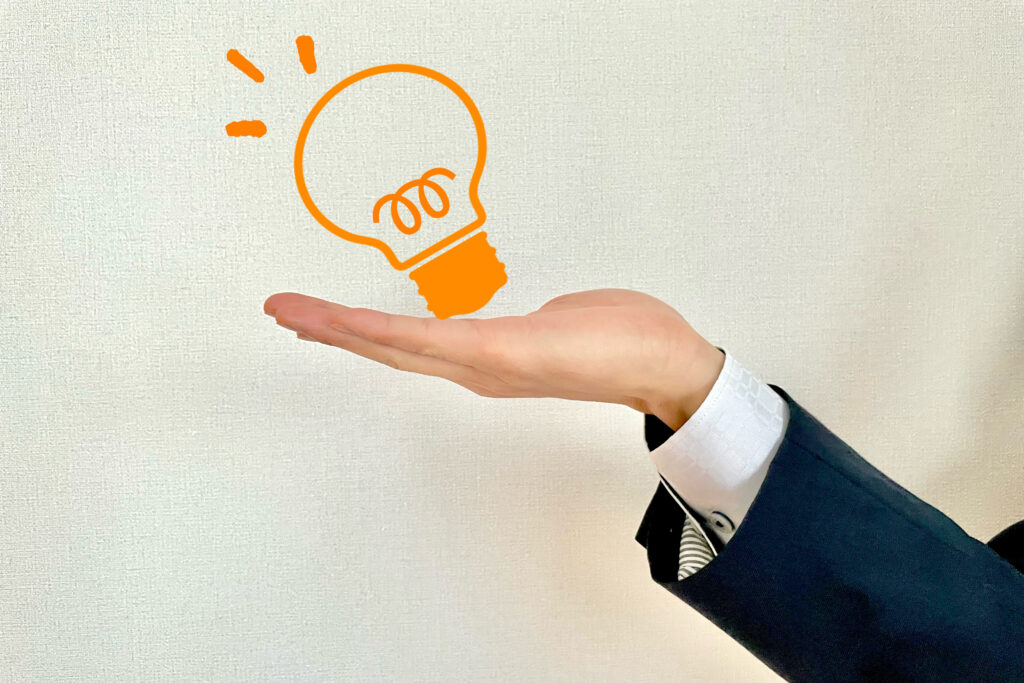
死因贈与は「贈与」という名が付くとおり、生前に効力が生じる通常の生前贈与と同じ「契約」という性質を持ちます。しかし、効力発生のタイミングが決定的に異なります。
本章では死因贈与と贈与の手続きを進める際に知っておきたい流れを解説します。
死因贈与手続きの流れ
1.契約を結び、契約書を作る
贈与者と受贈者が合意し、死因贈与契約書を作成します。
2.(不動産の場合)仮登記
公正証書がある場合は受贈者が単独で、ない場合は贈与者と共同で仮登記を行い、権利を保全できます。
3.贈与者の死亡
契約の効力が発生し、受贈者に財産を請求する権利が発生します。
4.名義変更手続き
死亡後、受贈者は死亡証明書や戸籍謄本などを用いて、不動産や預貯金の名義変更手続きを行います。
遺贈手続きの流れ
1.遺言書の確認
遺言書の遺し方を検討します。遺言書には主に次の3種類があります
- 自筆証書遺言:自筆で作成後に自身で保管するが、法務局に保管することも可能
- 公正証書遺言:公証役場で作成されたもの(最も確実)
- 秘密証書遺言:署名押印の上で封印されたもの(実務では少ない)
自筆証書遺言がある場合は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があります(公正証書遺言は不要)
2.遺言執行者の確認
遺言者の死後、遺言書に遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が財産の名義変更や手続きを行います。遺言執行者がいない場合は相続人と連携しながら手続きを進めます。(※遺言執行者が必要なケースもあるため注意)
3.遺産の引渡し・名義変更(登記)
各遺産の解約や登記名義を変更する必要があります。
知っておきたい税務上の違いはある?

死因贈与と遺贈は、どちらも贈与者(遺言者)の死亡によって財産が移転するため、生前贈与とは異なり、原則として相続税の課税対象となります。
しかし、不動産の名義変更(登記)を行う際に課される税金に、決定的な違いが生じます。この違いは、特に法定相続人に対して不動産を渡す場合に重要です。
登録免許税の違い
不動産の名義変更を行う際に法務局へ支払う税金です。遺贈の受遺者が法定相続人であるか否かで税率が変わります。
| 取得方法 | 取得者 | 登録免許税の税率 (固定資産税評価額に対して) | 備考 |
| 死因贈与 | 全ての受贈者 | 2.0%(一律) | 生前贈与と同じ税率が適用されます。 |
| 遺贈 | 法定相続人 | 0.40% | 相続と同じ税率が適用されるため、大幅に優遇されます。 |
| 遺贈 | 法定相続人以外 | 2.0%(一律) |
不動産取得税の違い
不動産を取得したときに一度だけ課税される税金です。贈与と遺贈では大きな違いがあります。
死因贈与はあくまでも贈与契約のため、生前贈与時と同様に法定相続人であっても不動産取得税が発生します。死因贈与は登録免許税も高いため、不動産の死因贈与には十分に注意が必要です。
| 取得方法 | 取得者 | 不動産取得税の課税 | 備考 |
| 死因贈与 | 全ての受贈者 | 課税される(原則) | |
| 遺贈 | 法定相続人 | 非課税 | 相続財産の承継として扱われるため、免除されます。 |
| 遺贈 | 法定相続人以外 | 課税される(原則) |
相続税の2割加算について
死因贈与・遺贈のどちらにおいても、財産を取得した人が法定相続人以外である場合、その人が負担する相続税額は、原則として2割加算されます。
生前に財産をもらうことを教えてもらっていない遺贈では、高額の相続税に悩まれた結果遺贈を受けないという選択をする可能性があります。受贈者の生活状況や資産状況も検討した上で遺贈をされることがおすすめです。
まとめ
死因贈与と遺贈はいずれも「死後に財産を渡す」方法ですが、仕組みや税負担が異なります。死因贈与は生前の贈与契約であり、条件付きの「負担付死因贈与」も可能ですが、一方的な撤回が難しく税負担も重くなりがちです。
一方の遺贈は遺言書で自由に指定でき、後から内容変更も可能で、法定相続人への不動産遺贈では税優遇も受けられます。
ただし遺言書に不備があると無効になったり、受遺者が放棄する場合もあるため、専門家に相談して手続きを進めるのが安心です。まずはお気軽に横浜市の響き税理士法人へお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。