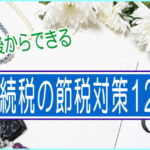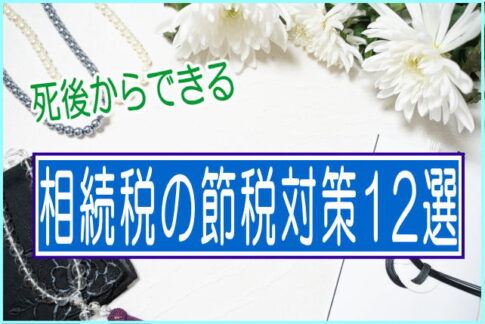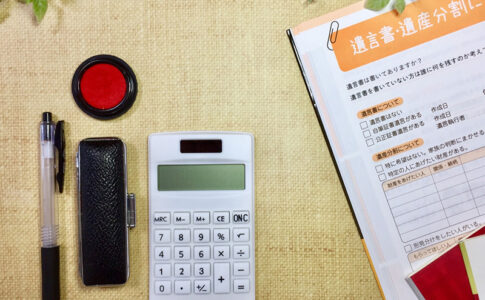家族が亡くなった際、被相続人が所有していた不動産で「未払いの固定資産税」についてどのように扱うべきか悩んでしまうことがあります。
固定資産税とは「毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される地方税」です。毎年4~6月頃に納税通知書が届きます。では、被相続人の未払いの固定資産税があったら誰が、どのように支払うべきでしょうか。
本記事では、被相続人に未払いの固定資産税があった場合の対処法について、相続人が知っておくべきポイントや手続きの流れ、相続税の計算における注意点などを詳しく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
被相続人に未払いの固定資産税があった場合の注意点

相続手続きを進める中で、未払いの固定資産税があるとわかったら、一体どのように対処すれば良いでしょうか。この章では誰が支払うのかなど、相続後によくあるお悩みについて詳しく解説します。
相続人が支払う必要がある
被相続人が亡くなった時点で未払いの固定資産税があった場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されるものであり、被相続人が亡くなった日に関わらず発生します。
そのため、未払いがあったらその年の納税義務は被相続人が承継します。つまり相続人はこの未払い分を支払う必要があるのです。亡くなったとしても税金は免除されるものではありません。
固定資産税の支払い対象となる財産とは
固定資産税の支払い対象となる財産は、おもに以下のものが挙げられます。土地や建物以外も対象となる資産があるためご注意ください。
①土地
宅地、田、畑、山林など
②家屋
住宅、店舗、工場、倉庫など
③償却資産
事業のために使用する土地や建物以外の資産など
横浜市の固定資産税については、以下リンクからご確認ください。
参考URL 横浜市 固定資産税・都市計画税について
被相続人の固定資産税は債務控除の対象?

被相続人が残した固定資産税は先に述べたように、相続人が支払う必要があります。残されたご家族にとって重い負担ですが、実は相続税申告前に押さえておきたいポイントがあります。それは、未払いの固定資産税は「債務控除」の対象となる点です。
「相続した人が支払うべき税金だから債務控除にならないのでは?」
と思っている人も多いですが、相続税の申告時には債務控除として相続財産から差し引くことができます。債務控除については以下のとおりです。
債務控除とは
相続税を計算する時は、被相続人の現金や預貯金、不動産などのプラスの財産から借入金や未払金といったマイナスの財産を差し引くことが可能です。
このことを「債務控除」といいます。
債務控除は多ければ多くなるほど相続財産を減らすことになるため、最終的な相続税を減らすことにつながります。そのため、債務控除の対象となるものを漏らすことなく計上することで、相続税を節税できます。
ただし、被相続人が支払うべき債務であれば何でもよいという訳ではなく、債務控除の対象となるものと対象にならないものを理解しておくことが重要です。
債務控除に該当するもの
債務控除に該当するものとして次のようなものが挙げられます。
・被相続人名義の借入金やローンの残債、未払金など
・固定資産税や住民税、所得税など
・ガスや電話代、水道光熱費などの生活費(日割り計算が必要)
・未払いの医療費
・未払いのクレジットカード料金
・葬祭費用 など
生活費等も適切に日割り計算することで債務控除の中に入れることが可能です。
債務控除に該当しないもの
債務控除に該当しないものとして次のようなものが挙げられます。
・団体信用保険に加入している住宅ローン
・相続財産の管理費用
・香典返しや法事に関する費用
・相続手続き開始後に発生した弁護士費用
・相続手続き開始後に発生した税理士費用 など
香典返しや法事など、債務控除できる葬祭費用に含まれない費用も多いため、実際に相続税計算をする際には税理士へ相談しながら正しく計上することが大切です。
債務控除を行うべきタイミングとは
債務控除は「相続税の申告を行う際」に適用します。相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出する必要があります。この申告書には、債務を記載する欄があり、ここで債務控除を申請することになります。
被相続人が亡くなった時点で固定資産税の未払い分がある場合、その未払い分すべてが債務控除の対象になります。
相続税申告前の注意点|固定資産税の支払いの注意点
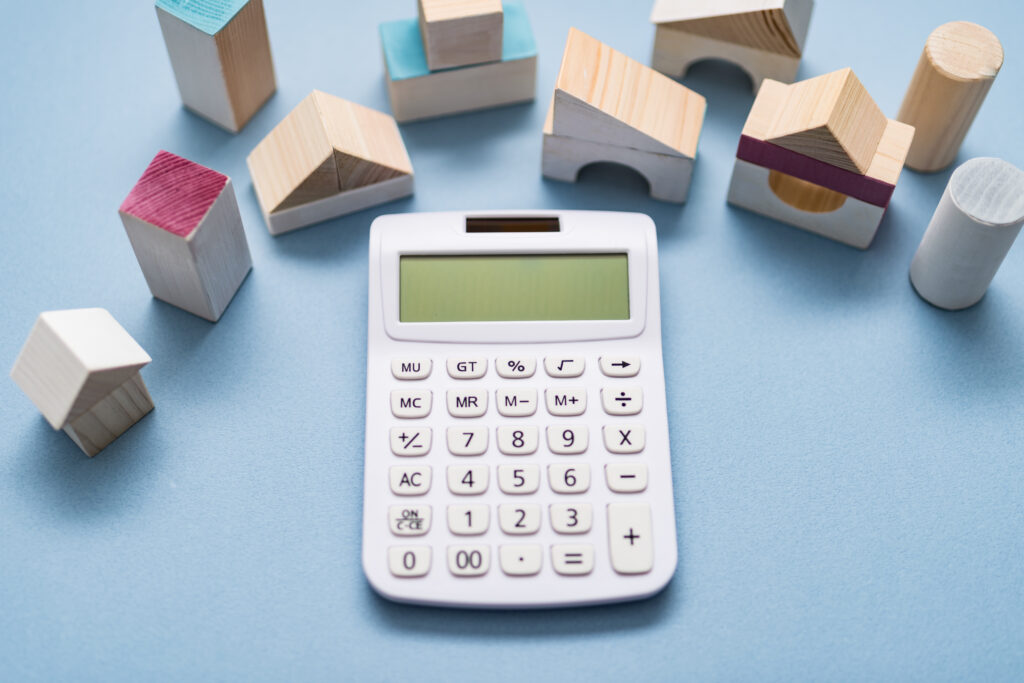
相続人が複数いる場合、未払いの固定資産税を誰が支払うかで意見が対立することがあります。遺産分割協議中は未払いの税金も共有状態となるため、相続人全員が支払い義務を負うことになります。
この章では支払いについて相続人が揉めてしまった時の対処法を中心に詳しく解説します。
未払い分の固定資産税は原則法定相続分で負担する
被相続人が亡くなった後、未払いの固定資産税がある場合は原則として各相続人が法定相続分に応じて負担することになります。
なお、未払いの固定資産税に延滞税が発生している場合、延滞税も含めて清算する必要があります。
例・未払いの固定資産税が20万円あり、配偶者1名と子2名で支払う
①配偶者 法定相続分は2分の1のため、負担は10万円
②子2名 法定相続分は2分の1、子は2名いるため子1名につき5万円ずつ
固定資産税を誰が支払うのか、もめたらどうする?
相続人が1名の場合は、未払いの固定資産税は該当する相続人が支払うことになります。しかし、複数の相続人がいて、誰が支払うのか揉めてしまった場合はどうすればよいでしょうか。
もめている場合でも、固定資産税の納付義務は生じるため、各自治体は「代表相続人」に対して支払いを求めます。この代表者が不動産の所有者ではない場合も同様です。
そのため、代表相続人が支払うか、以下の方法で早急に支払い方法を確定する必要があります。
- 法定相続分で分割する
- 遺産分割協議で話し合い決定する
なお、遺産分割協議が難航している場合は相続税申告も遅延するおそれがあるため、弁護士や税理士と相談しながら対応を協議することが望ましいでしょう。
共有不動産は持分に応じて納税義務が発生する
相続した不動産が共有名義になっている場合、各相続人は持分に応じて固定資産税を支払う義務が発生します。
たとえば、持分が2分の1ずつの場合、固定資産税も2分の1ずつ負担することになります。ただし、各共有者へ納税通知書が届くのではなく、代表者宛に納税通知書が発送されるため注意が必要です。
受け取った代表者は他の共有者にも支払いを依頼する必要があります。
遺産分割協議が終わるまでに請求が来たらどうする?
遺産分割協議は時間がかかることが多く、その間に固定資産税の納付書が届くこともあります。この場合、納税期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するため、放置は禁物です。
遺産分割協議がまとまる前でも、相続人全員で話し合って誰が支払うかを決めましょう。まずは代表者がいったん全額を支払い、後から遺産分割協議で清算するという方法がスムーズです。この際に支払った金額を記録に残しておくと、後々のトラブルを防げます。
固定資産税が発生している資産を取得する相続人が決まった後なら、新しい所有者が相続税を支払うことになりますが、ここで注意が必要です。
固定資産税は1月1日時点の所有者に課せられるため遺産分割協議の確定時期によっては相続人全員が納税義務者税義務者に該当します。
例として、遺産分割協議が6月1日なら、その年の固定資産税の納税義務者は被相続人のため相続人全員が納税義務者です。そのため、誰がいつ固定資産税を清算するのか、不動産の相続先を決める際にはセットで話し合うようにしましょう。
固定資産税の相続手続きの流れ

相続した不動産がある場合、どのような相続手続きを行う必要があるでしょうか。この章では固定資産税も含めた相続時の不動産における手続きを詳しく解説します。
相続登記
不動産を相続したら、法務局で「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは不動産の所有者を被相続人から相続人へと変更する手続きです。
相続登記は義務化されており、2024年4月1日からは期限が設けられました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられるおそれがあります。
現所有者申告書も忘れずに
現所有者申告書とは、土地や家屋の所有者が亡くなった後に、相続登記が終わっていない場合、誰が現在の所有者となっているか各自治体へ申告する必要がある書類です。
相続登記とはまったく別の手続きです。遺産分割協議が終わっていない場合は法定相続人全員を現所有者として申告します。書式などは各自治体によって異なるためご注意ください。
参考URL 横浜市 土地・家屋の名義人が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税について(相続登記・現所有者申告制度)
未登記家屋が発覚した場合の対応とは
被相続人が所有していた家屋が未登記家屋であると判明するケースもあります。未登記家屋は法務局の登記簿には記載されていませんが、市町村の固定資産税台帳には登録されており、固定資産税はもちろん相続税の課税対象にもなります。
未登記家屋は所有権が証明できないなどのデメリットがあるため、相続を迎えた際には手続きは慎重に検討する必要があります。未登記家屋を相続する人がきまったら、そのまま放置するのではなく建物表題登記と所有権保存登記を行うことが大切です。
特に、今後売却を検討している場合はこのタイミングで正しく登記しましょう。
相続放棄をすると未払いの固定資産税はどうなる?

高額の未払い固定資産税やローンなどの債務がある場合、相続人の中には「相続放棄」を検討する人もいるでしょう。
相続放棄とは、被相続人のすべての財産(プラスの財産とマイナスの財産)を放棄するために、家庭裁判所で行うことです。
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、未払いの固定資産税も放棄できます。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし、相続放棄をすると、被相続人の預貯金や不動産などの「プラスの財産」も一切受け取れなくなるので注意が必要です。
相続放棄をしたのに固定資産税が発生するケースに注意
相続放棄をすれば、未払いの固定資産税を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をしたにもかかわらず、固定資産税の支払い義務が発生するケースもあるので注意が必要です。
たとえば、相続放棄を12月中頃に家庭裁判所へ申述すると、家庭裁判所での受理(放棄完了)に時間がかかり2月までかかることも少なくありません。
繰り返しですが、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税が行われるため、納税義務が発生します。
このようなケースで別の相続人が不動産を相続する場合は、その相続人へ固定資産税の支払いを依頼しましょう。また、不服申し立てによる対応も検討できます。
相続放棄の申述前に固定資産税を支払うとどうなる?
相続放棄前に、被相続人名義の未払いや滞納されている固定資産税を見つけた場合、申述前(家庭裁判所への手続き前)に支払ったらどうなるでしょうか。
未払い・滞納となっている税金を「相続人自身」の財産で支払った場合は「単純承認」とはみなさないため相続放棄も可能です。
一方で、被相続人の預貯金などの財産から支払った場合は単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。被相続人の財産を小分子、税金に充当するなどの行為も危険です。
相続放棄できなくなってしまうと、債務も相続する必要が生じます。万が一のトラブルを防ぐためにも、高額の債務がある相続放棄は弁護士に相談した上で安全に進めることが大切です。
まとめ
本記事では被相続人に未払いの固定資産税がある場合に、相続税申告時の確認すべき
注意点を中心に詳しく解説しました。未払いの固定資産税は相続人が支払う必要がありますが、相続税申告時には債務控除ができるため、申告書類を作る際にその他の債務控除対象となるものとあわせて申告することが大切です。
遺産分割協議の遅れなどによって延滞税が発生してしまうおそれがあるため、相続人間で意見が異なる場合でも早期の対処を行いましょう。
横浜市の響き税理士法人では、債務控除も含めた相続税申告のご相談に対応しています。いつでもお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。