
無形固定資産は、形をもたない資産であることから、相続財産として保有しているかの確認が、まずは必要となります。
相続人が生前にゴルフを嗜んでいた場合、ゴルフ会員権の保有を必ず確認をしましょう。ゴルフ会員権も、預金や不動産のように相続税の課税対象となる相続財産のひとつであるためです。
今回は、無形固定資産のうち、ゴルフ会員権の評価方法と、相続財産にゴルフ会員権が含まれる場合の注意ポイントについて、詳しく紹介していきます。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
無形固定資産とは
無形固定資産とは、長期にわたって保有する資産のうち、形をもたないもののことをいいます。
法人税法施行令では、下記のものを無形固定資産として挙げています。
ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権は施設利用権のひとつであることから、上記の無形固定資産に該当します。このゴルフ会員権を相続した場合には、評価を行い相続財産に含める必要があります。
ゴルフ会員権とは
ゴルフ会員権とは、会員とゴルフ場との間だけに有効な権利証券です。この権利証券を保有することで、会員制のゴルフ場にて一般の利用者よりもクラブ競技参加等の様々なサービスの提供を受けたり、それらのサービスを割安な会員料金での利用をしたりすることができます。
ゴルフ会員権をもつメリット
ゴルフ会員権を持つメリットは、上記のように一般の利用者よりも様々な優遇措置を受けることができることです。
優遇措置には、プレー料金が一般の利用者よりも安くなる、利用予約を一般の利用者よりも優先的にとることができる、クラブ競技への参加ができる、送迎車の利用ができる等、様々なものがあります。
一方でデメリットは、購入や年会費のコストの負担や、会員権の価格変動により売却損が生じる場合があることです。
ゴルフ会員権の種類
ゴルフ会員権は、預託金制、株主会員制、社団法人制に分類することができます。
預託金制の会員権とは、一定の金額をゴルフ場経営会社に預けて会員となる方式で、会社は会員からの預託金を資金としてゴルフ場を作ります。
預託金は無利子で一定期間据え置かれますが、その後に退会する場合は預託金返還請求をすることができ、元金が保証されています。
株主会員制の会員権とは、会員がゴルフ場経営会社の株主として出資する形態で、株主総会で議決権を行使することで経営に参加をすることができます。
株主であることから、経営会社が解散になった場合には、会社財産を持株比率で分配を受ける権利があります。
社団法人制の会員権とは、ゴルフ場経営者である公益法人の社員として会員になるもので、その権利の譲渡が難しい名誉会員としての側面が強いものです。
取引相場のある会員権の評価
会員権の評価は、預託金制の会員権、取引相場のある会員権、取引相場のない会員権で取り扱いが異なります。
預託金制の会員権は、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができるため、評価はしません。
取引相場のある会員権の評価額は、被相続人の死亡の日の通常の取引価格の70%に相当する額です。
この通常の取引価格は、ゴルフ会員権の取引業者に問い合わせを行う、業者が新聞に掲載している広告やホームページで公表している取引価格を参考にすること等で知ることができます。
取引価格に含まれない預託金等がある場合は、その預託金等を合算します。
この預託金等は、課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等の場合は、ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額を評価額とし、課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等の場合は、ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額を評価額とします。
取引相場のない会員権の評価
取引相場のない会員権は、下記の区分に応じて評価をします。
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
株式部分については、上記の株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権と同様に評価をします。
預託金部分については、取引相場のある会員権の評価の預託金等と同様に評価をします。
取引相場のある会員権の評価の預託金等と同様に評価をします。
参考:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm
ゴルフ会員権の相続はここに注意!
ゴルフ会員権を相続する場合には、下記の点に注意が必要です。
ゴルフ会員権は共有名義で相続できない
ゴルフ会員権は、相続人のうち1人が相続をすることができ、共有名義で相続することはできません。
遺産をどのように分けるかを記した遺産分割協議書を相続人間で作成する際に、ゴルフ会員権を分割しないように注意をしましょう。
相続人が引き継いでゴルフ場を利用する場合
相続人が引き継いでゴルフ場を利用する場合には、その会員権の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。この際に名義書換料が発生するため、会員権を相続する人は、その金銭的負担を考慮する必要があります。
名義書換料は、会員権を相続人が引き継いでゴルフ場を利用する場合には、必然的に発生しますが、債務控除の対象として取り扱われません。葬式費用と同様に相続財産額から控除することができないため、相続税の申告の際には注意をしましょう。
相続人がゴルフを行わない場合
相続人がゴルフを行わない場合には、相続で受け取った会員権を売却することになります。この会員権の売却によって得た利益は、譲渡所得として課税対象となります。譲渡所得の申告を失念しないよう注意をしましょう。
また、譲渡所得の申告の際は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用することができます。譲渡所得は収入金額から取得費を差し引いて算出します。この取得費を相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
この特例の適用の条件を満たすためには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが必要であるため、ゴルフを行わない相続人がゴルフ会員権を相続した場合には、3年以内に売却をするようにしましょう。
まとめ
このように、ゴルフ会員権は、預託金制の会員権、取引相場のある会員権、取引相場のない会員権で取り扱いが異なります。
評価額の多寡により、算出される相続税額が異なるため、ゴルフ会員権の評価は正しく行う必要があります。
また、相続人がゴルフ場を利用する人であるかによって、相続後の取り扱いが異なります。分割して相続することができないため、相続人が複数の場合には、誰が取得するかを検討する必要があります。
ゴルフ会員権の評価や取り扱いについてご不明な点がございましたら、所轄の税務署や身近な専門家にご相談されることをおすすめします。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。






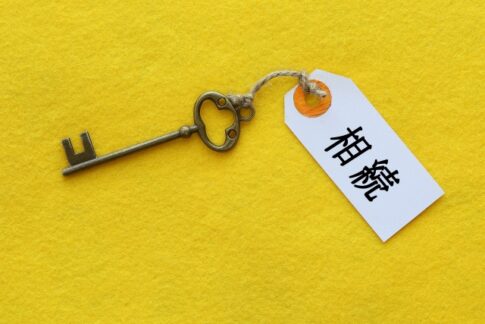

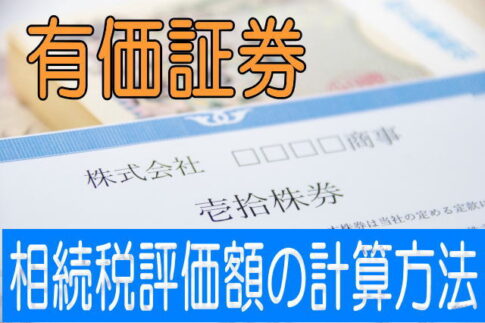


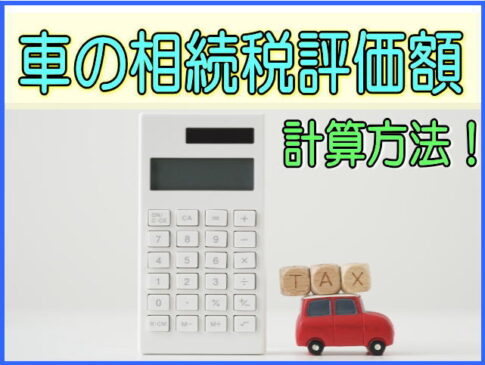






その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。