
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
定期借地権は相続税対策に効果的

「土地は更地で持っているよりも、家を建てた方がいい」という話、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?その理由は、建物が立っている土地の方が、更地の評価額よりも安くなるため。ただ、すでに持ち家がある方や建物を建てても住む人がいない…という方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときに利用すると良いのが、土地を貸し出して活用する「定期借地権」。定期借地権は、相続税の財産評価時に土地の評価額を下げることができるため、相続税対策にも効果的であると言えます。
定期借地権とは?
定期借地権とは、その名の通り、定められた期間での借地権のことを言います。かつて定められていた旧借地法では、借り主側が非常に強く保護されていました。結果として、「一度貸した土地は、半永久的に返ってこない」ということが通例となり、貸主側は不利な立場に追いやられることに。
上記の問題を受けて定められた「定期借地権」は、決められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新がないというのが大きな特徴です。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3つがあります。それぞれ、借地期間や権利内容、特約などが異なります。
相続税の基礎控除と非課税限度額
定期借地権を含むすべての相続財産には、まず「基礎控除」が適用されます。
この控除額を超えないと相続税は発生しませんので、節税対策を始める前に必ず把握しておきましょう。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた宅地や事業用宅地については、特例に関する要件を満たすことで、最大80%の評価減が可能です。
定期借地権付き宅地も、契約形態や利用状況によって特例適用となるケースがありますので、適用可否なども含めて損をしたくない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
適用のポイント
特例を受けるには、相続開始から10ヵ月以内の申告と、遺産分割協議書など必要書類の提出が必須です。
書類漏れや期限超過に注意しましょう。
定期借地権の相続税におけるメリット

では、定期借地権の相続税におけるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?貸す側、借りる側、双方に相続面でのメリットがあります。それでは、それぞれ見ていきましょう。
貸す側は、土地の評価が大きく下がる
まず、土地の持ち主「貸す側」から。
定期借地権の相続税における最大のメリットは、「土地の評価が下がること」です。この土地の評価が下がる事こそが、相続税の節税対策をさらにUPさせることに繋がります。通常、建物を建てられる土地である「宅地」は、相続税の財産評価時に次の3つに分けられます。
- 自用地
- 貸宅地
- 貸家建付地
貸し出す土地に定期借地権を利用する場合は、「貸宅地」という扱いになります。貸宅地は、自用地や貸家建付地よりも大きく評価額が下がるのが特徴です。
路線価評価額とは、国税庁が示している基準となる評価を基に算出された価額のことを言います。国税庁のホームページなどに掲載されている「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
さて、本題に戻って、自用地の場合は、土地・建物共に所有者に使用する権利があるため、控除はできず、評価額はそのまま5,000万円となります。一方、貸宅地の場合、計算方法は以下のようになります。

借地権割合とは国税庁が定めているもので、繁華街や主要な駅の周辺では高く、郊外に行くほど低くなります。90~30%の間を10%刻みで定められていて、自分の土地の借地権割合については、路線価と同様に「路線価図・評価倍率表」に示されています。
自用地評価額5000万円-自用地評価額5000万円×60%=2,000万円
定期借地権を使用して貸し出すだけで、土地の評価額が自用地の60%ほど下がり、2000万円になりました。もちろん、上記はあくまで一例であり、減額できる金額は土地や借地権割合により異なります。
しかし、定期借地権を利用することにより、どのような土地でも一定の評価額の減額は期待できるでしょう。
物納の認可が下りやすい
相続税を納付する際、現・預金に余剰がないときには、「物納」したいと考える場合もあるでしょう。通常、貸している土地では物納申請が認められないことが多くあります。
しかし、定期借地権を設定している土地であれば、いずれ更地に戻ることが約束されているため、物納の認可が下りやすくなります。相続税の節税になるだけでなく、相続税納付時にも相続人にとって心強いですね。
ただし、定期借地権を設定している土地を物納申請する場合には、以下のような事柄が問題点として上がる可能性があります。将来、相続時に物納申請する可能性がある方は、注意しておきましょう。
- 借り主から保証金を受け取っていた場合には、保証金を清算しなければならない
- 借り主が土地に抵当権を設定している場合には、抹消しなければならない
- 賃料がかなり低額なので、賃貸料の引き上げが必要になる
借りる側は、相続財産に土地が含まれない
続いて、借地権のある土地を「借りる側」、つまり借地権を持つ側のメリットについてお伝えします。借地権を持つ側の最大のメリットは、「土地が相続財産に含まれないこと」です。
定期借地権を設定した土地を借りた場合、住宅を建て、定められた期間、安心して土地を使用できる生活を送りながらも、相続が発生した時には財産に土地が含まれません。しかしながら、土地の代わりに「借地権」が財産に含まれます。借地権の相続税の評価額は、「自用地評価額×借地権割合」となります。
先ほど例に挙げた、自用地評価額5000万円、借地権割合60%の土地の場合、借地権の評価額は3,000万円になります。5000万円の土地を使用しながら、相続時の評価は3000万円になるため、節税対策としては十分でしょう。借地権割合によっては、さらに評価額が下がることも期待できます。
一方、主要な繁華街などでは借地権割合はかなり高くなるため、定期借地権を結ぶ際には全に借地権割合をしっかりと確認しておくとよいでしょう。
定期借地権を使用する場合の注意点
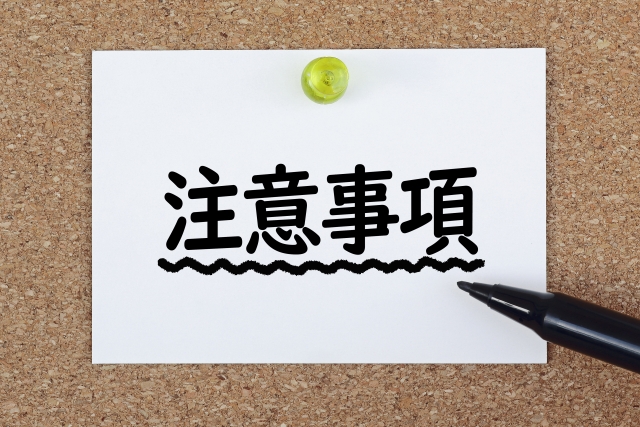
相続税においては非常に効果的な対策となる定期借地権ですが、契約を結ぶ際には、いくつか注意点もあります。引き続き、貸主側、借り主側にわけて、それぞれ見ていきましょう。
貸す側は、売却できない
貸す側における最大の注意点は、「土地の売却できない」ことです。定期借地権の契約年数はそれぞれ異なりますが、一般定期借地権の場合は最低でも50年の契約が必要になります。
土地の売却をしたくなったとしても、定期借地権を結んでしまっている土地は基本的に売却はできません。どうしても売却するという場合には、大きな労力が必要になる事を覚悟してください。
また、50年先まで宅地としての使用が決められているため、土地を他の方法で利用することもできなくなります。50年先のことまで決めるのは難しいですが、「50年以上貸したままでも大丈夫な土地」であることを前提に、検討するようにしましょう。
権利金や保証金なども含め、総合的に考える
土地の評価において、定期借地権は非常に有効ですが、賃料や権利金など、その他の財産となる部分にも注意する必要があります。契約を結ぶときに発生する「権利金」や「保証金」、「前払賃料」などは現・預金を増加させるため、相続財産が増えることが考えられます。
契約時に「権利金」と「保証金」どちらを選ぶかは、自由です。貸主、借り主の双方が納得したものを採用するため、事前にしっかりと検討することをオススメします。
借りる側は、途中解約・更新できない
一方、借りる側のデメリットとしては、「途中解約・更新できない」ことです。
貸主側のデメリットに「売却できない」と挙げたように、借りる側は途中解約ができません。
また、定期借地権は基本的に期間が満了を迎えたら、更地にして返還する必要があります。仮に建物に資産価値が残っていても土地所有者に買い取ってもらうなど、契約満了時には、今までの土地には住むことができません。
契約を交わす際には、契約満了以降の住宅はどうするかなど、先々のことまで考える必要があるでしょう。
定期借地権評価額の残存年数評価調整方法
定期借地権の評価額は、路線価だけでなく「契約残存年数」によっても大きく変動します。
残存期間が短いほど権利価値が下がるため、評価額の算出方法を具体的に確認しておきましょう。
路線価(円/㎡)× 宅地面積(㎡)× 借地権割合(%)
残存年数評価率の適用
残存期間が短いほど権利価値が下がる仕組みを、相続税法第23条に基づく割合表で確認しましょう。
| 残存期間 | 割合 |
| 10年以下 | 5% |
| 10年超~15年以下 | 10% |
| 15年超~20年以下 | 20% |
| 20年超~25年以下 | 30% |
| 25年超~30年以下 (地上権で存続期間の定めのないものも含む) | 40% |
| 30年超~35年以下 | 50% |
| 35年超~40年以下 | 60% |
| 40年超~45年以下 | 70% |
| 45年超~50年以下 | 80% |
| 50年超 | 90% |
具体計算例
50㎡の宅地、路線価20万円、権利割合70%、残存期間15年(評価率10%)の場合:
20万円×50㎡×0.70×0.10=70万円
手続きにかかるコストの内訳
相続登記や借地権評価にかかる登録免許税、司法書士報酬、鑑定費用などの目安をまとめます。
定期借地権相続で発生する主な費用についてまとめてみました。
事前に見積もりを立て、相続後の資金繰りに備えましょう。
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
| 登録免許税 | 評価額×0.4% | 相続登記に必要 |
| 司法書士報酬 | 5~10万円 | 土地が複数あると増額 |
| 鑑定士・土地家屋調査士 | 3~5万円/件 | 評価証明や境界確定など |
| 評価照明や境界画定など | 数百円/通 | 法務局で申請 |
| 評価証明書発行料 | 1,000~2,000円 | 市区町村役場で取得 |
定期借地権を上手に利用して、効果的な節税対策を

いかがでしたか?今回は定期借地権を利用した相続税対策についてお伝えしました。
定期借地権は、貸主・借主ともに相続財産の評価を下げられるため、相続税の節税効果を高めてくれる有効な手法です。もちろん、相続税だけでなく、貸主側は安定的に地代を得られることや更地のままにしておくことよりも固定資産税を下げられることなどのメリットもあります。
借主側としても、土地を取得する費用がなくても家を建てることができ、毎年の固定資産税を支払う必要がなく充分なメリットが得られます。50年間土地を動かすことができないと言われると、少し戸惑ってしまいますが、逆を言えば50年間は確実に借り主がいてくれるということです。
借り主としても、一方的に退去を命じられるなどのリスクを回避することができます。さらに、相続税対策を効果的にUPさせることができるため、ぜひ前向きに検討していくとよいでしょう。
定期借地権にはいくつかの種類だけでなく、権利金や保証金などの取り決めがあり、どれを選べばよいか、どのように進めれば良いのか悩む方も少なくありません。50年の長きに渡る不動産の行く末を決めるため、悩んだときには専門家に相談することをオススメします。
定期借地権を設定する場合には、相続税はもちろん、固定資産税、所得税など様々な税金が関わってくるため、税理士に相談するのが特に良いでしょう。
税理士など税金や土地のプロに相談すれば、あなたに合った解決策をきっと提案してくれます。ぜひ、今回ご紹介した定期借地権などを利用して、効果的に相続税を節税してくださいね。
FAQ:定期借地権相続に関するよくある疑問
はい、定期借地権も相続財産として評価・課税対象になります。
登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬(5~10万円)が一般的です。
基礎控除内であれば不要です。特例適用でさらに軽減も可能です。
「路線価×面積×権利割合×残存年数評価率」の数式で算出します。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

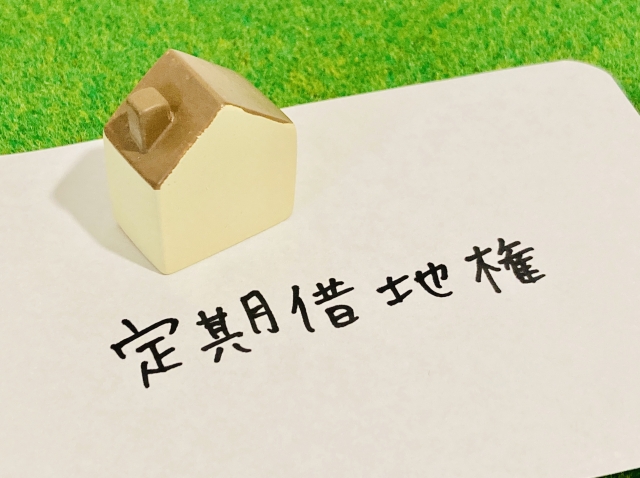





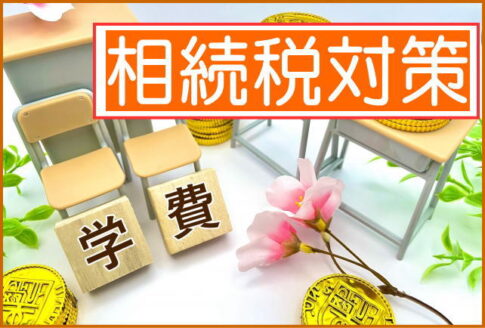

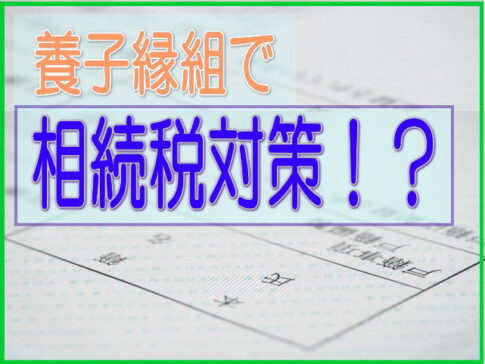


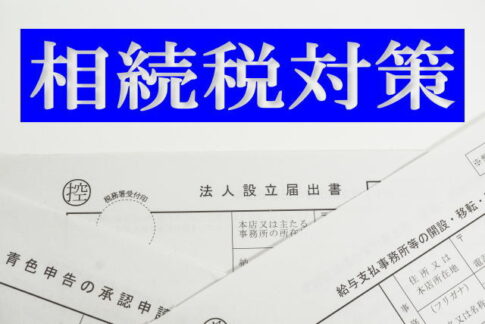







3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が 配偶者+子ども2人 の場合
→3,000万+600万×3=4,800万円の控除