
国税庁によると、令和4年中に亡くなられた方は1,569,050人、このうち相続税の課税対象となった被相続人(亡くなったご家族)は150,858人でした。つまり、令和4年分の相続税の課税割合は被相続人の数に対して9.6%です。令和3年度は9.3%だったことから、相続税を支払う必要がある人は増加しています。
相続税を支払う必要があるか知るためには、被相続人の相続財産の総額を把握し、適切に評価を行った上で相続税計算に臨む必要があります。
遺された相続財産の評価は、現金や預貯金は評価を行いやすいですが、土地など難しい財産も有ります。そこで、本記事では相続税を計算する時に必要となる「相続税評価額」について、調べ方や土地の計算方法をわかりやすく解説します。
参考URL 国税庁 令和4年分 相続税の申告事績の概要 令和5年12⽉ Ⅰ.令和4年分における相続税の申告実績における概要
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税評価額とは?評価方法を詳しく解説

相続税の納税が必要かどうか、まずは被相続人が遺した相続財産について「相続税評価額」を定める必要があります。現金・預貯金・土地・家屋など相続財産にはいろんな種類がありますが、どのように評価を確定させるのでしょうか。
そこで、この章では相続税評価額の評価方法を詳しく解説します。
相続税評価額の計算方法とは
相続税評価額は、原則として財産の「時価」を基準に算出します。
相続税評価額は財産の種類によって算出するための「計算方法」が異なっています。
たとえば、被相続人の預貯金が5,000万円だった場合、基本的に「相続開始時点での預金残高」がそのまま評価額になります。(多額の場合は既経過利息も加算します)
しかし、上場株式や非上場株式の場合は計算が預貯金とは全く異なります。車の場合は、買取相場価格を用いたり、査定額を用いたりなどの方法で評価します。
このように、財産に合わせて計算方法は異なっており、財産1つひとつに合わせて評価額を確定していく必要があります。
なぜ相続税評価額が重要なのか?
相続税評価額は以下3つのポイントが重要です。
- 納税額の決定
相続税評価額は、相続税の金額を決定する基礎です。 評価額の増減で納税額も変動します。 - 遺産分割への影響
遺産分割を行う際、各財産の評価額を基準として分割する場合が多く相続税評価額は遺産分割の重要な指標です。 - 節税対策の基準
生前贈与や相続時精算課税制度の活用など、相続税の節税対策を検討する際にも、相続税評価額は重要な判断材料です。
特に押さえておきたい「土地の相続税評価」とは

相続税評価額の計算の中でも「土地の相続税評価」については特に押さえておくことが大切です。土地は相続するエリアによっては高騰していることも多いため、丁寧に評価を行う必要があります。そこで、この章では土地の評価の計算方法や調べ方を詳しく解説します。
土地の評価方法は2種類ある
土地の評価額を定める際には、2つの計算方法があることを知っておきましょう。
①「路線価方式」
都市部や住宅地の土地を評価する際には、基本的に「路線価方式」を採用します。
路線価方式の計算式は以下です。
路線価とは、国税庁が毎年定めるもので毎年7月に公表されており、以下サイト(全国地価マップ)から確認できます。しかし、すべての土地に路線価が振られているわけではありません。
同じ地区にある土地なら路線価は共通しますが、土地の形状などによって利便性は大きく異なります。そこで、補正率で調整します。
補正率の詳細は後述します。
参考URL 全国地価マップ
②「倍率方式」
倍数方式とは、路線価がないエリアで行われている土地の計算方法です。各地域ごとに定められている倍数を用いて計算します。
相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
※評価倍率は国税庁が場所ごとに設定しています
評価倍率については以下サイトから確認できます。
参考URL 国税庁 財産評価基準書路線価図・評価倍率表
補正率とは
路線価方式で計算する場合は「補正率」で土地の実態に合った相続税評価額の調整が必要です。しかし、補正率は大変難しく、相続税に十分な知識がないと適切な計算ができないケースもあります。
実際に土地を評価する際には、以下のような土地について、慎重に補正を行う必要があります。
- 土地の形がいびつである
- 間口(道路との接触部分)が狭い
- 宅地であるが斜面やがけがある
- 非常に広い
適正に補正率を判断するためには、税理士など専門家に任せることが大切です。
主な土地の補正率の種類とは?

相続税における土地評価では、土地の形状や利用状況などに応じて評価額を調整するために、様々な補正率が用いられます。これらの補正率を適切に理解し適用することで、適正な相続税額を算出することができます。
以下に、主な補正率の種類と内容を解説します。
不整形地補正率
「不整形地補正率」とは、土地の形状が不整形である場合に適用される補正率です。いびつな部分の割合に応じて評価額をします。
不整形地の評価はの基本的な計算方法は以下です。
・不整形地の相続税評価額=想定整形地の評価額×不整形地補正率
なお、不整形地補正率を算出するためには「かげ地割合」と呼ばれる係数が必要です。
かげ地割合については以下の式で算出することができます。
・かげ地割合=(想定整形地の地積-不整形地の地積)÷想定整形地の地積
想定整形地…不整形の土地を取り囲むように想定された長方形の土地部分
かげ地割合のかげ地…不整形でない部分
このようにして算出したかげ地割合を、国税庁のホームページにある不整形地補正率表に当てはめることで調整率を算出します。
間口狭小補正率
「間口狭小補正率」は、間口(道路に接する部分)が著しく狭い場合に適用する補正率です。間口が狭い土地は、利用効率や利便性が低下するため相続税評価額を減額します。
補正率は、間口の広さを調べ、国税庁のホームページで公開されている「間口狭小補正率表」に当てはめることで求めることができます。
奥行長大補正率
奥行長大補正率は、間口の幅に対して奥行きが極端に大きい場合に適用する補正率です。
奥行距離が間口距離(道路に接する幅)の2倍以上である場合に適用します。奥行きが著しく長い土地は、利用効率が低下するため評価額を減額します。
「奥行き÷面積間口」で計算し、国税庁のホームページで公開されている「奥行長大補正率表」に当てはめます。
奥行価格補正率
奥行価格補正率とは、土地の奥行距離(道路からの距離)が標準的な距離よりも著しく長い、または短い場合に適用されます。土地の利用効率や利便性を考慮し、評価額を調整します。
基本的な計算方法は以下です。
奥行価格補正率による相続税評価額=路線価×画地調整率(奥行価格補正率を含む)×土地面積
その他
この他に、特別警戒区補正率や、規模格差補正率などもあります。補正率は種類も多く、調べ方も難解です。
計算するためには現地調査を要することも多く、時間がかかります。相続税申告には期限があるため注意が必要です。
土地の相続税評価額の調べ方とは

土地の相続税評価額を調べる方法は複数あります。ここでは主な方法について詳しく説明します。
国税庁を利用する方法
国税庁のウェブサイトでは、財産評価に関するさまざまな情報やツールが提供されています。
路線価図や評価率表といった、基準となる路線価を確認することができる閲覧サービスです。路線価が設定されていない地域については、評価倍率表も公開されているため、これらを活用することで土地の評価額を明確にすることが可能です。
国税庁のウェブサイトでは財産評価基準書も公開されています。この基準書には各種財産の評価方法が詳細に記載されており、年度ごとに更新される評価基準を確認できます。
無料で調べる方法
土地の相続税評価額を無料で調べる方法もあります。
・インターネット上の不動産価格サイトを利用する
・無料の相続税評価額シミュレーターを活用する
・固定資産税評価証明書を取得する
詳細な補正率などを加える必要がありますが、上記のようなツールを使えば、無料で相続税評価額をある程度把握することが可能です。
土地の使用状況も相続税評価額に影響する
相続税評価額には、調べた結果に基づき単純に計算するのではなく、土地の使用状況についても考慮が必要です。
評価額に影響を与える主な用途は以下の通りです。
1.賃宅地(他人に貸しているもの)
2.貸家建付地(例:貸アパートなど)
3.駐車場
4.私道
5.小規模宅地等
使用状況も正しく反映させた上で相続税評価額を算出します。
相続税評価額の算出を税理士に依頼すべき理由とは

相続税評価額の算出を税理士に依頼すべき理由は、主に以下の点が挙げられます。
適切な評価額の算出
相続税評価額は、財産の種類や状況によって計算方法が異なり、専門的な知識が必要です。
税理士は、税法や評価に関する専門知識を有しており、適切な評価額を算出できます。特に土地や非上場株式などの評価は複雑であり、専門家による評価が不可欠です。評価が遅れてしまうと、相続税申告も遅れてしまうおそれがります。遅れるとペナルティが課せられるため注意が必要です。
税務調査のリスク軽減
相続税申告を誤ってしまうと、税務署による税務調査の対象となる可能性があります。
税理士は、税務調査で指摘されやすいポイントを把握しており、適切な評価を行うことで税務調査のリスクを軽減できます。
税務調査で評価額が過少であると指摘された場合、追徴課税や延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。
節税対策ができる
相続税には、様々な特例や控除があり、適用することで税額を軽減できます。
税理士は、これらの特例や控除に関する知識を有しており、最適な節税対策を提案できます。特に土地の評価においては、さまざまな減額要因があり、経験豊富な税理士による評価によって税額を大きく減らせる場合があります。
煩雑な手続きの代行
相続税申告は、相続税評価額の計算だけではなく、書類の作成や収集など、煩雑な手続きが必要です。税理士に依頼することで、これらの手続きを代行してもらい、時間や手間を削減できます。
特に、相続人が複数いる場合や財産の種類が多い場合は、手続きが複雑になりやすく専門家のサポートが有効です。
まとめ
相続税評価額は相続税計算の基礎となるものであり、適切に計算を進める必要があります。評価方法は財産の種類によって異なるため、相続税の専門家である税理士にご依頼頂くことがおすすめです。
横浜市の響き税理士法人では、相続税評価額に関するご相談にも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。



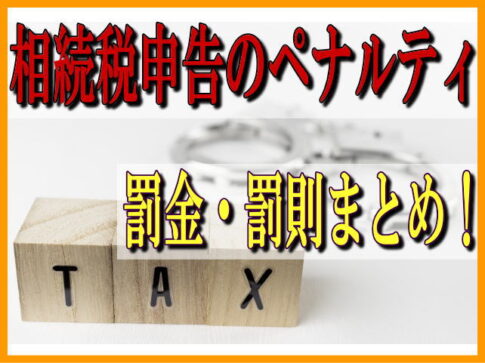








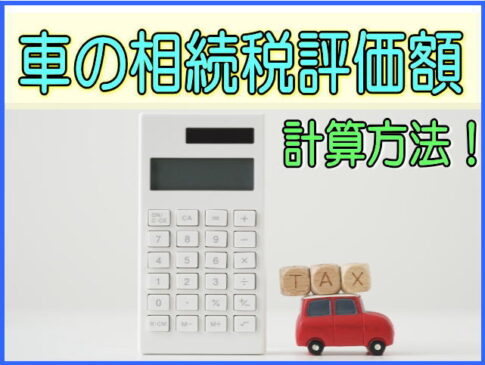
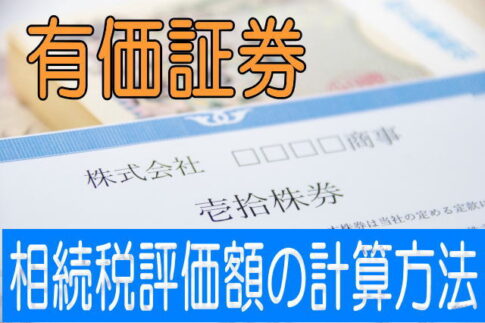






相続税評価額=路線価 × 地積(㎡)× 補正率 ※地積とは土地の面積を意味します