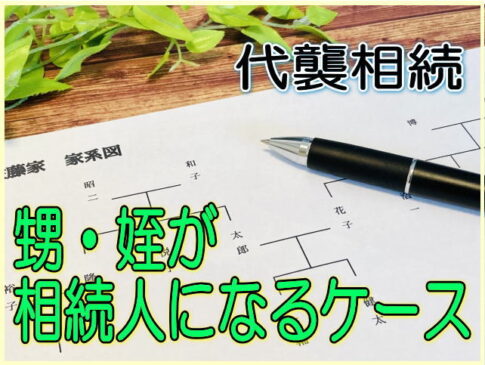死因贈与は相続とは異なり、贈与契約として扱うため財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との間で生前贈与と同様に契約を交わします。
しかし、贈与であっても相続人全員に承諾をもらう必要がある場面もあることはご存じでしょうか。
そこで、本記事では「死因贈与で相続人全員の承諾が必要となるケース」を中心に解説します。執行人がいたほうが望ましいケースなどにも触れますので、ぜひご一読ください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
死因贈与契約には相続人全員の承諾が必要?

死因贈与とはご自身が亡くなられた後に、特定の人に財産を遺す方法です。相続以外に大切な方へ財産を繋いでいく方法として、今注目が集まっています。
では、死因贈与を契約する際には、将来相続人になる可能性がある人全員の承諾は必要となるでしょうか。本章で詳しく解説します。
死因贈与契約時には不要
死因贈与は、贈与者が亡くなったときに財産を受贈者に渡すことを約束するものであり、贈与契約を結ぶ必要があります。
この契約は、贈与者と受贈者の二者間で合意すれば成立します。
つまり、契約を結ぶ時点では、相続人全員の承諾や同意は不要です。この点は生前贈与と同じです。
死因贈与で相続人全員の承諾が必要になる手続きとは

死因贈与契約時には相続人の承諾は不要ですが、贈与契約の方法や、贈与者の死後に発生する手続きによっては相続人の協力や承諾が不可欠となるケースがあります。押さえておきたいケースは以下のとおりです。
口頭で契約する死因贈与
死因贈与は法律上、口頭でも成立します。
たとえば、父が長男に「将来自分が亡くなったら、実家の土地と建物をもらってほしい」と伝え、子が承諾していたら死因贈与は成立することになります。
しかし、実際には贈与者の死後、死因贈与が成立している事実を証明できず、受贈者が財産を受け取れないというトラブルが発生しています。
上記のケースでは、長男以外の相続人が「そんな契約は知らない」と主張した場合、受贈者である長男は契約の存在を証明しなければなりません。
このため、契約書がない口頭契約による死因贈与は、相続人全員の承諾(または協力)が事実上必須となります。
不動産の名義変更
死因贈与により不動産を取得した場合、受贈者は贈与者の死後に、法務局で「所有権移転登記」を行う必要があります。
この登記手続きは、受贈者と贈与者の相続人全員が共同で申請することが原則とされています。この際に相続人全員の実印、印鑑証明書などの書類が必要となるため、実務上、相続人全員の承諾が不可欠です。
相続人の承諾を避ける方法はある?

暦年贈与などの生前贈与よりも、死因贈与時には「相続人全員の承諾」が必要となるケースがあるため、十分に注意しましょう。
では、承諾を避ける方法はあるのでしょうか。それぞれのケースにわけて解説します。
口頭の死因贈与契約時
口頭の死因贈与で、相続人全員の承諾を避ける方法には以下が挙げられます。
①書面(公正証書)を作成する
口頭での死因贈与は避け、公正証書による契約書を作成することがおすすめです。公正証書があれば、相続人が契約の存在を否定することはできません。死因贈与による公正証書の作成は、公正証書遺言のように証人2名の立ち会いも不要です。
②証人を用意する
死因贈与を書面化せずに口頭で契約を結ぶ場合、中立的な第三者に証人になってもらうことが大切です。弁護士等の士業、贈与者・受贈者以外のご家族、友人や知人などが検討できるでしょう。
証人の用意が難しい口頭による死因贈与は争いになる可能性が高いため契約書の作成を選択することがおすすめです。
不動産のある死因贈与契約時
不動産の名義変更に必要な相続人全員の協力を不要にする方法もあります。その方法とは「遺言執行者を指定すること」や「不動産の仮登記」を行っておくことです。
①執行者を指定する
死因贈与契約書の中で執行者を指定しておけば、贈与者の死後、受贈者は遺言執行者と共同で名義変更の登記申請ができます。この場合、相続人全員の協力は不要です。
②死因贈与を原因とする仮登記を行う
生前のうちに、不動産に「死因贈与を原因とする所有権移転の仮登記」を行っておけば、贈与者の死後、受贈者が単独で本登記を申請できます。この手続きも相続人全員の協力は不要です。
不動産の仮登記は贈与者と受贈者が共同で申請する必要がありますが、死因贈与契約書が公正証書で作られている場合は受贈者が単独で申請できます。
つまり、①・②は死因贈与契約書を作成する際に「公正証書で作成し、執行者も指定しておく」ことでスムーズに実現できます。
死因贈与時の執行者の役割

執行者とは、死因贈与が効力を発揮する贈与者の死後、速やかな手続きをサポートしてくれる大切な存在です。では、執行者の役割とはどのようなものでしょうか。
死因贈与における執行者とは
死因贈与における執行者とは、生前に結ばれた死因贈与の内容を実現するため、財産の管理や、名義変更などの手続きを担う人のことです。
死因贈与は民法の「遺贈に関する規定」が準用されるため、死因贈与契約でも執行者を指定できます。
先に触れたとおり、執行者がいると相続人全員の承諾なく不動産の名義変更をスムーズに進められるなどのメリットがあります。
遺言執行者になれる人
執行者になれる人に特別な資格は必要ありませんが、財産の管理や分配、名義変更などの手続きは法的知識が必要なことも多いため、執行者選びは慎重に決めることが大切です。
特に財産が高額であったり、受贈者以外に相続人になる方への財産の分配なども必要な場合、税理士や弁護士などの専門家を指定することが望ましいでしょう。
死因贈与で執行者がいた方がよいケース
死因贈与の執行者がいることで、不動産登記手続きにおける相続人全員の協力が不要になるだけでなく、以下のようなケースでもスムーズな手続きが可能となります。
①相続人間に不仲や争いがある場合
相続人の心情に関わらず、執行者が契約を実現するために手続きを進めていけるため、財産がなかなか受贈者のものにならないといったトラブルを回避しやすくなります。
②受贈者が手続きに不慣れな場合
複雑な登記手続きや、金融機関での手続きを専門家である執行者に任せられます。
③財産に非上場株式など複雑な手続きがある場合
会社の承継などを理由に非上場株式を死因贈与している場合、名義書換に専門的な知識が必要となるため執行者の存在は特に重要です。非上場株式の多くは定款で譲渡制限が設けられているため、死因贈与の契約時には丁寧に確認しながら手続きを進める必要もあります。
知っておきたい死因贈与によくあるトラブルとは

死因贈与は特定の相手に確実に財産を渡せる方法ですが、その性質上、相続発生後にトラブルになりやすい側面を持っています。ここでは、死因贈与で特によくあるトラブルを解説します。
相続人が死因贈与を認めない
死因贈与は生前に行われる契約のため、相続開始後に契約を知った受贈者以外の相続人が反発するトラブルがあります。
相続人側が「親父がそんなこと言うはずがない」「母は私にもお金をくれると約束した」などと主張し、財産の引き渡しや不動産の名義変更に協力しないことも予想されます。
死因贈与契約が口頭であったり、公正証書ではない私的な書面のみであったりする場合、相続人はその契約が本当に正しく結ばれたものなのか疑問を持つことも少なくありません。
こうした家族の紛争を避けるためにも、死因贈与契約は公正証書で作成し、その中で執行者を指定しておくことを検討しましょう。
遺留分の侵害が発生してしまった
死因贈与も遺言と同様に、財産を特定の個人(受贈者)に集中させるため、他の相続人の遺留分(相続人が最低限受け取れる財産)を侵害する可能性があります。
できれば死因贈与契約を結ぶ際には、遺留分に問題はないかなど専門家に相談しておくことが望ましいですが、遺留分を考慮せず死因贈与してしまった場合は注意が必要です。
遺留分を侵害された相続人は、受贈者に対して遺留分侵害額請求(金銭の支払い請求)を行うことができます。
受贈者は、せっかくもらった財産から金銭を支払う必要が生じるため、生前に遺留分を侵害しない範囲で契約するか、請求に備えて金銭を準備しておく必要があります。
もらえた人・もらえなかった人の間で対立する
死因贈与は、特定の受贈者と契約を結ぶため、その人ともらえなかった他の相続人との間で感情的な対立を引き起こしやすい傾向があります。
贈与者が生前に家族間で契約について説明せず、不公平感が残ったまま相続が発生してしまうと、「なぜあの人だけが」「納得がいかない」という感情的な対立が生じます。二次相続の際にも、こうした感情面の対立が残っている可能性があるため注意が必要です。
死因贈与を行う際は、その意図や理由を家族に説明し、遺留分にも配慮を示すことが、後の紛争を防ぐ上で重要です。介護などを理由に死因贈与をする場合は、負担付死因贈与にするなど工夫をしておくことで、その他の相続人も納得を得やすくなるでしょう。
遺言書も見つかった
贈与者が亡くなった後に、死因贈与と内容が矛盾する遺言書が発見されてしまうことがあります。すると、いつ作成されたのか、どちらが優先されるのかでトラブルになることがあります。
死因贈与と遺言書では、作成日付が新しいものが優先されます。(民法554条、1023条)
- 先に遺言書が作成されたが、あとに死因贈与を結んでいたら、遺言書の内容は撤回される
- 先に死因贈与を結んでいたが、あとに遺言書が作成されていたら死因贈与の内容は撤回される
遺言書を書いて、先に結んでいた死因贈与の撤回を行う際は、作成日付が決め手となるため効力がしっかり発揮できるように遺言書の形式には注意することが大切です。
登記や取得にかかる税金が相続時より高い
死因贈与は相続税の対象となり基礎控除を受けられるメリットがある一方で、不動産を贈与の対象とする場合、相続時にはかからない以下の税金が受贈者(財産をもらう人)に課税されます。
この税負担を考慮していないと、「思っていたよりも税金が高い」というトラブルにつながります。
① 不動産取得税が発生する
不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得したときにかかる都道府県税です。
死因贈与は、財産を取得する原因が「相続」ではなく「贈与」とみなされるため、原則として不動産取得税の課税対象となります。
税率は原則として固定資産税評価額の3%(宅地)または4%(住宅以外の家屋等)です。
相続や包括遺贈(財産の割合を指定する遺贈)で不動産を取得した場合は、この不動産取得税が非課税となります。死因贈与で不動産を取得する場合、この税金が追加でかかることが大きな負担となります。
② 登録免許税が発生する
不動産の名義を贈与者から受贈者へ移す所有権移転登記を行う際に、登録免許税が発生します。
死因贈与による所有権移転登記の税率は、固定資産税評価額の20/1000 (2.0%) です。
相続や包括遺贈による所有権移転の登記の税率は、法定相続人の場合は固定資産税評価額の4/1000 (0.4%) です。(法定相続人以外は2%)
死因贈与の場合、相続時と比べて登録免許税の税率が大きいため、不動産の評価額が高いほど、この税負担は大きくなります。
まとめ
死因贈与契約を検討されている方は、相続人間に不要なトラブルが生じないよう、専門家へ相談を重ねた上で契約を行うことがおすすめです。
横浜市に拠点を持つ響き税理士法人は、死因贈与や遺言を含む相続全般のご相談に対応しています。
お客様の想いを実現し、ご家族間の紛争を未然に防ぐため、最適な契約方法や税務対策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。